
難聴の人や聴覚障害者と、健聴者との間では聴こえに大きな差があります。
障害の原因や程度の差だけでなく、同じレベルの聴力であっても聞こえ方の違いもあります。
健聴者の一般的な聴力は0~25dBですが、25dB以上の聴力となると難聴者の位置づけになります。
25dBの音は、用紙に鉛筆で文字を書く音や時計の秒針が動く音が目安です。
今回は、健聴者と難聴者の聴こえにおける違いを紹介します。
聴力レベルに対する聴こえの程度、生活音や人の声における音量の目安についても解説していますのでコミュニケーションとして相手に伝わるための基準として参考にしてください。
難聴レベルにおける平均聴力
一般的にいわれる難聴レベルとその平均聴力は、以下の通りです。
| 難聴の程度 | 平均聴力(dB) | 日常生活における聞こえの目安 |
|---|---|---|
| 正常値 | 0~25dB未満 | よく聞こえる |
| 軽度難聴 | 25~40dB未満 | 小さい声や騒音下での会話が聞き取りにくい |
| 中等度難聴 | 40~70dB未満 | 普通の会話が聞き取りにくい |
| 高度難聴 | 70~90dB未満 | 耳元の大きな音や声でも聞き取りにくい |
| 重度難聴 | 90dB以上 | ほとんど聞こえない |
難聴の程度については別記事で紹介しますが、難聴の程度には軽度難聴・中等度難聴・高度難聴・重度難聴として位置づけられます。
健聴者と難聴者の聞こえにおける聴力の差は、以下の通りです。
一般的な聴力の位置づけ
聴力は、0dBに近いほど小さな音が聞こえることを意味し正常値に近いことを示します。
聴力が10dBということは10dBの音が聞き取れることを意味し、同様に普通の会話と音量が同じ聴力が60dBということは60dBの音でないと聞き取れないことを意味します。
上記表の通り、一般的に正常な聴力は0~25dBです。
聴力は防音室で特殊な機器を用いて測定されるためあくまで参考程度ですが、静かな場所でのささやき声や時計の秒針が動く音が聞こえるかどうかが聴力の目安となります。
難聴に位置する聴力は25dB以上
難聴といわれる、聴力は25dB以上です。
25dBの音は、例えば用紙に鉛筆で文字を書く音や時計の秒針が動く音に相当します。
深夜の郊外や図書館といった静かな空間で人のささやき声が聞こえるような状況です。
そして、25~40dBの聴力は軽度難聴と位置づけられます。
このため20~30dBの聴力の場合、正常域と難聴の境目であることがいえます。
100dB以上は聴覚機能に注意
90dB以上の音量でようやく聞こえることは、重度の難聴に相当します。
100dB以上になると健聴者にとっては聴覚機能に異常をきたす恐れがあり、難聴の程度ではろう者(聾者)に近いレベルです。
生活音・人の声における音量の目安
音の大きさに対する生活音には、どんな例があるのでしょうか。
音量レベルにおける生活音や人の声量、難聴の人が聞こえる程度は以下の通りです。
| 音の大きさ | 生活音の例 | 人の声量での例 | 難聴の程度 |
|---|---|---|---|
| 0dB~ | 健聴者が聞き取れる最も小さい音 | 人の声はほとんどない | 正常 |
| 10dB~ | 雪の降る音 | 呼吸の音 | 正常 |
| 20dB~ | 木の葉が擦れ合う音 | 小さな寝息 | 正常または軽度の難聴(25dB~) |
| 30dB~ | 深夜の郊外や病室内、鉛筆で用紙に文字を書く音 | 小さなささやき声 | 軽度の難聴(小さな音は聞こえにくい) |
| 40dB~ | 図書館内や昼間の閑静な住宅地 | ささやき声での会話 | 中等度の難聴(40dB~) |
| 50dB~ | 木々のざわめき、家庭用エアコンの室外機、換気扇 | 小さな声での会話 | 中等度の難聴(普通の音が入りにくい) |
| 60dB~ | デパートなどの店内、家電の作動音 | 普通の声量での会話 | 中等度の難聴(普段の会話が聞こえにくい) |
| 70dB~ | 騒々しい室内、電話のベル、セミの鳴き声 | 大きな声での会話 | 高度の難聴(70dB~) |
| 80dB~ | 走行中の電車内、救急車のサイレン、パチンコ店内 | かなり大きな声 | 高度の難聴(大きな声でも聞こえにくい) |
| 90dB~ | カラオケ中の店内、犬の鳴き声 | 怒鳴り声、独唱 | 重度の難聴(90dB~) |
| 100dB~ | 電車が通過する時のガード下 | プロの歌声 | ろう者(100dB~) |
| 110dB~ | 自動車のクラクション | 聴覚機能に異常をきたす | ろう者(耳元の大きな声でも聞こえにくい) |
| 120dB~ | 近くでの落雷、バイクの加速音 | 聴覚機能に異常をきたす | ろう者(日常の会話が聞こえない) |
上記表はあくまで目安です。
その場の状況や環境、相手の発する音域といった条件などにより個々の感じ方や大きさは違いますので参考としてください。
音量・声量における違い
健聴者にとっては普通の音量に思えても、難聴者には小さく聞こえることは当然にあります。
例えば普通の会話では一般的に60dBくらいの音量ですが、難聴者に聞こえる度合いは低くなりようやく聞き取れる程度であれば中等度の難聴です。
つまり健聴者が自分の聴力に合わせた声量で話しても難聴者に届かないことが多いため、難聴者の様子を見ながら話し声の大きさを調節する必要があります。
とはいえ、難聴者が聞き取れる話し声は音量だけが問題ではありません。
音量に問題はなくても音質や内容が聞き取りづらいこともあるため、難聴の人と話をしながら伝わりやすい話し方を工夫してあげてください。
逆に難聴者も自分の声が聞こえる大きさを基準としているため、健聴者にとって大きく聞こえることもあるでしょう。
また難聴者に聞こえる洗濯機や掃除機といった生活音も健聴者より小さく聞こえることになるため、近所迷惑にならないよう家電の作動音や物音には時間帯などに注意しながら生活しているのが実情です。
聴力レベルによっては身体障害者に該当
聴力が一定以下まで低下している人は聴覚障害者となり、身体障害者福祉法に基づいて身体障害者手帳が交付されます。
一例として両耳が騒々しい室内くらいの70dB以上、あるいは片耳が90dB(カラオケ店内)以上でもう一方の耳が50dB(家庭用エアコンの室外機)以上でなければ聞こえない聴力レベルとなると最も等級が低い6級に相当します。
次の等級に5級の認定はなく、その上の4級では両耳が80dB(走行中の電車内)以上などが該当します。
障害等級については、別記事で紹介します。
難聴者と健聴者の聴力差まとめ
健聴者と難聴者ではまったく異なる聴力レベル。
同じ聴力でも音量だけでなく、音域や音質によって聴こえはさまざまです。
どのくらいの声量や音質ならより伝わりやすいかは、コミュニケーションの頻度を増やすことが重要です。
聴覚だけに頼らないコミュニケーション手段として、手の位置や動かし方、顔の表情などで意思を伝える手話や指文字といったジェスチャーがあります。
また唇や舌の動きや顔の表情から話の内容を読み取る口話(読唇)、メモ用紙などに文字を書いて意思を伝え合う筆談などもコミュニケーション手段の1つです。
根気のいることですが、難聴者も健聴者の声をどうしたら聞き取れるか声質を脳内にインプットしたり相手の口の動きを読んだりして工夫しながら聞き取ろうとしています。
近年ではノートPCやスマートフォンを用いたチャットやメール機能も増えていますので、音声以外のコミュニケーションツールを活用してより正確な意思疎通が図れるようにしていきましょう。


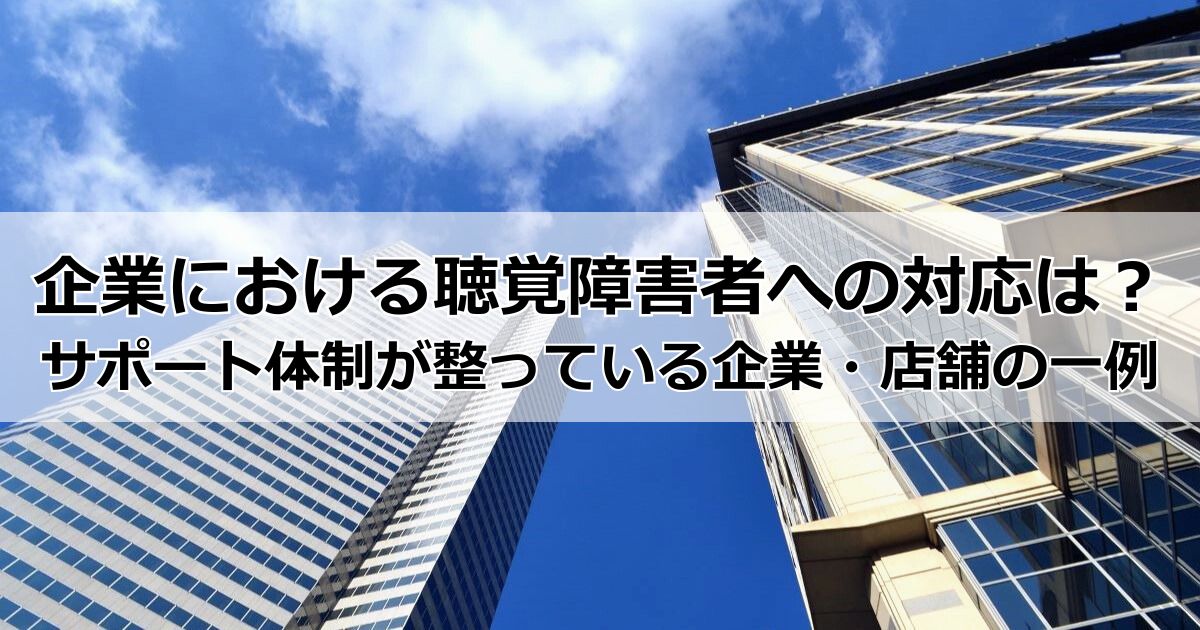
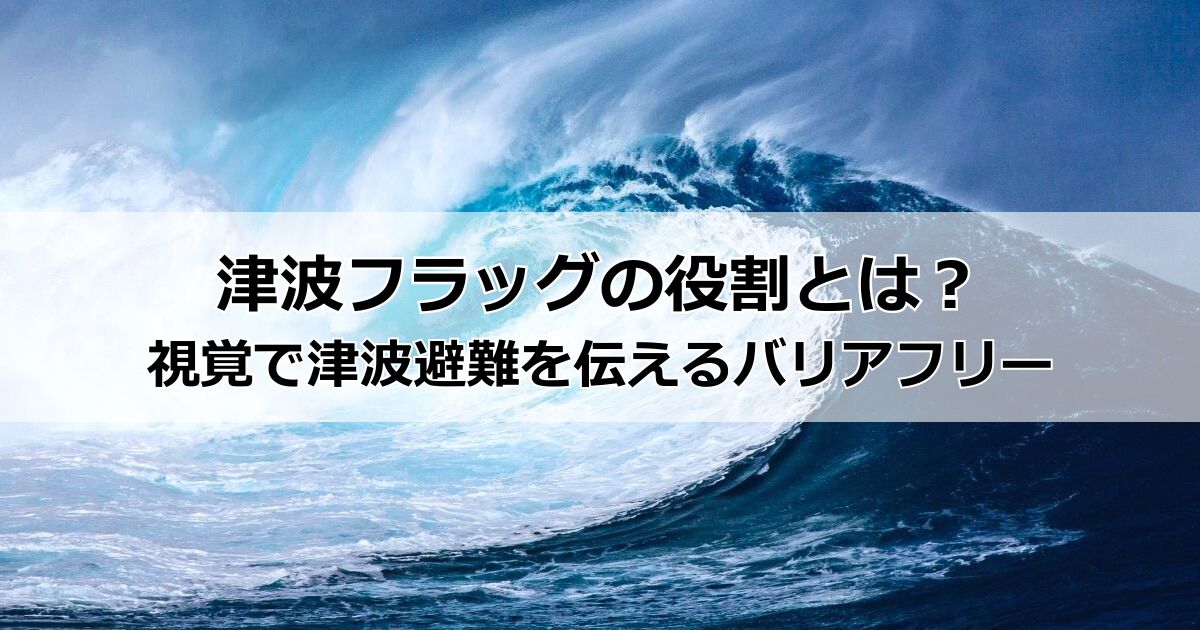

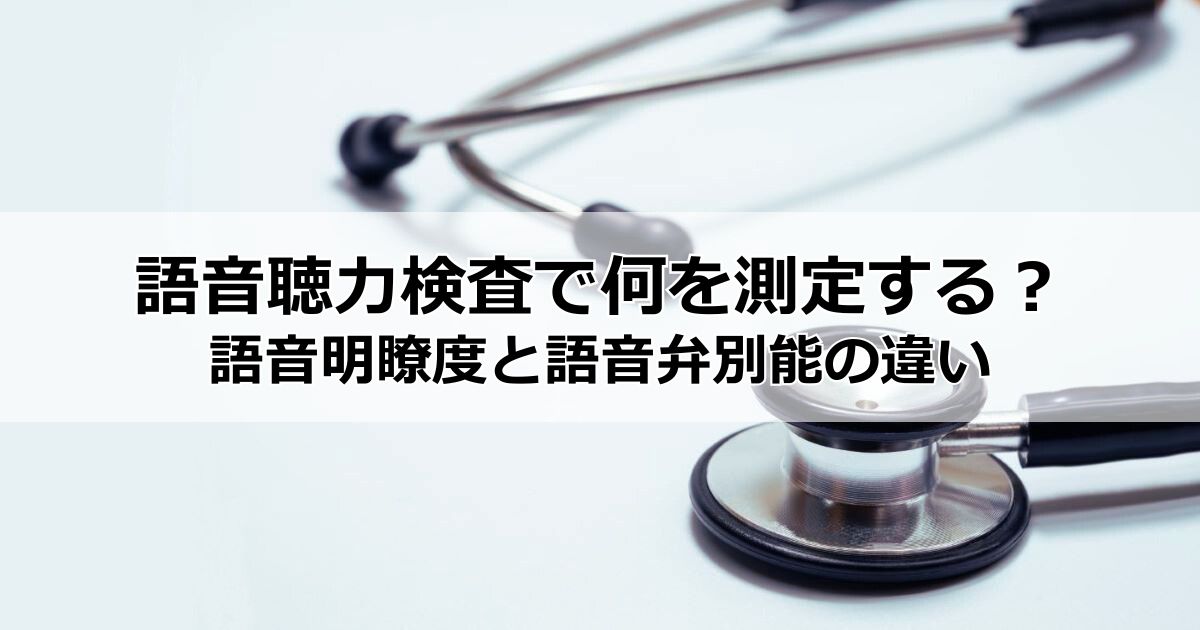
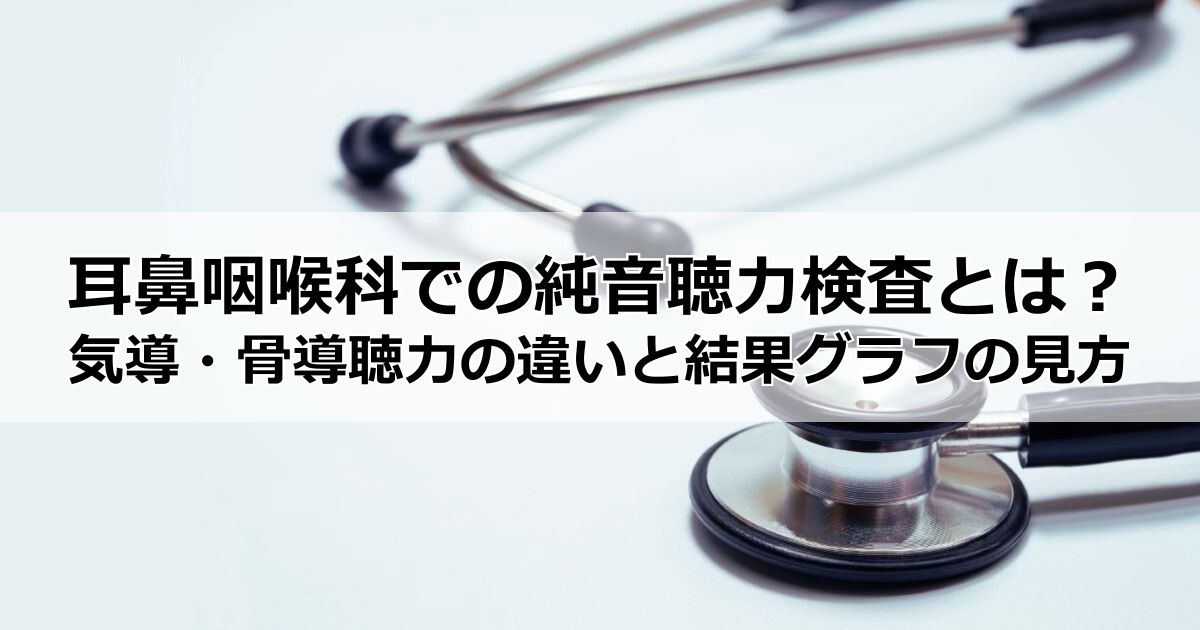
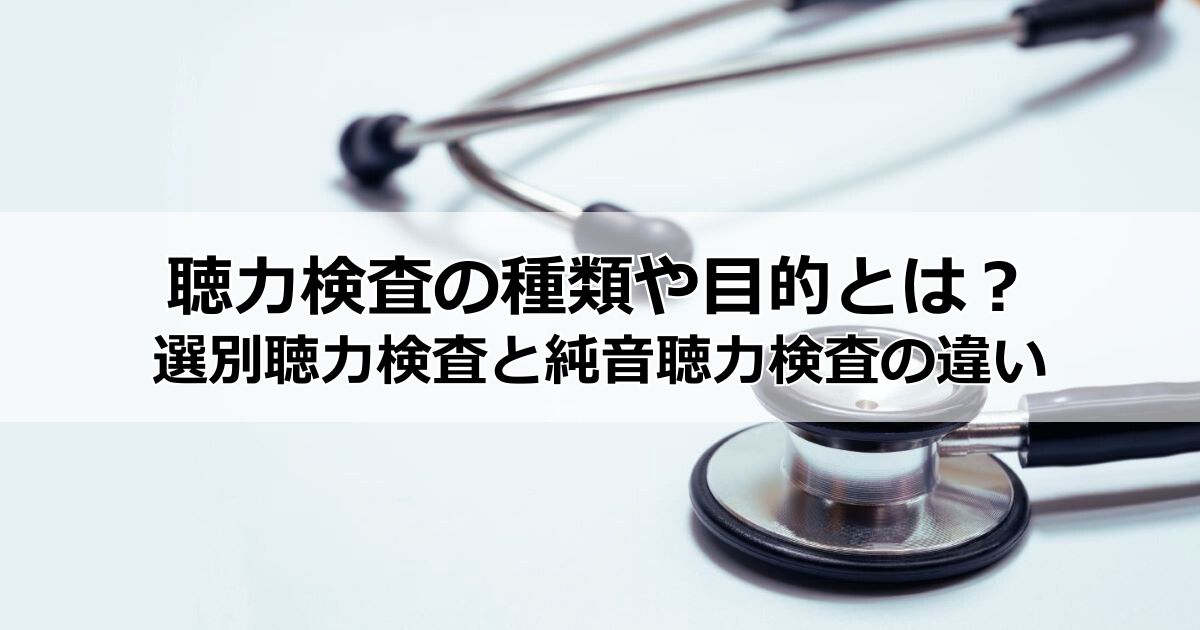
コメント