
日常でよく使う物の音や人の会話する声が聞き取りにくかったり聞こえなかったりすると、本人だけでなく直接関わる周囲の人も戸惑ってしまうものです。
そんな時にどういったやりとりをしたらいいのか、どうすれば会話がしやすくなるのかわからないと悩む人もいるのではないでしょうか。
難聴の人とのやりとりや会話をサポートするには、手話や口話、筆談といった手段があります。
この記事では、難聴・中途失聴者や聴覚障害者といった耳の不自由な人とやりとりするにはどうしたらスムーズにできるのかコミュニケーション手段について説明します。
会話などのコミュニケーションをとるのに便利なツールやアプリも紹介しますので、難聴の人をサポートするためのご参考になれば幸いです。
難聴の人がコミュニケーションで困ること
難聴・中途失聴者や聴覚障害者など耳の不自由な人にとって、コミュニケーションをとる上で難しいことや困難なことがいくつかあります。
まず、コミュニケーションにおいて難聴の人がぶち当たる主な困りごとを紹介します。
自分への呼びかけに気づかない
難聴の人は、本人の見えない位置から呼びかけられたり話しかけられたりしても反応できずコミュニケーションがとりにくくなります。
また病院や店舗などの待合室で、自分の名前を呼ばれても気づかないことが多いです。
周囲の話が聞き取れない
難聴や聴覚障害がある人は、セミナーや講演会といった大勢の人が集まる広い会議室で遠くにいる講演者の発する内容を聞き取れないことがあります。
複数人での会話でも周りの話す内容があまり聞き取れないことで、周囲とのやりとりに難しさを感じることも多いです。
会話がスムーズにできない
難聴・失聴の人は一対一での直接対話など最低限の会話ができますが、内容すべてを理解することは難しい面があります。
複数人での会話になると次に話す人がわからなくなり、会話の流れが理解できなくなることも多いです。
生活音に気づかない
日常で入ってくる通常の音や声は聞こえるものの、聴力の程度によってはテレビやインターホンなど生活する上で必要な音が入りづらいことがあります。
在宅中でも電話やインターホンの鳴る音が聞こえないと気づけません。
洗濯機や電子レンジなどの家電製品の稼働が終わったアラーム音に気づかないことも多いです。
音声情報が聞き取れない
難聴の人は電話やインターホンの鳴る音に気づけたとしても、相手が誰なのかわからないだけでなく用件が何なのか聴力の程度によって聞き取りが困難です。
テレビやラジオの音が聞こえないと情報が不足しがちで、防災訓練や災害発生時の緊急放送が聞こえないという問題もあります。
緊急時の警報アラームは聞こえるかもしれませんが、店内放送や交通機関の車内放送が聞こえないと何が起こっているのか把握できません。
上記のように難聴・中途失聴者や聴覚障害者など耳が不自由な人にとっては、とくにコミュニケーションにおいて難しいことや困難なことがあります。
これらの困りごとに対する対策については、別記事で詳しく解説します。
難聴の人や聴覚障害者のためにできること
難聴・中途失聴者や聴覚障害者など耳が不自由な人のために、私たち健聴者にできることはどんなことでしょうか。
聴覚に障害をもつ人へのサポートは難しいと感じるかもしれませんが、ちょっとした仕草や配慮が役に立ちます。
コミュニケーションをとること
耳の不自由な人でも、工夫次第では十分にコミュニケーションをとることが可能です。
難聴の人や聴覚障害をもつ人は、補聴器を装用している人・手話しかできない人・相手の声は聞こえるけれど自分では話せない人など、コミュニケーションをとる手段は人それぞれです。
コミュニケーションの手段については後述しますが、口話する時は口元が相手に見えるように発話するほか手話や筆談を活用することも可能です。
聞こえない・聞こえづらい人とのコミュニケーションに慣れていないと戸惑う人も少なくありません。
そんな時に覚えておきたいのは、多くの難聴や聴覚障害のある人が相手の顔を見てコミュニケーションをとることを意識しているという点です。
難聴の人や聴覚障害者と会話をする時に抑えておきたいポイントは、以下の通りです。
- 話し始める時は合図をする
- できるだけ大きく口を動かしながら
- 普段より少し大きめの発声をする
- 1文字ずつではなくゆっくり区切って話す
- 小さな間違いを責めない
難聴の人が聞き取れないことにより会話が成立しないことがわかると、もういいといったニュアンスで会話を終わらせる人も当然います。
伝わらないことに焦りや苛立ちを感じてしまうかもしれませんが、焦りは禁物です。
相手のいいたいことをうまく読みとれない、とわかると難聴の人はその人に対して心を閉ざします。
難聴の人は、とくに初対面の人などあまり話す機会のない相手が発する会話のコツをつかもうとしています。
ゆっくりとコミュニケーションに臨めば、意思疎通を図れるようになるでしょう。
お店や窓口での配慮
お店や窓口での配慮には、何か困っていることはないか手伝うことはあるかと声をかけることなどがあります。
とくにお店や窓口に耳マークが掲示されている場合は、耳が不自由な人に配慮した対応をしてくれることを表しているため探してみるのもひとつの手です。
電車やバスでの配慮
電車やバスの車内や駅のホームなどは、騒がしいこともあり音が聞き取りにくいものです。
乗り換えがわからなかったりアナウンスが流れていたりする場合、耳の不自由な人は自分から誰かに助けを求めないといけません。
このような場面で困っている人がいたら、何に困っているのかを聞き適切な対応をとりましょう。
難聴の人とのコミュニケーション手段
難聴の人や聴覚障害者の状況はさまざまで、手話を使う人もいれば話せるものの聞き取れないために口話で汲み取るという人もいます。
難聴者とのコミュニケーション手段として、以下の方法でのポイントを紹介します。
- 手話
- 口話
- 筆談
- 音声翻訳ツール
手話

手話(しゅわ)は、手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語です。
手話を母語として使う人を「聾者(ろう者)」といい、ろう者の間で手話は意思疎通を図るための大切な手段として受け継がれてきました。
騒がしい場所や声の聞こえない場所でも普通に話せるメリットがある一方で、手話を知っている人が少なく表現手法も少ないためいいたいことが伝わりにくいデメリットがあります。
また、難聴の人や聴覚障害者全員に手話ができるとは限りません。
筆者も言葉を覚えるとともに口話でのやりとりを訓練してきたため、現在でも手話はできません。
そのため、後述する口話や筆談でのやりとりがいいのか確認することが重要です。
口話

口話(こうわ)とは、相手の口の形から話の内容を読み取る「読話(どくわ)」と言葉を発する「発話」の総称です。
筆者は読唇術と呼んでいますが、難聴の人に向かって口の動きがわかりやすいように話すことでコミュニケーションをとることが可能です。
口話でのやりとりで気をつけるポイントは、以下の通りです。
- 口元が見えるように明るい場所で話す
- 一文字一文字を伝えるより文節ごとに区切ってゆっくり、はっきり話す
- ジェスチャーや視覚情報も加えながら伝える
口話は慣れや相当な訓練が必要な場合があり、全ての難聴者が理解できるわけではありません。
また複数の人と話す場やマスクなどで口元が見えない環境では、コミュニケーションをとることが困難です。
筆談

筆談は、メモ用紙や筆談器を使って文字でのやりとりをする方法です。
話す内容をすべて書く必要はなく、難聴の人によっては必要な情報だけを簡潔に書くだけで伝わる場合があります。
また、必要な情報を簡潔に書きながら口話やジェスチャーで補足します。
なお契約や金額など十分な確認が必要な情報については、齟齬(そご)がないように筆談で伝えることが重要です。
音声翻訳ツール・字幕アプリ

スマートフォンやタブレットなど近年のデジタル端末には、音声を文字に変換してくれるツールやアプリがあります。
精度も速度も向上してきているため、難聴者向けのコミュニケーションとしても利用することが容易にできます。
コロナ禍以降、オンラインでの打ち合わせが増えたことにより1人1人の顔は見えるものの、何を話しているかまでは画面上ではわからないことも多かったため字幕機能を備えたツールも増えました。
しかし口話の文字への自動変換には誤字がまだ多く、日本語には対応していないものもあるため難聴者や聴覚障害者への情報伝達は課題が残っています。
口話や筆談を交えつつ音声翻訳ツールや字幕アプリも利用することで、それぞれの欠点を補いながらコミュニケーションをとることが望ましいです。
職場や自社サービスでも提供する情報が視覚・聴覚情報のどちらかだけになっていないか確認し、情報のバリアをなくしていくことが難聴者を含めた多様な人とのコミュニケーションのとりやすさにつながります。
音声翻訳ツールやアプリについては、後述します。
難聴の人とのやりとりを補助するツール
難聴の人や聴覚に障害をもつ人とのやりとりを補助する手段として、真っ先に思い浮かべるアイテムといえばメールやチャットがあります。
また代表的な音声翻訳ツールとしては、リアルタイムで文字起こしをしてくれるZoomやTeamsといった会議アプリが知られています。
しかし難聴や聴覚障害をもつ人など、耳が不自由な人のための便利なツールやアプリがあるのをご存知でしょうか。
耳が不自由な本人だけでなく、会話やサポートをする人ももっておくと役に立つアイテムもあるため以下を参考にしてください。
筆談ボード・ノート
筆談ボードやノートは、文字でのやりとりを要する難聴の人が常に持ち歩いているアイテムです。
中でも軽量で書き消しができる筆談ボードがあると、会話での「聞き取れない」「聞こえない」をカバーできます。
電子メモパッドなら文字を消すのが簡単なためスムーズな会話につながり、軽量タイプであれば持ち運びもしやすいです。
紙のノートは、記録として残したい会話に便利です。
音声認識アプリ「こえとら」
こえとらは、聴覚障害者が健聴者など聞こえる人との間で文字と音声をお互いに変換し合うことで円滑なコミュニケーションができるよう支援するアプリです。
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)により開発され、内閣府でも紹介されています。
音声で文字入力ができるだけでなく逆に文字を音声へ変換してくれるため、文字で書いたりキーボード入力が苦手な人との筆談としても使うことが可能です。
よく使う文言が定型文として登録されており自身でよく使う文言も追加登録できるほか、文字だけでなく絵文字や地図などを使って情報を提示できます。
無償で提供されており、iOSとAndroidに対応しています。
音声認識と自動翻訳アプリ「UDトーク」
UDトークは、音声認識による文字起こしと自動翻訳などの機能を搭載したコミュニケーションを支援するためのアプリです。
聴覚障害者を扱ったテレビドラマの「silent」や「ファイトリング」などに起用されたことで注目を集めました。
インターネットを使って話した言葉を文字化したり入力した文章を読み上げてくれたりするアプリで、UD=ユニバーサルデザインを支援するために開発されました。
UDトークは基本的に無料で利用でき、iOSやAndroid、Amazon Kindleにも対応しています。
文字起こしアプリ「Group Transcribe」
Group Transcribeは、Microsoftが提供している無料の文字起こしアプリです。
対面での会話やミーティングでの文字起こし・翻訳ができ、会議シーンでの利用に特化しています。
最先端の音声技術により参加者は誰が何を話したのかを的確に聞き取ることが可能で、リアルタイムでの文字起こしにより聴覚に障害がある人も取り残されることなく会話に参加できます。
現在のところiOSのみの対応ですが、携帯端末の中でもっとも利用者が多いiPhone同士ならやりとりもスムーズにできるでしょう。
公式サイト:Group Transcribe(Microsoft)
筆談アプリ「筆談サポート」
筆談サポートは、聴覚障害者と健聴者の筆談をサポートするアプリです。
通常の筆談に「音声入力」「キーボード入力」を加えることで負担を軽減できるほか、文字サイズの調整やテキストを上下反転させて表示することもできます。
基本的に無料ですが、現在のところiPad対応(iOS)のみです。
緊急連絡アプリ「電話お願い手帳」
電話お願い手帳は、外出先で用件や連絡先などを書いて周辺の人に協力をお願いする際に使用するコミュニケーションツールです。
NTT西日本が1983年より発行していた冊子版が、インターネットに接続できる携帯端末(スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォンなど)の普及によりWEB版とアプリ版を提供を始めました。
インターネットに接続できない場面でも利用が可能なため、災害時などに重宝します。
難聴の人とのコミュニケーション手段まとめ
難聴・中途失聴者や聴覚障害者にとって、もっとも困難なことはコミュニケーションです。
軽度の難聴レベルであれば口話だけでやりとりが可能ですが、重度の難聴レベルになってくると場合によっては文字を使ったやりとりが必要になってきます。
ろう者の場合は手話が中心になってきますが、口話が基本である健聴者に手話を扱える人は多くありません。
聴力の程度だけでなく、周囲の音や口元が見える明るさなど環境や条件によっても変わってきます。
難聴・失聴者や聴覚障害者それぞれに対応できる手段を知って、補助するツールやアイテムをうまく活用してコミュニケーションをとれたらいいですね。


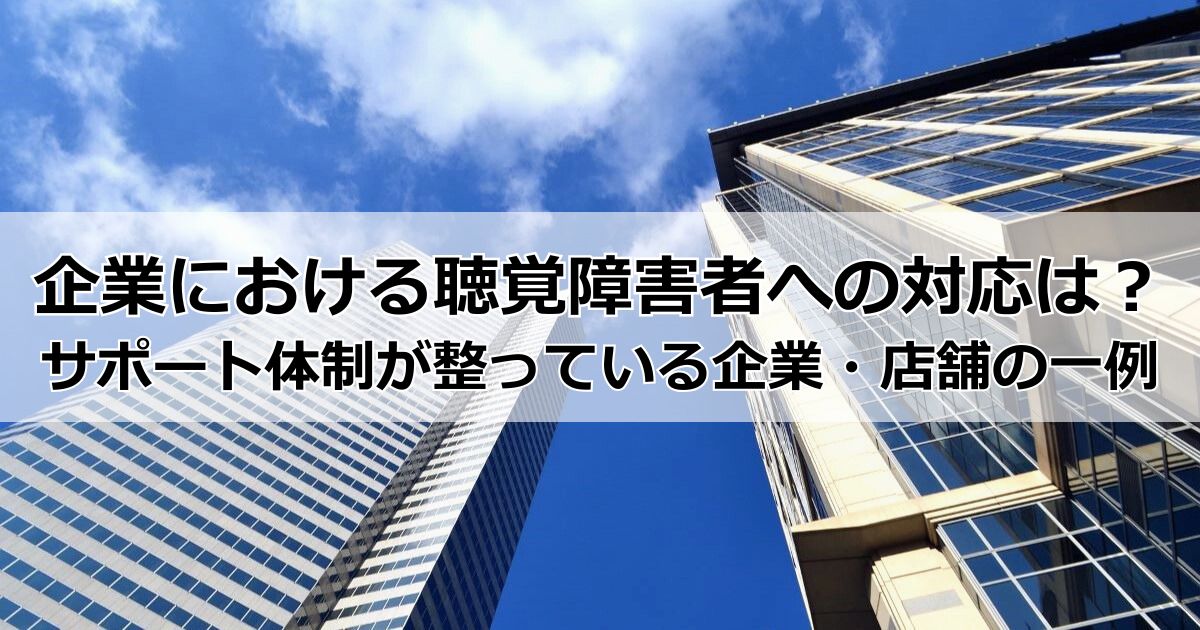
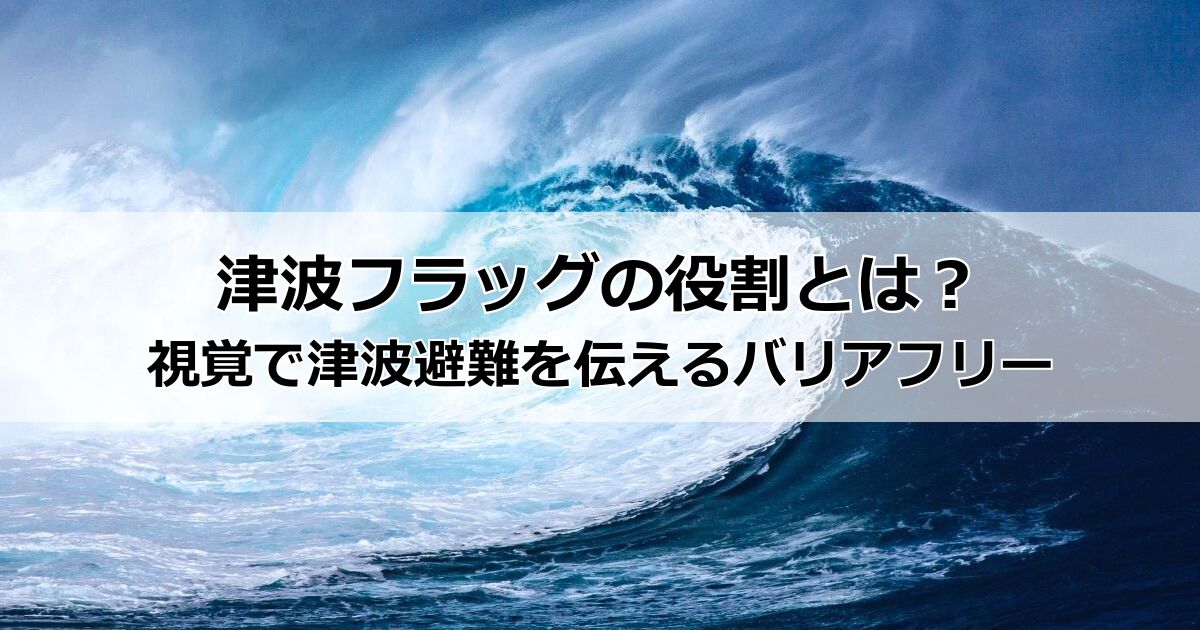

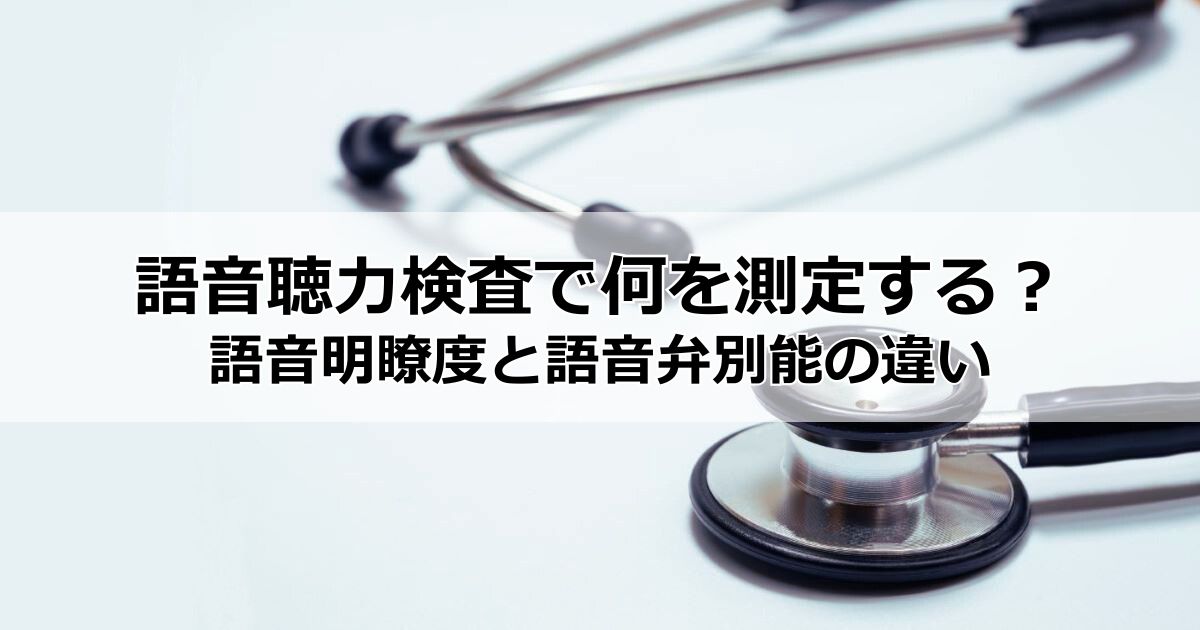
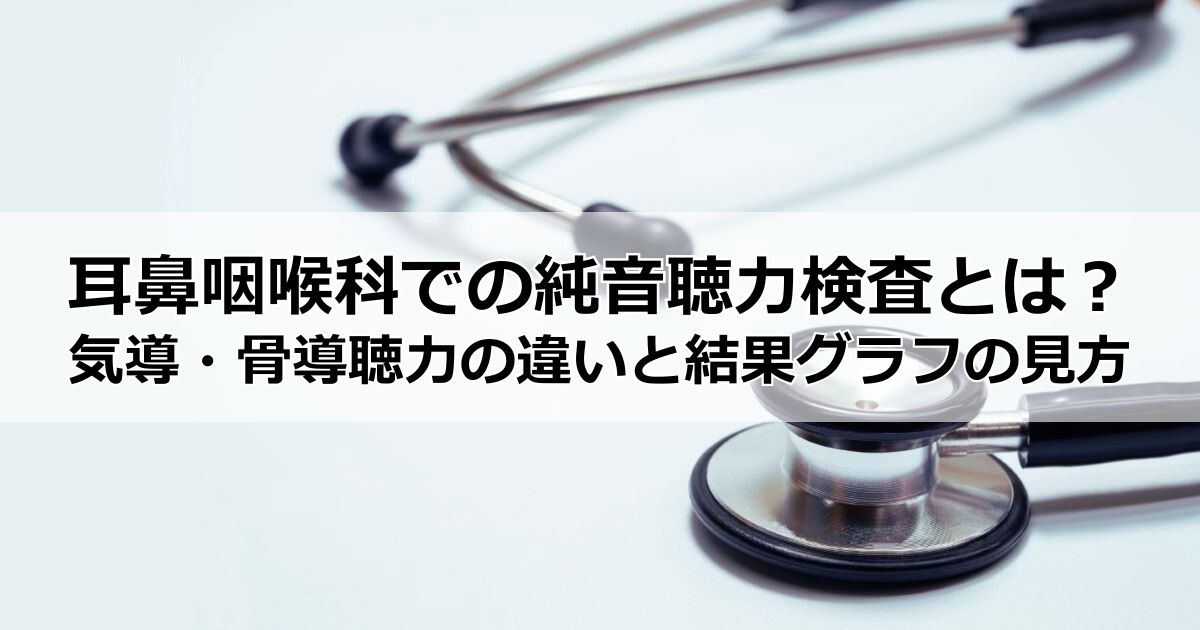
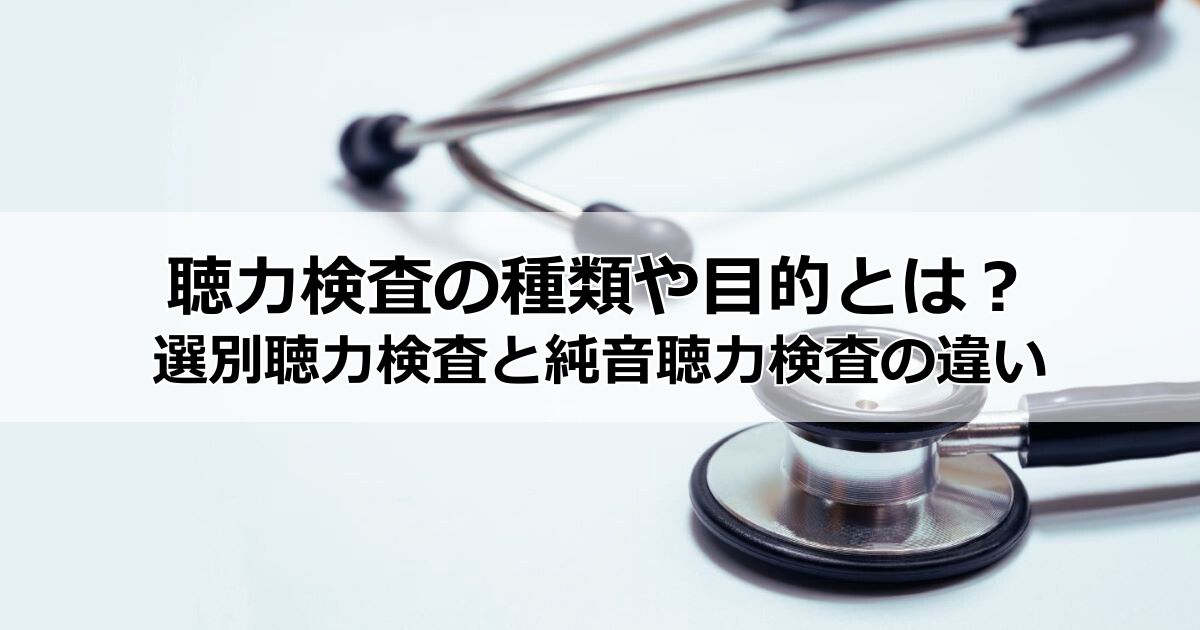
コメント