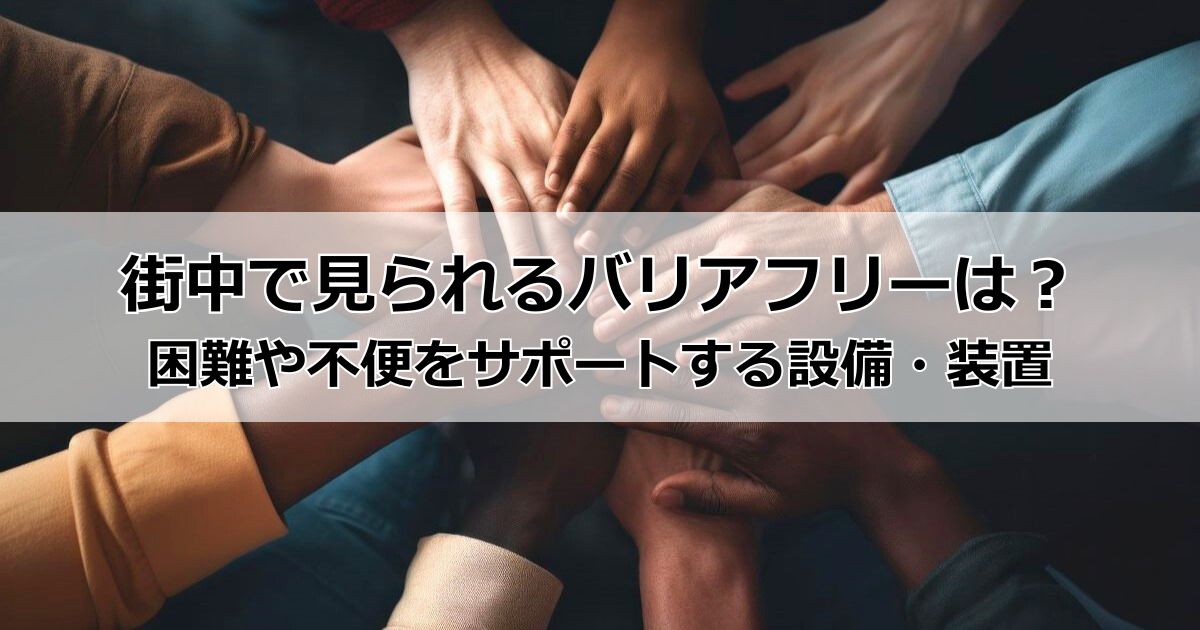
駅や交通機関、商業施設など、街中を見渡せばバリアフリーにあふれているのをご存知でしょうか。
バリアフリーとは、年齢や性別、環境など異なるさまざまな人の障壁(バリア)を取り除くことです。
障害をもつ人をはじめ高齢者や妊娠中の人など、生活する上で困難や不便に感じていることを解消する設備や装置が街中の至るところにあります。
この記事では、交通機関や建物など街中で見られる身近なバリアフリーの例を紹介します。
あらゆるバリアフリー設備や装置にはどんな目的や機能があるのか、1人ひとりが多様な人の立場や身になって考える機会になれば幸いです。
バリアフリーとは
バリアフリーは、年齢や性別、環境などが異なる多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすことです。
もともとは建築用語として建物や道路の段差などを除去する意味で使われていました。
近年では障害のある人をはじめ、さまざまな境遇の人たちの社会参加を困難にしているすべての分野においてバリア(障壁)を取り除く意味で用いられています。
バリアフリーの意味や種類については、下記記事をご参考ください。
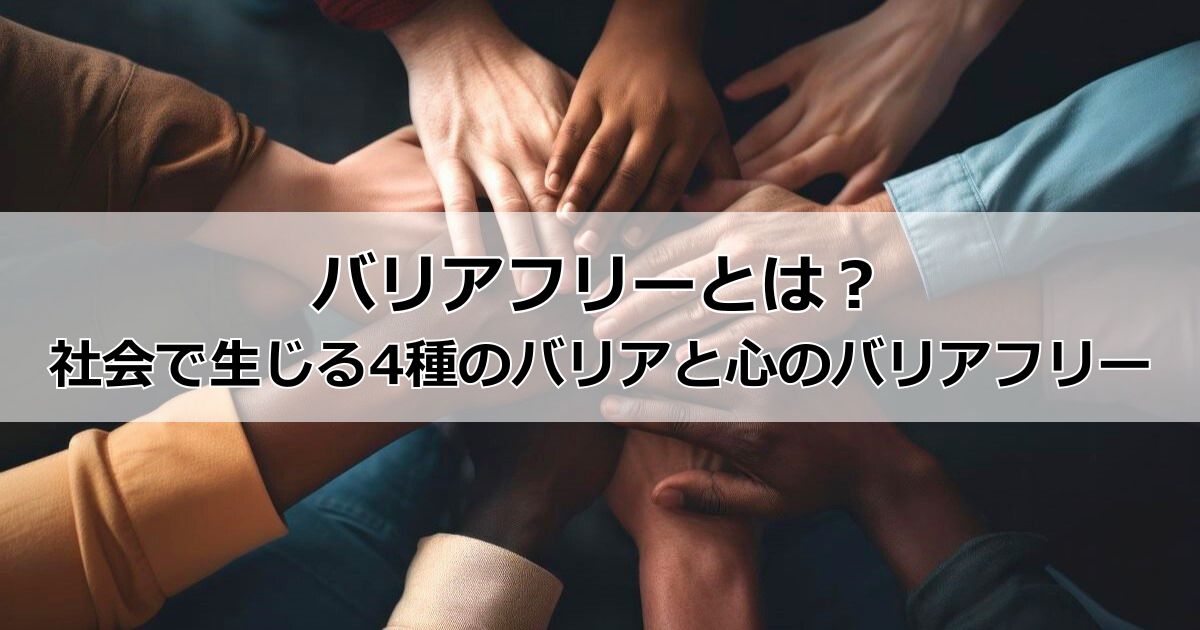
街中で見られる身近なバリアフリー
障害のある人や高齢者など社会で参加する上で生じるバリア(障壁)をなくすために、私たちの周りではさまざまな取り組みが進められています。
まずは、街中で見られる身近なバリアフリーを一部紹介します。
スロープ

スロープは、階段や段差を上り下りするために設置される傾斜路いわゆる坂道です。
駅前や建物の前など段差の大きい場所に多く見られ、車いすの人や杖を利用している人などもスロープがあれば上下の移動がしやすくなります。
また視覚に障害がある人にとっても、段差につまずくことなく移動がスムーズです。
エレベーター

エレベーターは、階数のある建築物や駅などバリアフリー化が義務づけられている建築物特定施設の1つです。
車いすの人や視覚に障害がある人が利用しやすいようにボタンの位置を低くしたり、方向を変えずに出入り口を確認できる鏡をつけたりするなどの工夫がされています。
またエレベーターと建物のすき間を狭くすることで、車いすやストレッチャーなどの車輪脱落事故を防止し乗り降りの安全性を高めています。
エスカレーター

エスカレーターも階数のある建築物や駅など、バリアフリー化が義務づけられている建築物特定施設の1つです。
運転方向を知らせるために上り(下り)を知らせる音声を流したり、床用の案内標識を設置したりすることで障害のある利用者に必要な情報を表示しています。
近年では乗り降りする箇所のコムを従来の黒から黄色に変更することで視認性を高めたり、乗り口と降り口で水平となる踏段(ステップ)の枚数をこれまでの1.5枚程度から3枚に増やしたりして乗降時の不安を軽減する工夫がされています、
また3枚のステップが同一平面上に並べて大きな1段にすることで車いすが乗せられる車いす対応エスカレーターもあります。
バリアフリートイレ(多目的トイレ)

バリアフリートイレは、車いすを使っている人や身体内部に障害がある人、赤ちゃんを連れた人などが利用しやすい機能がつけられた多目的トイレです。
車いす使用者が使いやすい2メートル四方の広いスペース、手すりやオストメイト(人工肛門・人工ぼうこう保有者)用汚物流し台、乳幼児用のおむつ交換台などが設けられたトイレなどを総称して呼ばれます。
誘導用ブロック(点状・線状ブロック)


誘導用ブロックは、視覚に障害のある人が安全に移動できるよう道路や通路に設置されているもので点状ブロックと線状ブロックの2種類があります。
点状ブロックは、一時停止や注意を促すのが目的で点状の突起を5列以上設置しています。
線状ブロックは、道筋を示すのが目的で誘導する方向と平行に線状の突起を4列以上設置します。
駅のホーム端に設置されている点状ブロックには、ホームの内側と外側が区別できるように点状に加えて1本線(内方線)の突起がホーム内側についています。
音響式信号機

音響式信号機は、視覚に障害がある人や視力が低下している高齢者に歩行者信号が青であることを知らせるための音声案内です。
音声は、メロディ式(通りゃんせ、故郷の人々など)と擬音式(カッコー、ピヨピヨ)の2種類が使われています。
交通量が多い・少ない道路、幅の広い・狭い道路など地域や道路環境によっても異なる音を使い分ける信号機もあるようです。
また通常の歩行者用押しボタン箱は黄色ですが、横断に時間がかかる人のために歩行者用信号機の青信号が通常より長くなる白色押しボタン箱を設置した高齢者等感応式信号機もあります。
身障者用駐車場


駐車場は、バリアフリー化が義務づけられている建築物が駐車場を設ける場合に車いすの人のための駐車場を1枠以上設けなければならないことになっています。
1枠の幅は350cm以上とし、利用する施設の入り口にできるだけ近い場所に設置します。
駐車場は、身障者用駐車場、思いやり駐車場などさまざまな名称があります。
身障者用駐車場は、障害のある人や高齢者、妊娠中の人、ケガをした人など歩行が困難な人が利用できる駐車スペースです。
思いやり駐車場は、身障者用駐車場とは別に乗降に広いスペースを必要とする高齢者、障害者、妊娠中の人、ベビーカー使用者などのための優先駐車場です。
駐車場で見られる車いすマークは障害者のための国際シンボルマークで、車いす専用の駐車場という意味ではなく障害をもつ人が利用できます。
障害者に関するシンボルマークについては、下記記事をご参考ください。

駅や公共交通機関で見られるバリアフリー
駅や空港など各種公共交通機関で見られるバリアフリーの例を紹介します。
駅のホームドア

駅のホームドアは、ホームと電車の間に設置される安全設備です。
駅ホームの端にドアを設置して線路への転落や電車との接触を防ぐことが主な目的で、電車の乗降口に合わせてホームドアが開閉し乗客が安全に乗り降りできる仕組みになっています。
1973年(昭和48年)に全盲の上野孝司氏が、東京・高田馬場駅ホームから転落し電車とホームに挟まれて亡くなる事件が起こりました。
事故の責任を問う裁判がきっかけで点字ブロックや転落防止ガード、警告装置の設置が普及しました。
この裁判は視覚障害者の間でよく知られている「上野訴訟」と呼ばれる死傷事故です。
近年ではホームドアを設置する駅も増えていますが、国土交通省の資料によると2023年度(令和5年度)時点では9649駅のうち1129駅が設置済みとなっています。
2025年度(令和7年度)までの整備目標を3000番線としており、2023年度(令和5年度)時点で2647番線が整備済みです。
情報表示装置・案内表示

聴覚に障害がある人は、公共交通機関を利用する時に駅や空港内の案内放送、電車の発車ベルや車内放送などが聞こえず困ることがあります。
近年では駅や電車内には電光掲示板や点灯ランプが設置され、視覚的に判断できるような表示機器が増えてきました。
情報表示装置は電車の発車時刻や行き先、ホーム番号のほか電車がホームに入ってくる時や遅延する時などのお知らせを表示する装置で改札口付近やホームに設置されています。
案内表示は電車やバス内のドア付近に設置されており、次の停車駅や行き先、遅延の状況などが表示されます。
筆者はこの文字による案内表示に助けられていますが、電車の運転見合わせの時は運転再開見込みなどの情報が得られないため鉄道会社の公式サイトやSNSでの情報に頼っています。
案内サイン

案内サインは、駅構内や公共交通に設置されている場所を案内するボードです。
視覚に障害のある人や文字がわからない人にも伝わりやすいように、エスカレーター・エレベーター・階段などの文字と併せて図記号(ピクトグラム)が用いられています。
駅や公共交通機関だけでなく、商業施設の中や道路など街中でも目にすることも多いです。
他にお手洗いや非常口も図記号を用いて遠くから見えることもあり、普通の人にとっても助かる面がありますね。
案内サインは、大きく3種類に分けられています。
| 指示サイン | 施設などの方向を示すもの(例:トイレの図記号+矢印) |
| 同定サイン | 施設などの位置を示すもの(例:〇〇改札口、△番出口など) |
| 図解サイン | 現在地や施設の位置関係などを図で示すもの(例:駅構内にあるマップ、周辺エリアマップなど) |
優先席・車いすスペース

優先席は、電車やバスなどで障害のある人や高齢者、妊娠中の人、子ども連れの人などが優先的に利用できるように設置された座席です。
一般の座席とは異なる配色・柄が用いられており、つり革や通路、壁面などの色を変えて優先エリアをより明確に示している車両もあります。
車いすスペースは、車いすの人が車いすのまま電車やバスを利用できるように広いスペース(幅75cm以上・長さ130cm以上)が確保されている場所です。
車いすの人だけでなくベビーカーで子どもを連れている人もベビーカーを折りたたまずに利用できるように、車いすマークと合わせてベビーカーマークも表示されています。
車いすマークは、障害者のための国際シンボルマークです。
障害者に関するシンボルマークについては、下記記事をご参考ください。

階段昇降機(階段移動用リフト)

階段昇降機は、主に足が不自由で階段の昇り降りが困難な車いすの人のために設備された可搬型の階段移動用リフトです。
駅構内や学校などの公共施設で多く見られ、階段に昇降機が走行するためのガイドレールと車いすや人を乗せるトレイを設置するため建物自体への設置工事が必要ありません。
階段の昇り降りで心臓に負担がかかる人も安全に利用できるのも特徴です。
ベビー休憩室

最近見かけるのが、駅構内のベビー休憩室です。
ボックスの壁面に描かれている絵が哺乳瓶だったため授乳室だと思ったのですが、おむつ替えベッドもあるためおむつ交換もできます。
個室型になっているため、コンセントが使えるほか一部では調乳用のお湯が使えたり寝かしつけができたりします。
改札内・改札外でベビー休憩室の有無が分かれますので、事前に確認することをおすすめします。
公共施設や商業施設などの建物で見られるバリアフリー
役所や病院といった公共施設、ショッピングモールやジムといった民間・商業施設などの建物でもバリアフリーが施されています。
前述で紹介したエレベーター・エスカレーター・駐車場など街中の身近なバリアフリー以外に見られるバリアフリーの例を紹介します。
手すり付き組上げスロープ

手すり付き組上げスロープは、前述で紹介したスロープに手すりがついた傾斜路です。
学校や公共施設に多く見られ、車いすの人はもちろん足の不自由な人や高齢者など転倒防止に手すりが取りつけられています。
また利用者がいない時間に合わせて、台車を要する大きな荷物の運搬にも役立ちます。
耳マーク

病院や役所、ショッピングモールなど一部の民間・商業施設では、入口近くの総合案内カウンターやインフォメーションセンターに耳マークのスタンドが設置されています。
聴覚障害のある人から申し出があれば援助を行うという意思表示を示しているため、手話もしくは筆談で対応できるという意味です。
デジタルサイネージ

高層ビルの屋上や壁面、商業施設の館内ではデジタルサイネージを取り入れることも増えてきました。
館内の場所案内やテナント店舗の宣伝だけでなく災害など緊急時には文字による情報掲示板としても活用されているため、聴覚に障害がある人にとっても適切な判断がしやすくなっています。
移動式プールリフト
移動式プールリフトは、スポーツセンターやジムのプールで下肢に障害のある人でも安全に入出水できる装置です。
主にパラスポーツや障害者スポーツ教室を行う施設に見られ、多目的フロアやスロープが同時に設置されています。
他にもあるバリアフリー設備

上記は一例であり、他にも駅構内や自動券売機・精算機で音声・音響案内をしているところは視覚障害のある人に向けたバリアフリーです。
また階段の手すりやエレベーターの押しボタンなどに点字表記が備えてあるのも視覚障害のある人に配慮しています。
近年ではエレベーター内の扉上部に液晶モニターを設置する施設も増えていますが、聴覚障害のある人にとっても視覚情報のサポートになっているわけです。
駅や空港、劇場などあらゆる施設にAEDという自動体外式除細器が設置されているのを見たことがある人も多いでしょう。
AEDは、突然の心停止を起こして倒れた人の命を救うことができる医療機器です。
けいれん状態の心臓は伸収縮できなくなるため、心臓から血液を送り出すことができなくなります。
そのまま何もしないと時間の経過とともに生存率がどんどん下がってしまうため、そうなる前に電気ショックを与えることで正常なリズムに戻す役割があります。
他にもさまざまなバリアフリーがありますので、街中や公共交通機関、民間施設などを利用する際に意識を傾けてみてください。
バリアフリーに関するシンボルマークやサイン
配慮を必要とする人を支援するために、バリアフリーに関するさまざまなシンボルマークやサインがあらゆる場所で使われています。
それぞれのサインやシンボルマークの意味を理解して、心のバリアフリーを広げましょう。
 障害者のための国際シンボルマーク | 車いすの人に限らず、障害のある全ての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マーク |
 盲人のための国際シンボルマーク | 目の不自由な人のバリアフリーを考慮した世界共通マーク |
 耳マーク | 聴覚に障害のある人のための国内で使用されているマーク |
 ほじょ犬マーク | 身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマーク |
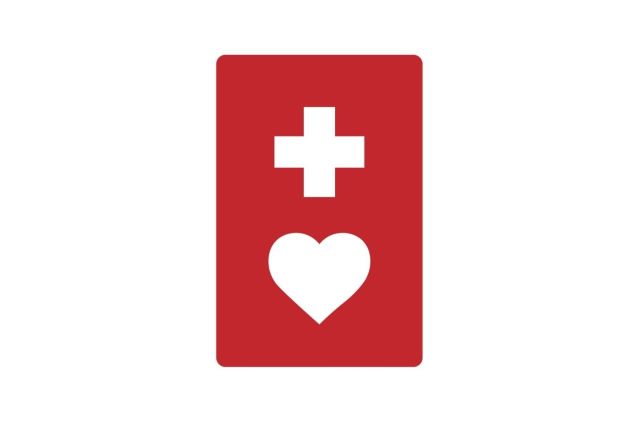 ヘルプマーク | 外見からわからない障害や難病、妊娠初期の方のために作られたマーク |
 ベビーカーマーク | ベビーカーを利用しやすい環境を整備するためにつくられたマーク |
 マタニティマーク | 妊婦している人が交通機関などを利用する際に身につけるマーク |
このようにバリアフリーに関するシンボルマークやサインは、障害者のためだけではありません。
ベビーカーマークは、ベビーカーを折りたたまずに利用できるなどベビーカーを安心して利用できる場所や設備を表しています。
マタニティマークは、とくに妊娠初期の人は外見からわかりにくい傾向があるため周囲に妊婦であることを示しやすくするために作られました。
障害者に関するシンボルマークや標識については、下記記事をご参考ください。

街中にあふれるバリアフリーまとめ
バリアフリーは、障害をもつ人のためにあるわけではありません。
高齢の人や妊娠中の人、ベビーカーで子どもを引き連れている人も含め、どんな立場の人でも安心して社会に参加する上でバリアフリーが必要です。
駅や公共交通機関、商業施設など街中で見られるバリアフリーを目にして、どんな意味がありどういった目的や助けになるのか意識を傾けてみてください。
そして、街中のあらゆる場所で困っている人を見かけたら。
あなたにできる心のバリアフリーで、その手を差し伸べてあげてください。
以下の記事では、社会に参加する上で生じる4種類のバリアと心のバリアフリーの重要性について解説していますので併せてお読みください。
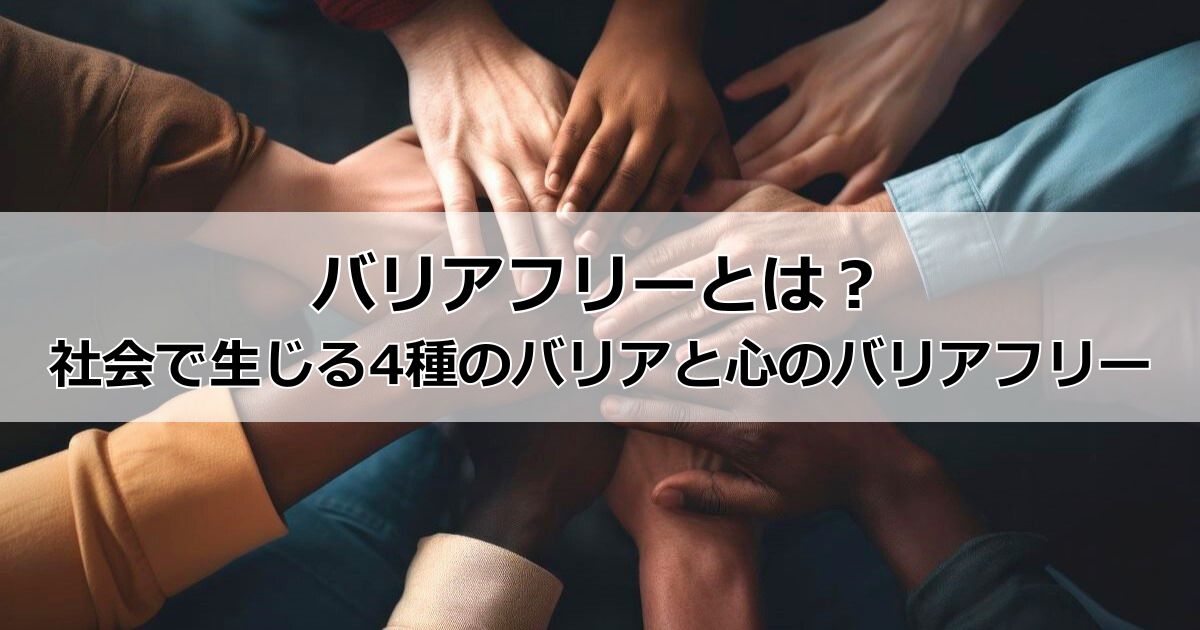




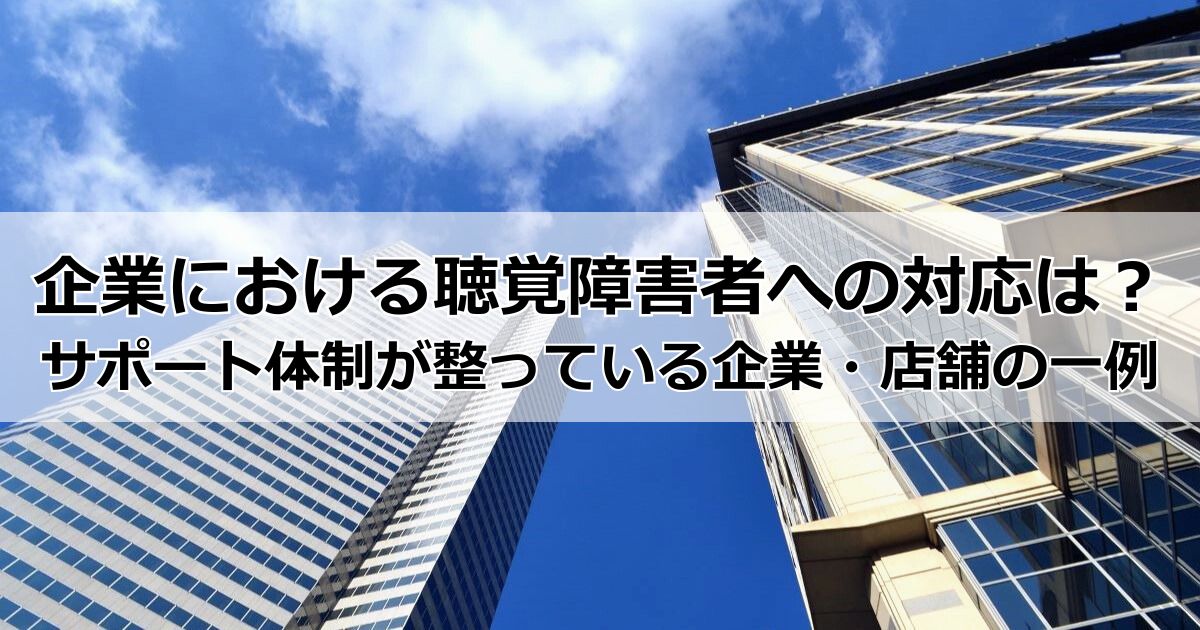
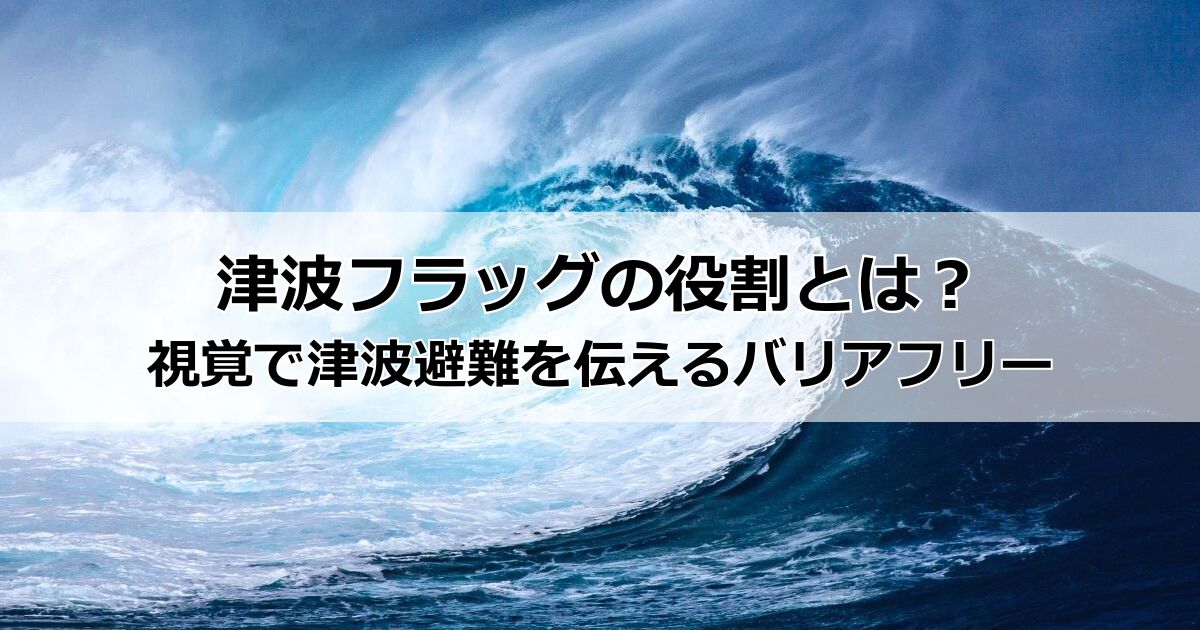
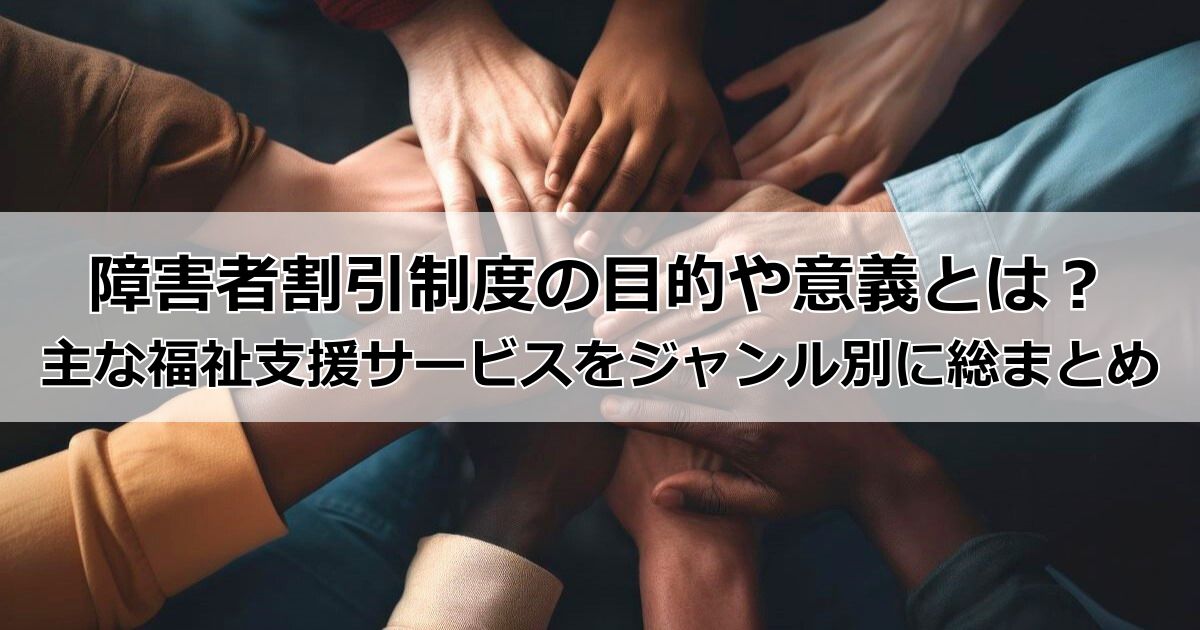

コメント