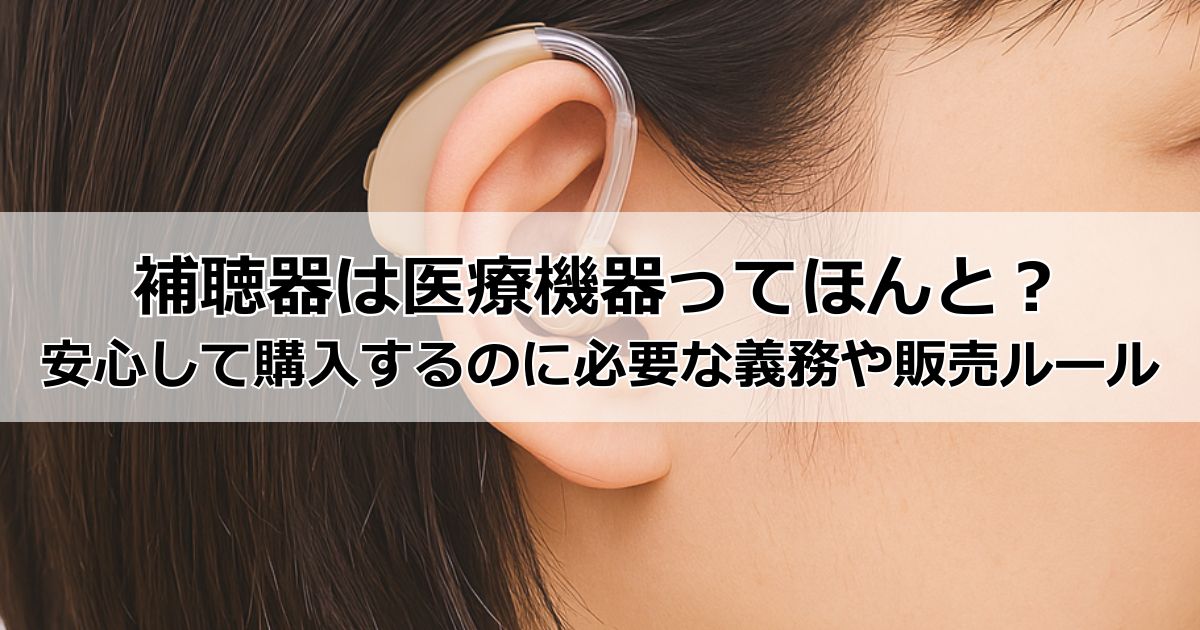
難聴や聴力が低下した人や聴覚障害者の聴こえを補う、補聴器。
補聴器は音を増幅する機能があるとはいっても集音器と同じ音響機器でも家電製品でもなく、実は医療機器であることをご存知でしょうか。
医療機器の中でも人体への影響が比較的低い管理医療機器に属しており、効果や安全性が求められているのが補聴器です。
この記事では、医療機器として扱われる補聴器の位置づけについて紹介します。
また管理医療機器として求められる補聴器の販売ルールを解説しますので、補聴器を安心して購入できるためのご参考になれば幸いです。
補聴器は医療機器
補聴器は、聴こえを補うために薬機法(旧・薬事法)で定められた医療機器です。
似た形状をもつ集音器と同じ音響機器でも家電製品でもありません。
医療機器とは
医療機器は、薬機法第2条により以下の通り定義されています。
「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいう。」
簡潔にすると、以下の3つです。
(1)人間か動物に用いられるものに限られる
(2)疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされている機械器具など
(3)身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具など
医療機器のリスク分類
医療機器には4000以上におよぶ種類がありますが、人体に与えるリスクや影響に応じてクラスⅠからⅣまでの4つに分類され、製造や販売などにおいてはリスクに応じた規制が行われます。
補聴器は、人体へのリスクが比較的低い管理医療機器(クラスⅡ)に属しています。
医療機器の不具合などによる副作用・機能障害といった人の生命・健康に対するリスクの大きさを示す4つのリスク分類については、以下の表を参考にしてください。
| クラス分類 (種別) | 定義 | 主な対象例 | 許可・届出 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| クラスⅠ (一般医療機器) | 人体へのリスクが極めて低いもの | 救急絆創膏、水銀体温計、医療用ピンセットなど | 不要 | 不要 |
| クラスⅡ (管理医療機器) | 人体へのリスクが比較的低いもの | 補聴器、電子血圧計、MRI・X線撮影装置など | 届出 | 不要 |
| クラスⅢ (高度管理医療機器) | 人体へのリスクが比較的高いもの | コンタクトレンズ、輸液ポンプ、人工股関節など | 許可 | 必要 |
| クラスⅣ (高度管理医療機器) | 生命の危険に直結する恐れがあるもの | ペースメーカー、人工呼吸器など | 許可 | 必要 |
| 特定保守管理医療機器 | 保守点検に専門的な知識や技能を必要とする | 脳波計、呼吸モニタ、麻酔システムなど | 許可 | 必要 |
補聴器は2番目の管理医療機器
2005年(平成17年)4月1日に改正された薬機法により、補聴器は医療機器の中でも管理医療機器(クラスⅡ)として分類が変更されました。
管理医療機器とは、薬機法第2条第6項で「副作用又は機能の障害が生じた場合に人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの」と定められています。
管理医療機器である補聴器を販売する場合は、営業所の届出・許可をはじめ厚生労働省令で定める基準に該当する管理者の設置が必要です。
効果や有効性・安全性で一定の基準をクリアし、正式な認定を受けなければ補聴器として販売できないことになっています。
補聴器は購入したら終わりではなく、使う人の聴力に応じて調整・メンテナンスを必要とするため安心して使用することが可能です。
補聴器の販売におけるルール
補聴器は医療機器でもあることから、販売においてさまざまなルールがあります。
補聴器を販売するための資格
前述の通り、補聴器は管理医療機器の販売業・貸与業の届出と営業所管理者(販売営業所管理者講習会の受講者)の設置が必要です。
届出は各都道府県に講習会への受講条件があるため、公益財団法人医療機器センターのWebサイトを参考にしてください。
また管理医療機器である補聴器は、専門知識をもった人がフィッティングや修理をすることが望まれています。
そのために公益財団法人テクノエイド協会の主催で、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会や日本聴覚医学会が後援する認定補聴器技能者養成事業を作って、補聴器の専門家である「認定補聴器技能者」の育成を図っています。
認定補聴器技能者とは
認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が行う認定補聴器技能者試験に合格した人です。
補聴器の販売や調整などに携わる人に対し、公益財団法人テクノエイド協会が厳しい条件のもと、基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する資格です。
認定補聴器技能者は、2024年12月現在で4,835人が登録されており公共財団法人テクノエイド協会が認定しています。
認定補聴器技能者が対応できる内容は、以下の通りです。
- 補聴器を1人ひとりの聴力状態に合わせて調整し、より快適な聴こえを追求する
- テレビや電話、会話が聞きづらい時の相談
- 難聴や聴力低下に悩む人の聴こえや補聴器購入に関する相談
- 公的支援のアドバイスや情報提供
- 耳鼻科医師と連携した対応
以下の記事では、認定補聴器技能者の役割や資格など具体的に紹介していますので併せてお読みください。
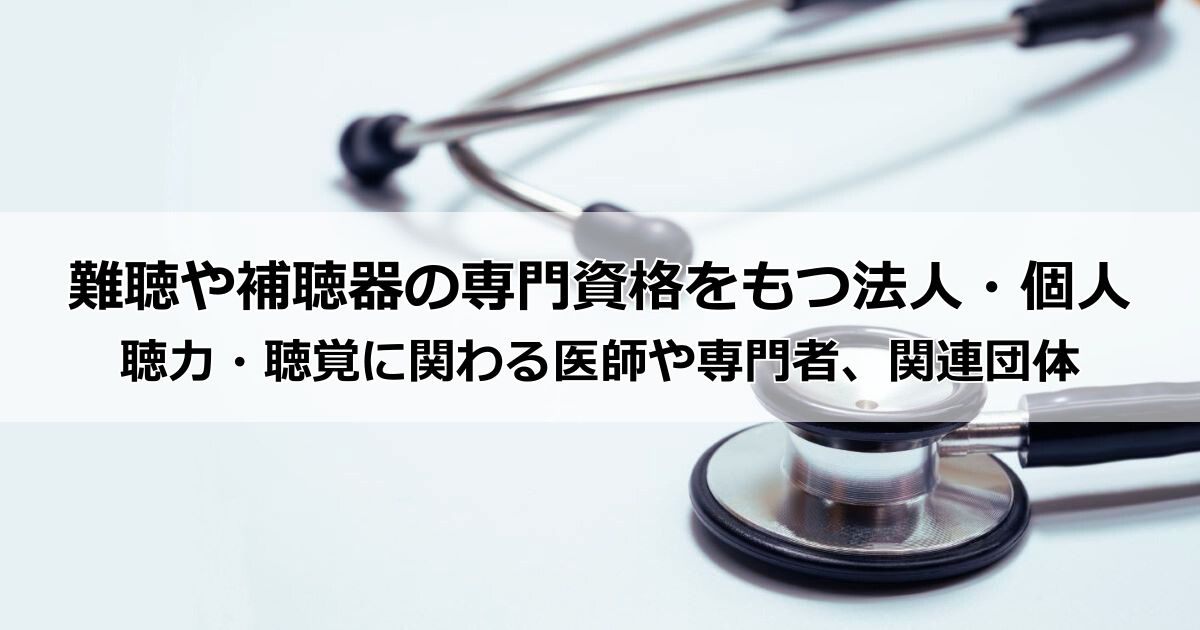
認定補聴器技能者の在籍場所
認定補聴器技能者は、基本的に認定補聴器専門店に在籍していることが多いです。
補聴器は一般的に、補聴器販売店や街中にあるメガネ店、通販などで購入することができ、どの店舗でも補聴器を販売している店であれば一定水準以上の知識をもった従業員が在籍しています。
しかし、全ての補聴器販売店に認定補聴器技能者が在籍しているわけではありません。
補聴器販売店は全国で約8000店舗もあり、その中で認定補聴器技能者が在籍している店を探すのは大変です。
認定補聴器技能者は、実は「認定補聴器専門店」を探すと見つかります。
認定補聴器専門店とは
前述の通り、認定補聴器技能者は認定補聴器専門店に必ず在籍しています。
その理由は、認定補聴器専門店は認定補聴器技能者の在籍を義務づけられているためです。
認定補聴器専門店として認可されるには、認定補聴器技能者の指導のもと補聴器の調整や相談などが行われている必要があります。
また他にも、認定補聴器専門店の認可にはいくつかの審査基準を満たさなければなりません。
審査基準の1つとして、補聴器の購入を希望する人の難聴の症状、使用目的、使用環境などに対応できる各種の機種を揃えておく必要があります。
そのため、認定補聴器専門店には各メーカーのさまざまな補聴器を置いてあります。
特定のメーカー店舗では同メーカーの補聴器しか置いていませんが、基本的にはタイプや機能・仕様の異なる補聴器が置いているため、認定補聴器専門店であれば使う人に合った1台を見つける可能性が高くなります。
そのため、補聴器を安心して購入するためには認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店を探せばいいのです。
以下の記事では、認定補聴器専門店の資格や販売基準、全国の店舗など具体的に紹介していますので併せてお読みください。
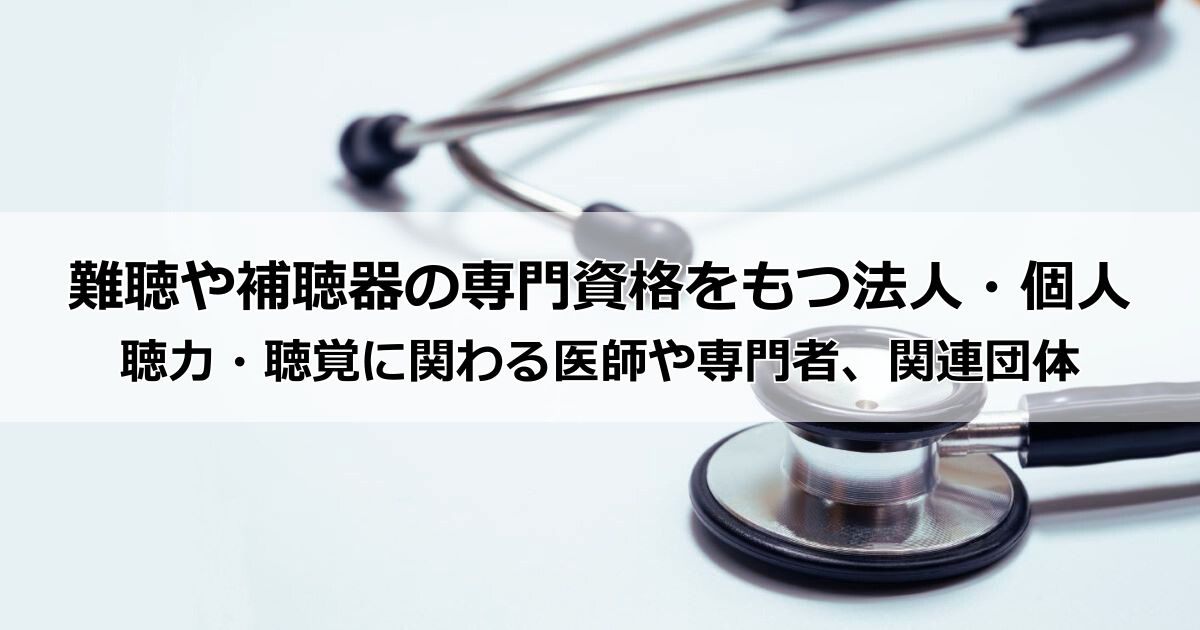
補聴器を安心して購入するために
補聴器は、有効性・安全性を保証できる医療機器であり厳格な基準を設けて販売されています。
補聴器を購入する時は、前述の通り認定補聴器技能者が常駐する認定補聴器専門店を利用するのがおすすめです。
まずは補聴器相談医の診察を
ただし認定補聴器専門店へ行く前に、補聴器相談医の診察を受けることがより安心して購入できます。
難聴や聴力の低下を感じても、補聴器の装用が適しているとは限らないためです。
補聴器の購入は自分の判断だけではなく、まずは症状や原因を診察してもらうことが重要になります。
補聴器相談医は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より認定された専門医です。
決められた講習と実習を履修することが前提で、6年ごとに資格を更新する必要があります。
補聴器相談医は、聞こえが不自由な人に対して耳の状態を診察したり聴力検査を行ったりすることで難聴の種類や症状を判断し、治せる症状には治療を行います。
その中で補聴器の装用が適していると判断した場合には、日常生活において聞こえの向上が実感できるようサポートします。
そのため認定補聴器専門店へ行く前に、まずは補聴器相談医の診察を受けることをおすすめします。
補聴器相談医と耳鼻咽喉科医との違い
補聴器相談医は、耳鼻咽喉科医に含まれますが明確な違いがあります。
耳鼻咽喉科医(耳鼻科医)は、中耳炎や鼻炎、のどの感染症など耳・鼻・喉に関連する幅広い専門知識をもつ医師です。
補聴器相談医は、さらに補聴器を必要とする人に対してより専門的なサポートを提供する役割があります。
難聴や聴力の低下により補聴器の装用が必要なのかを判断するために、補聴器相談医としても認定されている耳鼻咽喉科医に相談しましょう。
補聴器相談医については、下記記事もご参考ください。
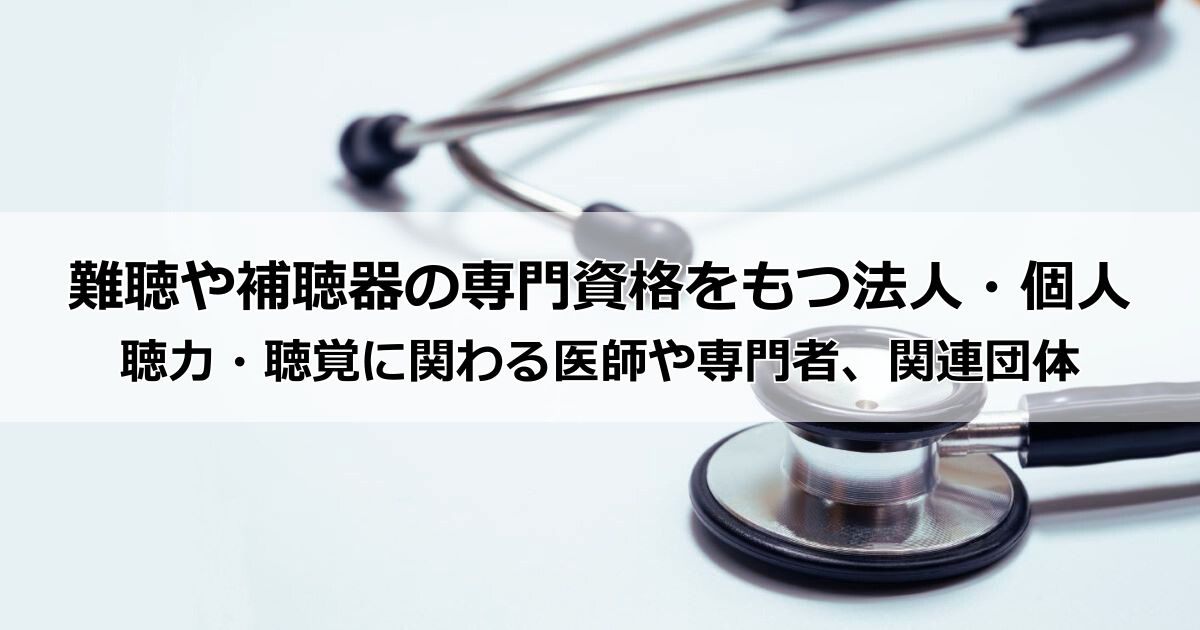
医療機器としての補聴器まとめ
補聴器は、薬機法に定められた医療機器です。
疾病の診断・治療・予防への使用、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とされている機械器具などを指します。
また安全性や有効性を認めた管理医療機器として、販売業・貸与業の届出や営業管理者の設置が必要です。
販売が認められた店舗で専門資格をもった人がフィッティングや修理をすることが望まれています。
耳鼻咽喉科医または補聴器相談医に補聴器の装用が必要と診断された人、補聴器の購入を検討している人へ。
補聴器の購入先は、管理医療機器として販売資格をもった認定補聴器専門店で相談しましょう。
以下の記事では、音響機器として家電量販店や通信販売などで購入できる集音器について補聴器との違いを含め解説していますのでご参考ください。



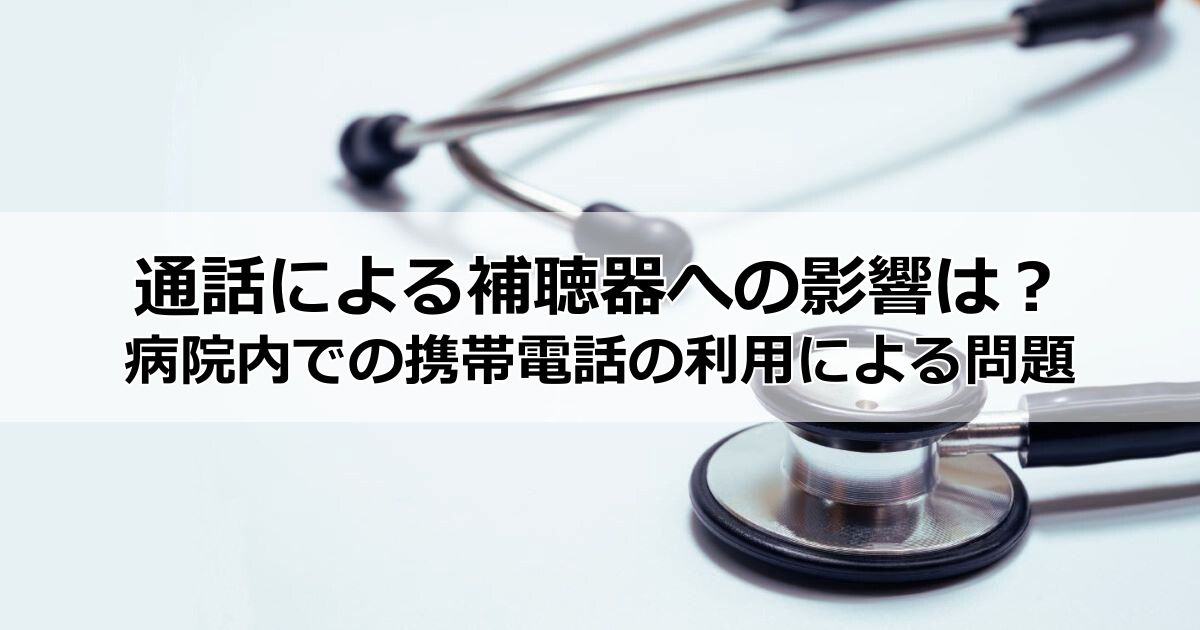

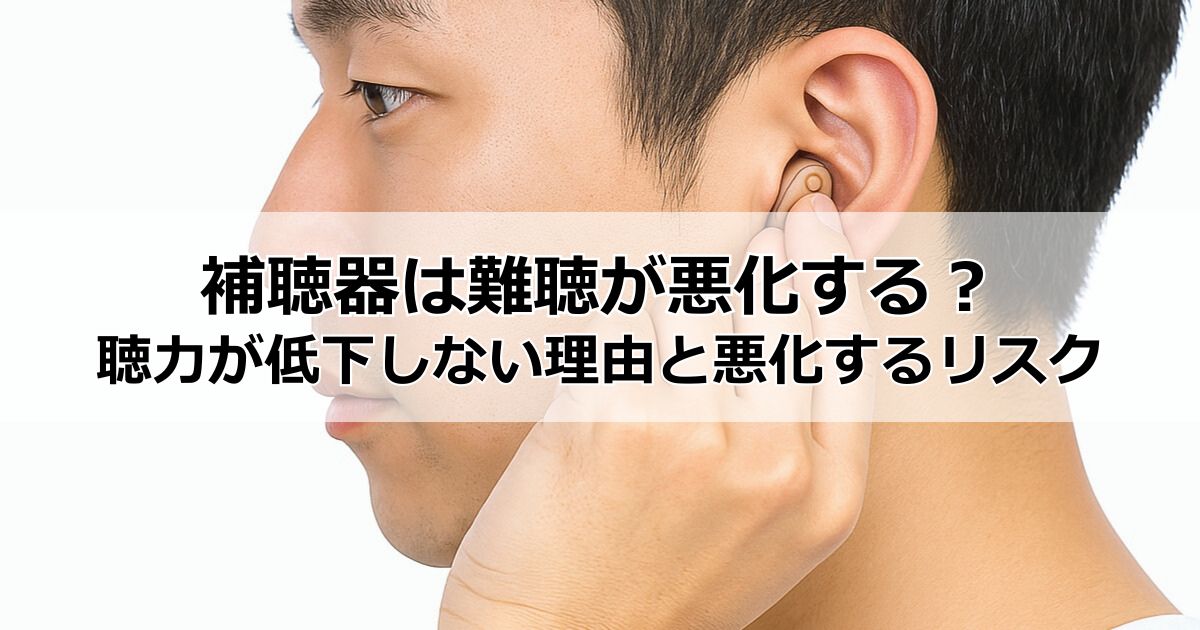


コメント