
国・地方公共団体や民間企業には、従業員数に対して一定割合以上の障害者を雇用する義務があるのをご存知でしょうか。
この法律が障害者雇用促進法であり、障害者を雇用する割合が法定雇用率です。
ではそもそも障害者雇用促進法とは何か、どんな目的で制定されたのか。
もし企業が障害者を採用せずに法定雇用率を満たしていなかったらどうなるのか。
障害者雇用促進法の目的や法定雇用率の意味、引き上げに伴う雇用義務と現在の雇用状況を紹介します。
企業における法定雇用率が未達成だった場合の影響も解説しますので、障害者を雇用する必要のある採用担当者をはじめ障害のある人が平等な雇用の機会を得られる情報としてご参考になれば幸いです。
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法は「障害者の雇用の促進等に関する法律」を正式名称に、企業や国・地方公共団体などに対し一定の割合で障害者の雇用を義務づける法律です。
1960(昭和35)年に制定された「身体障害者雇用促進法」をもとに、その後幾度か改正されて現在の名称になりました。
障害者雇用促進法の概要
| 正式名称 | 障害者の雇用の促進等に関する法律 |
| 制定日 | 1960年(昭和35年) |
| 目的 | 障害者の職業生活における自立を実現できるように平等な雇用の機会を提供すること |
| 対象 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有している人 |
| 公式サイト | 障害者雇用促進法 |
障害者雇用促進法の目的
障害者雇用促進法は、就労が困難な障害者が社会において自立できるように平等な雇用の機会を提供し安定した職業生活を目指すことを目的としています。
民間企業はもちろん全ての事業主に対して障害者雇用を義務づけており、雇用対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有している人です。
障害者雇用促進法では、職業リハビリテーションの推進・障害者に対する差別の禁止・障害者の雇用義務に基づく雇用の促進など障害者が働くことができるようにするための内容が定められています。
雇用対象となる障害者
障害者雇用促進法では、雇用対象となる障害の種類や程度が定められています。
障害者雇用率制度の対象となるのは、以下に該当する人です。
| 身体障害者 | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~6級)を所持している人 |
| 知的障害者 | 都道府県知事が発行する療育手帳(A・B)を所持している人 |
| 精神障害者 | 精神保健福祉法による精神障害者保健福祉手帳(1~3級)を所持している人 |
障害者雇用促進法と法定雇用率
障害者雇用促進法において中心となる方策は「障害者の雇用義務に基づく雇用の促進」で、障害者の雇用義務として法定雇用率を達成することです。
民間企業や国・地方公共団体、都道府県などの教育委員会に対して、一定割合以上の障害者を雇用する義務が法律で定められています。
この障害者を雇用する割合が「法定雇用率」です。
法定雇用率の引き上げ
障害者雇用促進法第43条により、直近で2024年4月に民間企業における法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。
つまり、従業員を40人以上雇用している企業は障害者を1人以上雇用しなければならないという意味です。
現在の法定雇用率
| 事業者区分 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 民間企業 | 2.5% |
| 国・地方公共団体 | 2.8% |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.7% |
また2026年7月には、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることになっています。
つまり、従業員37.5人以上に対して障害者を1人以上雇用しなければならないという意味です。
そのため、障害者雇用枠での求人応募もしやすくなるといえるでしょう。
法定雇用率の引き上げ歴
| 改定年月 | 民間企業 | 国・地方公共団体 | 教育委員会 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 2.3% | 2.6% | 2.5% |
| 2024年4月 | 2.5% | 2.8% | 2.7% |
| 2026年7月 | 2.7% | 3.0% | 2.9% |
日本国内の障害者雇用状況
厚生労働省が発表した「障害者雇用状況の集計結果」によると、2024年12月時点で民間企業に雇用されている障害者の数は67万7,461.5人です。
前年より5.5%増加し、過去最高を記録しています。
障害者雇用状況と雇用率
| 項目 | 民間企業 | 国 | 都道府県 | 市町村 | 教育委員会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雇用障害者数 | 677,461.5人 | 10428.0人 | 11,030.5人 | 37,433.5人 | 17,719.0人 |
| 実雇用率(前年値) | 2.41%(2.33%) | 3.07%(2.92%) | 3.05%(2.96%) | 2.75%(2.63%) | 2.43%(2.34%) |
| 法定雇用率 | 2.5% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
しかし上記表で見ると、民間企業における障害者の実雇用率は2.41%で法定雇用率の2.5%に対して到達していません。
前年に比べると増えているものの、法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%となっています。
民間企業の法定雇用率と障害者の雇用義務
2024年4月に民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられたばかりで、応募から採用まで時間がかかるために未達成の企業が少なくありません。
民間企業における法定雇用率と障害者の雇用義務は、以下の通りです。
| 改定年月 | 民間企業の法定雇用率 | 障害者の雇用義務 |
|---|---|---|
| 2023年4月 | 2.3% | 従業員43.5人に対して障害者1人 |
| 2024年4月 | 2.5% | 従業員40人に対して障害者1人 |
| 2026年7月 | 2.7% | 従業員37.5人に対して障害者1人 |
厚生労働省は、2026年には法定雇用率が2.7%へと段階的に引き上げる方針を発表しています。
なお、国や地方公共団体は法定雇用率が別に設定されており、2026年から3.0%になる予定です。
民間企業に求められる障害者雇用の対応
障害者の雇用義務を表す法定雇用率を達成しているか、障害者雇用状況において民間企業に求められる対応は以下の通りです。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること
- 障害者雇用の促進と継続を図るために障害者雇用推進者を選任するよう努めること
- 障害者を解雇する場合はハローワークに解雇届を届け出ること
2025年時点で従業員が40人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者を何人雇用しているかを報告するために障害者雇用状況報告書をハローワークに提出する義務があります。
障害者雇用状況の報告は、6月1日時点の状況を報告することから通称「ロクイチ報告」とも呼ばれているそうです。
この報告により、法定雇用率が未達成の企業には行政指導や罰則が行われます。
障害者を雇用する際のルールについては、厚生労働省サイトを参考にしてください。
法定雇用率が未達成だった場合
前述の通り、民間企業が障害者を雇用推進することは法的義務であることが定められています。
では、法定雇用率が未達成だった場合はどうなるのでしょうか。
民間企業の障害者雇用において法定雇用率が達成できていない場合の取り扱いは、大きく分けて以下の2つです。
- 障害者雇用納付金の徴収
- ハローワークからの行政指導
障害者雇用納付金の徴収
従業員数が100人を超える企業が法定雇用率を達成できていない場合は、障害者雇用納付金が徴収されます。
障害者雇用納付金とは、障害のある人を雇用する際の経済的負担などを公平にするために、法定雇用率の未達成企業から納付金を徴収することで多くの障害者を雇用している企業へ助成する制度です。
障害者雇用納付金は不足している障害者1人につき月額50,000円で、法定雇用率を満たすまで払い続ける必要があります。
また徴収された納付金を財源に、法定雇用率を超過達成している企業には超過する障害者数に応じて1人につき月額29,000円の調整金および報奨金が支給されます。
法定雇用率の未達成・達成している企業への対応
| 法定雇用率が未達成の企業 | 達成・超過達成している企業 |
|---|---|
| 納付金が徴収される | 調整金および報奨金が支給される |
筆者が勤務する会社でも法定雇用率に対して雇用する義務のある障害者が3人不足していることが発覚し、数年前から月5万円+3人分(月15万円)を支払っているそうです。
ハローワークによる行政指導
法定雇用率を達成できていない企業は、ハローワークから雇用率達成指導という名の行政指導が行われます。
障害者雇用率達成指導の流れ
毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告により、実雇用率の低い事業主に対して以下4段階の障害者雇用率達成指導が行われます。
- (1)障害者雇入れ計画作成命令
- (2)障害者雇入れ計画の適正実施勧告
- (3)特別指導
- (4)企業名の公表
具体的にはまずハローワークから雇入れ計画作成の命令があり、その計画の状況が思わしくない場合にはさらに指導が入ります。
それでも法定雇用率を達成できない場合には、特別指導や企業名の公表が行われることもあるのです。
(1)障害者雇入れ計画作成命令
翌年の1月から2年間で障害者を雇用するための計画を作成して提出するように、公共職業安定所(ハローワーク)の所長が命令を発出します。
この計画に基づいてハローワークから定期的に指導が行われます。
なお障害者雇入れ計画作成命令が発出される基準として、厚生労働省では以下のいずれかに該当する場合と示されています。
- 実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満、かつ不足数が5人以上であること
- 不足数が10人以上であること
- 法定雇用障害者数が3人または4人であり、雇用障害者数が0人であること
(2)障害者雇入れ計画の適正実施勧告
計画1年目の12月時点で計画実施状況が悪い企業に対して、計画の適性実施勧告が行われます。
(3)特別指導
障害者雇用状況の改善がとくに遅れている企業には、計画期間終了後に9ヶ月間を目途に企業名の公表を前提とした特別指導が行われます。
(4)企業名の公表
障害者雇用促進法第47条にある通り、最終的に障害者雇用状況の改善が見られないと判断された場合は企業名が公表されます。
また、障害者雇用の不足数がとくに多い企業の幹部に対して厚生労働省からの直接指導も行われます。
企業名が公表されることによる影響
前述の通り、ハローワークの3段階目にある特別指導が行われても最終的に障害者雇用の状況に改善が見られない場合には、厚生労働省のサイトで企業名が公表されます。
企業名が公表された場合、どのような影響が考えられるのでしょうか。
公表される企業名
厚生労働省のサイト内で「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」というタイトルで企業名が公表されます。
毎年3月下旬に「報道・広報」というカテゴリの報道発表資料として掲載されていますので、最新情報として2024年3月27日(水)掲載分を確認するとわかります。
または厚生労働省サイトの右上にある検索窓に「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」と検索するとサイト内検索結果が表示されますのでチェックしてみてください。
障害者の雇用状況に改善が見られないとして、2022年は6社、2023年は5社、2024年は1社が公表されています。
障害者の雇用状況に改善が見られない企業情報を検索する
2024年3月に報道発表資料として発表された企業名公表を見る
そして企業名が公表された場合には、次のような影響が出ることが考えられます。
- 企業イメージの低下
- 採用計画や人員計画への影響
- 社員のモチベーション低下
企業イメージの低下
前述の通り企業名が公表されると、厚生労働省のサイトに掲載されたままになるため障害者雇用が達成できていない企業として世間に広く知られることになります。
障害者を雇用することは障害者雇用促進法という法律で定められた義務であり、企業の社会的責任(CSR)でもあります。
公表されることで企業イメージが低下して、今後の業績や取引に影響が出る可能性があるでしょう。
採用計画や人員計画への影響
就職活動や転職活動を行う人の多くは、業界研究や企業研究を行う時にインターネットから情報を得ていることがほとんどです。
そこへ求人応募しようと思っていた企業の名前が障害者雇用の義務違反で社名が厚生労働省のサイトで公表されていると知った場合、応募に少なからず影響が出る可能性もあります。
そもそも企業は、人材採用のために多くの採用経費や人的コストをかけているはずです。
企業名が公表されることによって応募者が集まらないなど、採用計画や人員計画に悪影響があれば障害者雇用納付金を徴収される以上の経営リスクが発生するでしょう。
社員のモチベーション低下
社員の中には、家族や知人に障害者がいることもあるかもしれません。
自分が働く会社が障害者を雇用しない企業として社名を公表されたら、会社に対しての愛着や信頼がもてなくなるほか、それによって帰属意識の低下を引き起こすこともありえるでしょう。
勤務先の社名公表は社員のモチベーションの低下を招き会社の業績が悪化する可能性もあり、社員の離職・退職につながる場合もあります。
障害者雇用促進法の法定雇用率まとめ
障害のある人が安定した職業生活を実現できるように制定された障害者雇用促進法は、企業や事業主に対し一定の割合で障害者の雇用を義務づける法律です。
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が2.5%に改定されたことにより、従業員が40人以上いる企業には障害者を1人以上雇用する必要があります。
法定雇用率を達成できない企業には、障害者雇用納付金が徴収されるほかハローワークによる行政指導で最悪の場合に厚生労働省のサイトに企業名の公表が行われます。
企業名が公表されると企業イメージの低下や取引先・顧客からの信用失墜、社員のモチベーション低下などさまざまリスクが生じます。
障害者を雇用することは、法的義務だけでなく企業の社会的責任でもあります。
企業は障害者を受け入れる社内体制をしっかりと整え、障害者雇用を促進しましょう。
また2026年7月より、法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられることになっています。
障害のある人にとっては障害者雇用枠での求人応募もしやすくなり就労の機会を広げられるため、この制度を大いに活用してください。
以下の記事では、障害者を支える主要な10つの法律について必要な要素だけをコンパクトにまとめて解説していますので併せてお読みください。



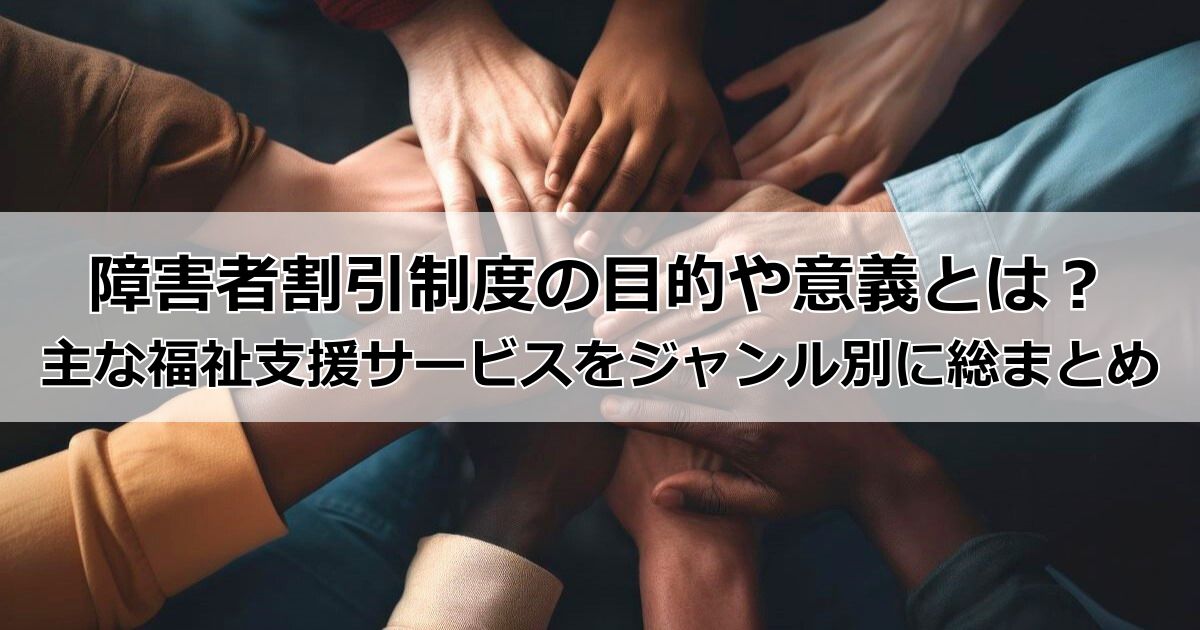




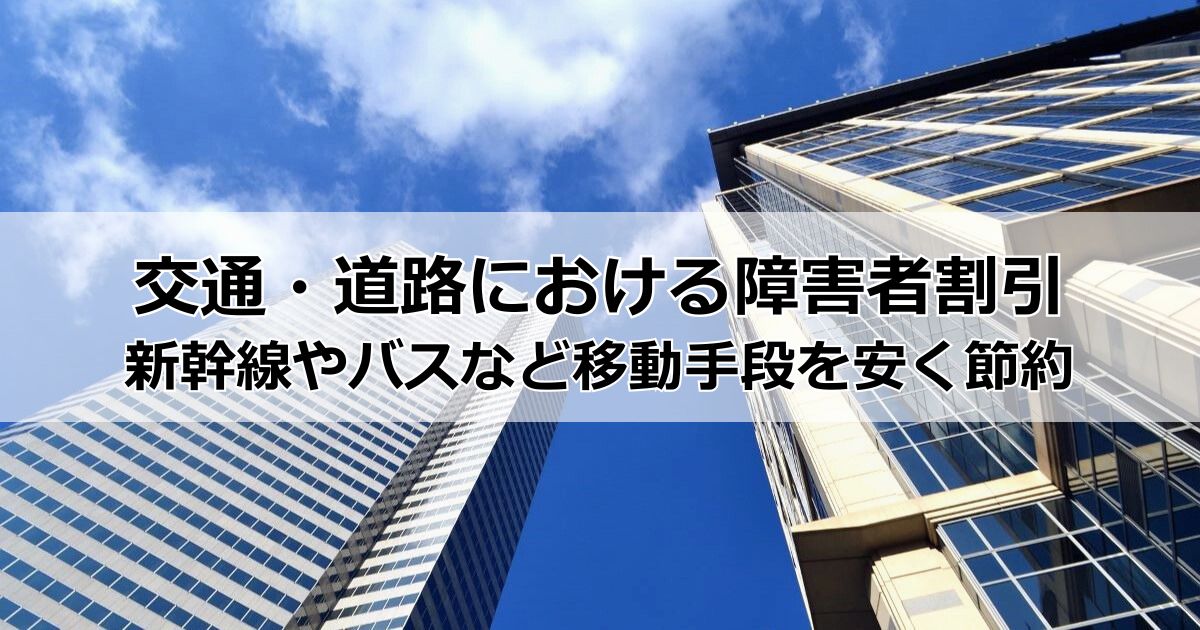
コメント