
国が定めた法律の中には、障害者に関連する法律が数多く存在しているのをご存知でしょうか。
障害者に関する基本原則を定めた障害者基本法、障害者差別の解消推進に関する障害者差別解消法、障害者の雇用促進に関する障害者雇用促進法など。
すべてを挙げるとキリがありませんが、障害の種類や目的などによって少なくとも15種類以上あるのです。
この記事では障害者に関連する法律の中で、もっとも主要とされる10つの法律について紹介します。
必要な要素だけをコンパクトにまとめて解説していますので、障害をもつ人を支えている法律を知るご参考になれば幸いです。
障害者に関連する10つの法律一覧
国が定めた障害者に関連する法律は、15種類以上にわたります。
そんな多数ある法律の中でもっとも障害者を支えている法律は10つあり、以下の通りです。
| 法律名称 | 概要 | 所管官庁 |
|---|---|---|
| 障害者基本法 | 障害者に関する基本原則を定めた法律 | 内閣府 |
| 障害者差別解消法 | 障害を理由とする差別の解消推進に関する法律 | 内閣府 |
| 障害者雇用促進法 | 障害者の雇用促進などに関する法律 | 厚生労働省 |
| 障害者総合支援法 | 障害者の日常・社会生活を総合的に支援する法律 | 厚生労働省 |
| 身体障害者福祉法 | 身体障害者に必要な援助や保護を行う法律 | 厚生労働省 |
| 知的障害者福祉法 | 知的障害者に必要な援助や保護を行う法律 | 厚生労働省 |
| 精神保健福祉法 | 精神保健・精神障害者福祉に必要な援助や保護を行う法律 | 厚生労働省 |
| 発達障害者支援法 | 発達障害者に必要な援助や保護を行う法律 | 厚生労働省 |
| 身体障害者補助犬法 | 補助犬の受け入れに関する法律 | 厚生労働省 |
| 障害者虐待防止法 | 障害者への虐待を防止する法律 | 厚生労働省 |
他にもある障害者に関連する法律
上記は障害者に限定されている法律として10つを挙げましたが、他にも以下のような法律があります。
| 心身喪失者等医療観察法 | 心身喪失等の状態で重大な他害行動を行った者の医療及び観察等に関する法律 |
| 難病医療法 | 難病の患者に対する医療等に関する法律 |
| バリアフリー法 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化・促進に関する法律 |
| 児童福祉法 | 障害をもつ18歳未満の子ども(障害児)に関する法律 |
さらに福祉用具や通信・放送関連、特別支援学校に関するものまで、障害者・障害児に関連した法律はさまざまです。
これらは高齢者や子ども、医療に関わる難病者を含む法律となるため、この記事では省略します。
目的に応じた障害者に関する法律の分類
しかし10つも障害者に関する主要な法律があると、どういった種類の法律なのかどういう趣旨があるのかわかりにくい人もいるでしょう。
障害者に関する10つの法律を目的別に大きく分類すると、以下の通りです。
障害者の雇用や支援に関する4つの法律
| 障害者基本法 | 障害者の福祉施策だけでなく企業における障害者の雇用促進についても記載されている |
| 障害者差別解消法 | 国・地方公共団体や企業は障害者が配慮を求められた際に合理的配慮をする法的義務がある |
| 障害者雇用促進法 | 民間企業や全ての事業主に対して障害者を雇用する法的義務がある |
| 障害者総合支援法 | 障害者が自立した社会生活を送れるように就労支援が行われている |
障害の種類や手帳交付に関する4つの法律
| 身体障害者福祉法 | 身体障害者の自立と就労の促進、福祉の増進を図る |
| 知的障害者福祉法 | 知的障害者の自立と社会参加の支援、必要な保護を行う |
| 精神保健福祉法 | 精神障害者の医療・保護や自立と社会参加のために必要な援助を行う |
| 発達障害者支援法 | 発達障害に配慮した適切な支援や就労支援を行う |
障害者の福祉に関する2つの法律
次項からは、障害者に関する10つの法律について具体的な意味や特徴をそれぞれ説明します。
障害者基本法
障害者基本法は、障害の有無に関わらず全ての国民が平等に暮らせる社会を作るために、障害者の権利や福祉に関する国の基本的な方針を定めた法律です。
1970年(昭和45年)に制定された「心身障害者対策基本法」を前身とし、1993年(平成5年)の改正に伴い「障害者基本法」へ名称が変更されました。
障害者基本法の概要
| 法律名称 | 障害者基本法 |
| 所管官庁 | 内閣府 |
| 制定 | 1970年(昭和45年) |
| 目的 | 障害者の自立や社会参加に向けた支援を推進すること |
| 対象 | 身体障害、知的障害、精神障害、その他心身の機能障害があるために日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人 |
| 公式サイト | 障害者基本法 |
障害者基本法の目的
障害者基本法は、障害者の自立や社会参加に向けた支援を推進することを目的に、国や地方公共団体などの責務を明らかにしています。
障害者基本法では、障害者の福祉に関する施策だけではありません。
基本的な施策として挙げられている内容は、以下の通りです。
| (第14条) | 医療・介護など |
| (第15条) | 年金など |
| (第16条) | 教育 |
| (第17条) | 療育 |
| (第18条) | 職業相談など |
| (第19条) | 雇用の促進など |
| (第20条) | 住宅の確保 |
| (第21条) | 公共的施設のバリアフリー化 |
| (第22条) | 情報の利用におけるバリアフリー化など |
| (第23条) | 相談など |
| (第24条) | 経済的負担の軽減 |
| (第25条) | 文化的諸条件の整備など |
他にも選挙や司法手続きによる配慮、防災など全部で第36条まであります。
企業における障害者の雇用促進
障害者基本法は、障害者の福祉に関する施策を行うだけでなく企業における障害者の雇用促進についても記載されています。
障害者基本法第19条では、企業は障害者を雇用するにあたって以下の2つを心がける必要があると定めています。
- 障害者の能力を正当に評価して適切な雇用機会を確保する
- 個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理によって雇用安定を図る
また国や地方公共団体は、障害者を雇用する企業に対して以下の2つを支援しています。
- 障害者雇用のための経済的負担を軽減する
- 障害者を雇用する際に必要となる施設や設備の整備などに要する費用の助成などを行う
例えば視覚障害者を雇用するにあたって拡大読書器を購入するなど、職場環境の整備を行った企業は助成金を申請することが可能です。
参考:障害者基本法(内閣府)
障害者差別解消法
障害者差別解消法は、正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として障害を理由とする差別を禁止する法律です。
日本は世界的に見て障害者に関する法整備が遅れており、2006年に初めて国際連合総会に出席し「障害者権利条約」に署名しましたが、その時点ではまだ障害者への差別を禁じる法整備は整っていませんでした。
その後2011年に成立した「障害者差別基本法」をもとに、2013年に制定されたのが「障害者差別解消法」です。
障害者差別解消法の概要
| 法律名称 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) |
| 所管官庁 | 内閣府 |
| 制定 | 2013年(平成25年) |
| 目的 | 障害者の職業の安定を図ること、障害の有無に関わらずそれぞれの希望や能力に応じて各地域で自立した生活を送れる共生社会を実現することを柱とする |
| 公式サイト | 障害者差別解消法 |
障害者差別解消法の目的
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年(平成25年)に障害者差別解消法が制定されました。
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害者基本法の第4条にある、以下の3つの項目を具体化した法律です。
- 障害を理由とした差別的な行為を禁止すること
- 社会的なバリアを取り除かなかったことによって障害者の権利を侵害することを防ぐこと
- 国は障害に関する啓発や知識を広げる取り組みを行うこと
企業も合理的配慮の提供を義務化
2024年(令和6年)4月の改正により、国・地方公共団体だけでなく企業に対しても合理的配慮を提供することを義務づけることになりました。
合理的配慮とは働く環境の調整を通して社会にある障害を取り除き、より働きやすく1人ひとりが能力を発揮できるようサポートをすることです。
障害のある人が障害のない人と平等な労働機会を得られるよう、状況に応じた困りごとを改善する目的で個別の対応や支援を行います。
例えば車いすの人が段差のある場所で困っている場合に車いすを持ち上げるサポートをしたり、会話が難しい場合に筆談やタブレット端末を使ってコミュニケーションを図るなどです。
ただし相談した内容がすべて採用されるとは限らず、お互いにすり合わせをしながら合理的配慮の内容を決めていきます。
差別解消の措置
国・地方公共団体や企業が、障害を理由に障害者ではない人とは違う不当な差別的取扱いをして障害者の権利利益を侵害してはならないことになっています。
また国・地方公共団体や企業は、障害者が社会的バリアの除去を必要としている場合にその実施に伴う負担が過重でないなら合理的配慮をしなくてはならないとなっています。
罰則
障害者や行政機関などから構成される障害者差別解消支援地域協議会に関わる人が、そこで知り得た秘密を漏らした場合には1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。
民間企業が障害者への不当な権利侵害や差別的取扱いをした場合、行政などに報告し助言・指導・勧告を受ける必要があります。
もし未報告や虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が課せられます。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府)
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法は、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、企業や事業主に対して一定の割合で障害者の雇用を義務づける法律です。
1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」を前身に、幾度も改正が行われ現在の名称に至っています。
障害者雇用促進法の概要
| 法律名称 | 障害者の雇用の促進等に関する法律 |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 1960年(昭和35年) |
| 目的 | 就労が困難な障害者に平等な雇用の機会を提供し、安定した職業生活を目指すこと |
| 対象 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有している人 |
| 公式サイト | 障害者雇用促進法 |
障害者雇用促進法の目的
就労が困難な障害者に平等な雇用の機会を提供し安定した職業生活を目指すことを目的に、民間企業はもちろん全ての事業主に対して障害者雇用を義務づけています。
雇用対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有している人が対象です。
障害者雇用のポイントは、障害者の雇用義務として法定雇用率を達成すること、法定雇用率未達成の場合は納付金が徴収されることなどがあります。
法定雇用率の引き上げ
2024年4月に、民間企業における法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。
つまり従業員を40人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければならないという意味です。
法定雇用率は2026年7月以降に2.5%から2.7%に引き上げる予定となっているため、企業における障害者雇用の優先順位はますます高くなることがいえます。
罰則
企業が障害者を雇用推進することは、法的義務であることが定められています。
そのため雇用労働者数が100人以上の企業で、法定雇用率未達成の場合は不足している障害者数に応じて1人につき月額5万円の納付金が徴収されます。
徴収された納付金を財源に法定雇用率を超過達成している企業には、超過する障害者数に応じて1人につき月額2万9千円の調整金が支給される仕組みです。
他にも雇用労働者数が40人以上の企業が毎年6月、ハローワークに「障害者雇用状況報告書」を提出しない、雇用労働者数が100人以上の企業で毎年提出義務のある「障害者雇用納付金申告書」を提出しない・申告内容に虚偽がある場合には違反行為として30万円以下の罰金が課せられます。
筆者が勤務する職場でも法定雇用率に対して雇用する必要のある障害者が3人不足していることがわかり、月5万円+3人分を支払っているそうです。
障害者総合支援法
障害者総合支援法は、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とし、障害の有無に関わらず共生できる社会実現のために障害福祉サービスなどの支援を定めた法律です。
2005年に施行された「障害者自立支援法」が、2014年の改正に伴い「障害者総合支援法」に名称変更されました。
障害者総合支援法は、3年ごとに福祉サービスの見直しや改正が進められています。
障害者総合支援法の概要
| 法律名称 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 2012年(平成24年) |
| 目的 | 障害者や障害児が他の国民と同様に基本的人権が守られ、自立した社会生活を送れるように総合的な支援を行うこと |
| 対象 | 18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)、障害児、難病患者 |
| 公式サイト | 障害者総合支援法 |
障害者総合支援法の目的
障害者総合支援法は、障害のある人が他の人と同じように基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や自立した社会生活を送れるよう総合的な支援を行います。
支援対象は18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)、障害児、難病患者です。
在宅で介護や支援を受けたり就職のための訓練を受けたりするなどの自立支援給付、障がい者が身近な地域で生活していくための地域生活支援事業を柱として、他に必要な福祉サービスを行っています。
これらの支援には世帯所得に応じた月額負担上限額が設定されており、利用料は原則1割負担です。
障害者総合支援法の就労支援について
障害者総合支援法の就労支援は、大きく分けて就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援の3つです。
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を希望する障害者が必要な能力や知識を得られるように支援 |
| 就労定着支援 | 就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般企業に就職した障害者が働き続けるためのサポート |
| 就労継続支援 | 今すぐに一般企業に就労するのが難しい障害者に就労や生産活動の機会を2つの型で提供 A型:雇用契約が結ばれ最低賃金が適用された給料が支払われる B型:雇用契約は結ばず作業に応じた工賃が支払われる |
参考:障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律(厚生労働省)
身体障害者福祉法
身体障害者福祉法は、身体障害のある人の自立と社会経済活動への参加を促進するために必要な援助や保護を行うことを定めた法律です。
1949年に制定された当初は、対象となる身体障害は視力障害・聴力障害・言語機能障害・肢切断または肢体不自由・中枢神経機能障害でした。
その後、内部疾患を中心に徐々に対象が拡大しています。
身体障害者福祉法の概要
| 法律名称 | 身体障害者福祉法 |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 1949年(昭和24年) |
| 目的 | 身体障害者の生活の質を向上させ、社会経済活動への積極的な参加を促進すること |
| 対象 | 身体障害者手帳を交付されている人(1~6級、7級は手帳なし) |
| 公式サイト | 身体障害者福祉法 |
身体障害者福祉法の目的と内容
身体障害者福祉法は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために援助したり必要に応じて保護したりすることで、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的に制定されました。
身体障害のある人のうち身体障害者手帳を交付された人が、どのような支援や福祉サービスを受けられるかについて定められています。
身体障害者手帳を交付された人に向けた主な支援内容は、以下の通りです。
- 入所施設・通所施設での介護、訪問介護、移動支援など日常生活を支援するもの
- 就労支援センターや障害者雇用促進法に基づく雇用促進措置の就労を促進するもの
- バリアフリー化推進や身体障害者の権利を擁護するための施策などの社会参加を促進するもの
- 障害基礎年金や特別障害者手当などの経済的支援に関するもの
身体障害者福祉サービスの主な内容は、以下の通りです。
(1)相談援助サービス 障害の種類や程度に応じて利用できる制度やサービスの案内、手帳の取得支援などのアドバイス
(2)日常生活用具給付サービス 車椅子や補聴器など日常生活を便利に過ごすための用具を支給
(3)生活援助サービス 食事や入浴の介助など日常生活を自立して行えるように支援
(4)社会参加サービス 就労支援や教育支援、余暇活動支援など
身体障害者手帳の交付対象と社会福祉サービス
身体障害者福祉法により社会福祉サービスなどの支援を受けられる身体障害者手帳の交付対象は、以下の通りです。
| 視覚障害 | 視力障害、視野障害 |
| 聴覚・平衡機能障害 | 聴覚障害、平衡機能障害 |
| 音声・言語機能、そしゃく機能障害 | - |
| 肢体不自由 | 上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能・移動機能) |
| 内部障害 | 心臓・じん臓・呼吸器・小腸の機能障害、ぼうこう・直腸の機能障害、肝臓の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
| 重複障害 | 上記の5つに分類される身体障害のうち2つ以上 |
障害の等級や市区町村により違いはありますが、身体障害者手帳の交付を受けると以下のようなサービスを受けることが可能です。
(1)公共料金等の割引…交通機関の運賃割引、携帯電話や上下水道の割引、NHK受信料減免など
(2)税金の控除・減免…所得税・住民税の控除、相続税の控除、自動車関連税の軽減など
(3)手当の支給など…福祉手当など
(4)その他…障害者雇用での就職、公営住宅への優先入居など
知的障害者福祉法
知的障害者福祉法は、知的障害のある人の自立と社会への参加を促進するために必要な援助や保護を行うことを定めた法律です。
2013年に障害者の日常・社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」が制定され、そのうち知的障害のある人に関するサービスや制度が移行されました。
知的障害者福祉法の概要
| 法律名称 | 知的障害者福祉法 |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 1960年(昭和35年) |
| 目的 | 知的障害者の自立と社会参加の支援と必要とする保護を行うこと |
| 対象 | 知的障害者(定義がないため自治体によって基準が異なる) |
| 公式サイト | 知的障害者福祉法 |
知的障害者福祉法の目的と定義
知的障害者福祉法は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために知的障害者を援助するとともに必要な保護を行うことで知的障害者の福祉を図ることを目的としています。
知的障害者には療育手帳が交付されますが、療育手帳制度によるもので知的障害者福祉法とは直接的に関係していません。
また知的障害はどのような障害なのか定義がないため、自治体によって支援やサービスを受ける場合に適用される基準が少しずつ異なります。
実際には以下の基準で考えられているため、参考にしてください。
- 知的検査によって確かめられる知的機能の欠陥がある
- 適応機能の明らかな欠陥がある
- おおむね18歳までに生じている
精神保健福祉法
精神保健福祉法は、正式名称を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」といい、精神障害者の福祉の増進や国民の精神保健の向上を図るために制定された法律です。
1950年に制定された「精神衛生法」が、1987年に「精神保健法」、1995年に「精神保健福祉法」へと名称が変更されました。
精神保健福祉法の概要
| 法律名称 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法) |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 1995年(平成7年) |
| 目的 | 精神障害者の医療や保護、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加促進のために必要な援助を行うこと |
| 対象 | 精神障害者 |
| 公式サイト | 精神保健福祉法 |
精神保健福祉法の目的
精神保健福祉法は、精神障害者の権利の擁護を図り必要な医療と保護を行い、障害者総合支援法と連携しながら精神障害者の自立と社会活動への参加を促進するために必要な援助を行うとしています。
また国民の心の健康への保持・増進に努めることで、精神障害者の福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることを目的としています。
精神保健福祉法の適用対象
統合失調症や発達障害などの精神障害がある人は、精神障害保健福祉手帳の交付を受けることができます。
精神保健福祉手帳が交付される精神障害の症名は、以下の通りです。
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
- 発達障害
- その他の精神疾患
発達障害者支援法
発達障害者支援法は、発達障害者を支援するための法律です。
この法律が施行されるまでは日本で障害だと認められていなかった、知的障害を伴わない自閉症やADHDなどの発達障害がある人も必要な支援やサービスを受けられるようになりました。
2016年の改正により発達障害者への支援が切れ目なく行われ、より充実したものとなるよう定められています。
発達障害者支援法の概要
| 法律名称 | 発達障害者支援法 |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 2004年(平成16年) |
| 目的 | 発達障害の早期発見と早期支援の体制を地方自治体に推進すること、学校教育において個々の発達障害に配慮した適切な支援や就労支援を行うこと |
| 対象 | 発達障害者 |
| 公式サイト | 発達障害者支援法 |
発達障害者支援法の目的
発達障害者支援法は、発達障害の早期発見と発達支援を行い、支援が切れ目なく行われることに関する国・地方公共団体の責務を明らかにすることを目的として定めています。
それは発達障害者の自立と社会参加のための生活全般にわたる支援を図り、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に役立つことを意味します。
発達障害支援センターだけではなく、学校教育において発達障害に配慮した適切な支援や就労の支援も行います。
発達障害者やその家族だけでなく、教育を受ける学校や雇用する企業にとっても発達障害との向き合い方を考えさせられる内容となっている法律です。
発達障害者の対象
発達障害者は、精神障害の一種として精神保健福祉手帳が交付されます。
なお、発達障害者支援法は精神保健福祉手帳と直接的に関係ありません。
発達障害に該当する内容は、以下の通りです。
- 自閉症(ASD)
- アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
- 学習障害
- 注意欠如多動性障害(ADHD) など
発達障害者への支援ポイント
発達障害者への支援ポイントは、以下の通りです。
- 社会的なバリアを除去する
- 切れ目のない支援をする
- 司法手続きにおいて配慮する
- 教育現場で支援計画を一貫する
社会的なバリアの除去とは、発達障害者個人の問題としてではなく社会全体の問題として捉え障害の有無に関わらず暮らせる社会を目指すことです。
発達障害は早期発見・早期療育が重要だと考えられており、発達障害者支援法には就学前から就労までだけでなく就労後も定着するまで継続的な支援が必要だと定められています。
社会的なバリアについては、別記事で紹介します。
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立と社会参加を促進するために補助犬との社会参加の受け入れを義務づける法律です。
これまで盲導犬・聴導犬・介助犬に対する理解が不十分なために、入店を断られたり電車内で非難されたりすることが多くありました。
しかし2003年(平成15年)に施行された身体障害者補助犬法により、盲導犬などの同伴を断れないことになっています。
身体障害者補助犬法の概要
| 法律名称 | 身体障害者補助犬法 |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 2002年(平成14年) |
| 目的 | 身体障害者の自立と社会参加を促進するために補助犬との社会参加の受け入れを義務づけること |
| 対象 | 補助犬と同伴する身体障害者 |
| 公式サイト | 身体障害者補助犬法 |
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬は、障害のある人の目や耳、手足となって働くよう訓練された盲導犬・聴導犬・介助犬の総称です。
3種類の補助犬はそれぞれ一定の訓練基準によって訓練されており、国が指定する法人から認定されています。
盲導犬
盲導犬は、視覚障害のある人が安全に歩行できるように誘導する補助犬です。
目の見えない人や見えにくい人が行きたい時に行きたい場所へ出かけられるように、障害物を避けたり段差や交差点を伝えてくれたりして目的地まで案内するなどのサポートをします。
盲導犬はハーネスという胴輪をつけて障害者の左側を歩き、ハーネスを通して障害者が安全に歩行できるように支えているのです。
聴導犬
聴導犬は、聴覚障害のある人が安全かつ安心して生活ができるように誘導する補助犬です。
耳の聞こえない人や耳の聞こえにくい人に生活する上で必要な音の情報を知らせてサポートします。
例えばインターホンや自動車の警笛、火災報知器や非常ベルの警報音、赤ちゃんの泣き声などがしたら障害者にタッチするなど、さまざまな動作を使って音を運んでくれるパートナーなのです。
介助犬
介助犬は、手や足に障害のある人の日常生活における動作をする補助犬です。
身体の不自由な人の手足となって落とした物を拾う、指示された物をもってくる、ドアを開閉するなど日常生活の手助けをします。
不測の事態が起きた時に人を呼びにいったり緊急ボタンを押したりするといった緊急対応もでき、障害者の精神的な支えにもなるといわれています。
身体障害者補助犬はペットではない
身体障害者補助犬は、ペットではありません。
障害のある人のサポートをするために訓練されたパートナーです。
社会のマナーを守れるほか衛生面も管理されているため、公共施設や交通機関、飲食店などさまざまな場所に同伴できます。
身体障害者補助犬の受け入れ義務
これまで補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)を連れていることを理由に、障害者が飲食店や交通機関などへの立ち入りを拒否される事例がありました。
そんな制度的なバリアを抱える障害者や補助犬に対して、社会的な受け入れ体制を整えることを義務づけるのが身体障害者補助犬法です。
身体障害者補助犬の受け入れ義務がある場所は、主に以下の通りです。
- 公共施設
- 公共交通機関(電車やバスなど)
- 不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設、飲食店、ホテル、病院など)
- 国や地方団体などの事務所や従業員45人以上の民間企業
補助犬を同伴する・あるいは生活を共にする必要がある障害者の人は、この身体障害者補助犬法を知っていることで行動範囲を広げられるわけです。
身体障害者を雇用する企業も、補助犬同伴での出勤に対する受け入れが義務化されているため受け入れ体制を整える必要があるといえます。
制度的なバリアについては、別記事で紹介します。
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障害者への虐待を禁止・防止するための法律です。
障害者虐待防止法の概要
| 法律名称 | 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法) |
| 所管官庁 | 厚生労働省 |
| 制定 | 2011年(平成23年) |
| 目的 | 障害者への虐待を禁止すること、虐待を受けた障害者の保護や自立のための措置など |
| 公式サイト | 障害者虐待防止法 |
障害者虐待防止法の目的
障害者虐待防止法の目的は、まず障害者への虐待を禁止することです。
そして国などの責務、虐待を受けた障害者の保護や自立のための措置、養護者への支援措置を定めるとともに、障害者虐待の防止と養護者への支援施策を促進し障害者の権利利益を守るように行動します。
障害者虐待とは
障害者虐待にあたる加害者として3つあり、(1)保護者などの養護者による虐待(2)障害者福祉施設従業者といったサービススタッフによる虐待(3)障害者を雇用している事業主による虐待です。
虐待にあたる内容・種類としては以下の通りです。
| 身体的虐待 | 暴力・拘束・過剰な投薬など |
| 放棄や放置 | 食事や排せつなど必要な支援を行わない |
| 心理的虐待 | 侮辱、無視など |
| 性的虐待 | 同意なしの性的行為やその強要など |
| 経済的虐待 | 同意なしの財産搾取、必要性なく本人が使う金銭を制限するなど |
障害者虐待防止法では虐待ではないかと思った段階で通報することが義務づけられているため、確信をもてなくてもすぐに通報することが必要です。
参考:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(厚生労働省)
障害者に関連する法律まとめ
この記事では主要となる法律を10つ紹介しましたが、他にも障害者・障害児に関連する法律が多数あり複雑です。
基本原則を定めた障害者基本法をベースに、障害者の日常・社会生活を総合的に支援する障害者総合支援法や障害者別に具体的な支援を定めた各福祉法、補助犬法など。
あらゆる障害を考慮したものや個別の事柄について定めたものなど、これらの法律を上手く活用しながら生活を成り立たせているわけです。
障害のある人の生活にとって役立つ支援やサポートには何があるのか。
障害者を家族にもっている人や障害者と関わる仕事をしている人、障害者を雇用する立場にある企業の採用担当者などは関連する法律を守った上で必要な対処を行いましょう。
そして障害をもつ人は、これらの法律に守られていることを理解しながら日常・社会生活を快適かつ安全に過ごせるように願っています。



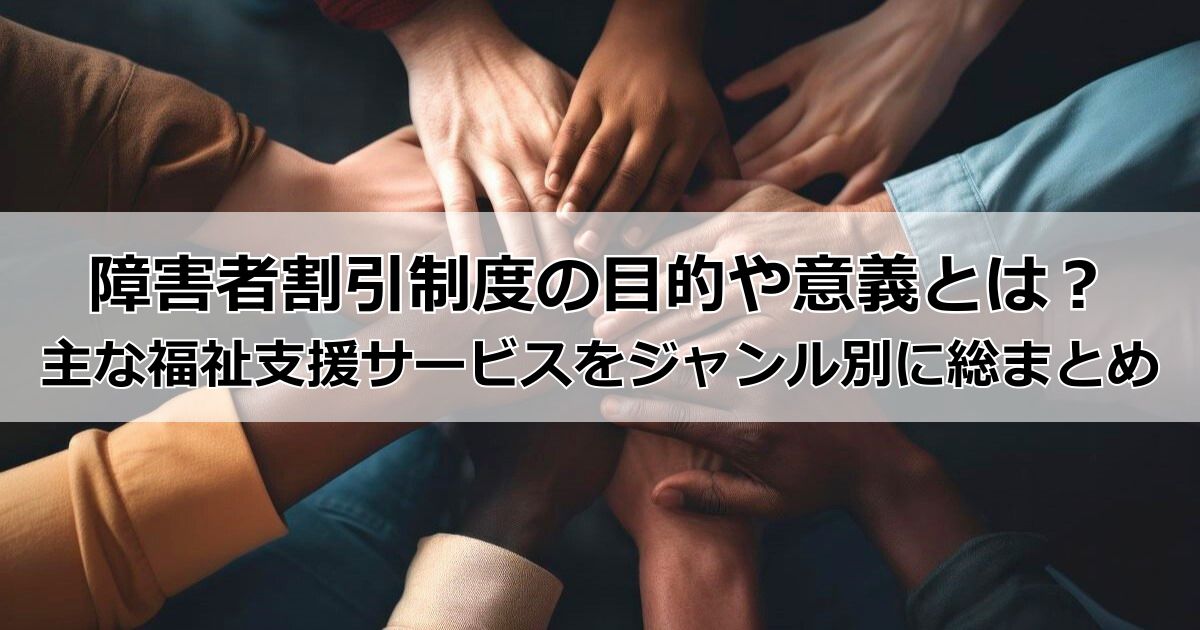




コメント