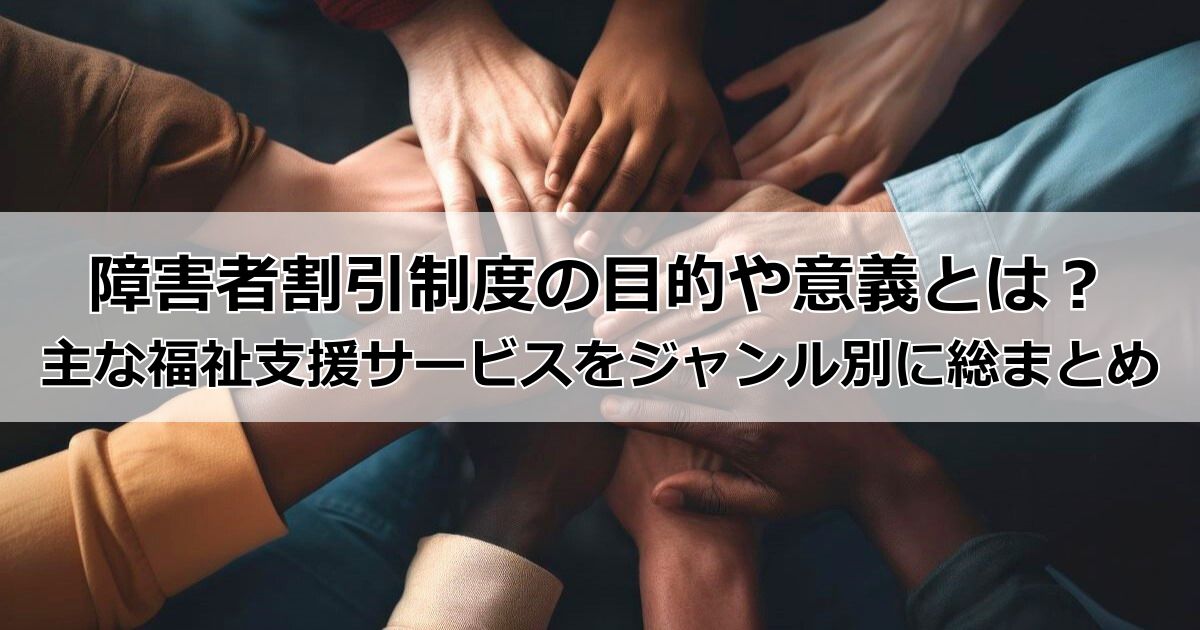
電車やテーマパーク、美術館、温泉、スポーツ観戦など。
あらゆる公共施設や民間サービスを利用するにあたって、障害をもつ人に与えられた割引制度があるのをご存知でしょうか。
例えばタクシーを利用すると運賃が1割引、携帯電話の基本料金が半額になるなどさまざまな障害者割引・優遇があります。
なぜ障害者には割引や優遇があるのか、通常よりどこまで安くなるのか。
この記事では障害者割引制度の目的や意義を説明しながら、代表的な公共・民間の割引サービスを紹介します。
交通や通信、娯楽・レジャー、旅行などジャンル別に多数ある割引の中からよく利用される身近なサービスを選んでいますので、障害のある人が生活する上で費用負担を軽減する手段として参考にしてください。
健常者にとっても、障害者が経済面や機会の不平等にならないように国や地方自治体、民間企業が導入した障害者割引制度について理解を深める機会になれば幸いです。
障害者割引制度とは
障害者割引制度は、障害のある人が日常生活において社会的な自立と社会活動への参加支援を促す優遇措置として各種サービスに割引を適用するために導入されたものです。
健常者と平等にさまざまな活動に参加できるようにサポートすることを目的として、障害者手帳などをもっている人向けに各種割引や優遇制度が用意されています。
障害者割引制度の目的や意義
障害者割引はなぜあるのか、と疑問に思う人もいるでしょう。
障害者は、健常者よりも生活にお金がかかるのが実情です。
障害者が健常者と同じような動きを達成しようとする場合に、意図しない出費を余儀なくされるケースがあります。
例えば以下のような場合には、日常生活において能率の向上を図るために必要な出費です。
- 車での移動を必要とする場合
- 車いすや補聴器といった補装具購入を必要とする場合
- 医療機関への定期的な通院や治療を必要とする場合
- 日常生活を送るために増改築費用を伴う場合
- 補助犬が住める住宅に転居する場合
交通機関での移動が困難だったり同伴者が必要だったりするなど、障害のある人は普段の外出や遊びに出かけることが健常者に比べ難しい場面が多々あります。
他にも障害のために必要な治療費や思うような就労が困難となるケースもあり、経済的余裕が得にくい場合もあるでしょう。
これらの影響により、ハードルが健常者よりも高くなる傾向にある社会との関わりが薄くなってしまいがちな障害者が大勢います。
そういった障害者が生活しやすいように、そして積極的に自立と社会への参加がしやすいように障害者割引という福祉支援が存在しています。
障害者割引の対象は後述しますが、主に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有している人です。
店舗や施設でのサービスによっては、同伴者や介助者も同時に割引を受けられる場合もあります。
障害者割引の必要性
筆者も障害者割引を利用する1人ですが、近年では障害者が利用しやすい環境が増えているもののまだまだそのような施設やサービスを見つけることに時間を費やすことも多いです。
2006年に開催された国際連合では「私たちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」を合言葉に、世界中の障害者が参加して採択された障害者権利条約があります。
その後、SDGsにもこの考えが多く取り入れられました。
1人ひとりの違いが尊重され健常者と同じような生活ができるようになる社会は、日本のみならず世界規模で浸透してきています。
今は健常者であっても誰もが予期せず障害を抱える可能性があります。
障害の有無にかかわらず、誰もが豊かに生活ができるような障壁のない社会がこれからも発展していくことを望んでいます。
SDGsとは
SDGsというのは、Sustainable Development Goalsの頭文字をとった略で「持続可能な開発目標」という意味です。
2015年に開催された国連のサミットで、加盟国193カ国の全会一致で定められました。
SDGsには17のゴール(目標)と、さらに細分化された169のターゲット(具体目標)で構成されます。
SDGsで掲げられている17のゴール(目標)には、すべての人に健康と福祉をもたらす・人や国の不平等をなくす・平和と公正をすべての人に・質の高い教育など17つの目標があります。
2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標であり、SDGsへの取り組みを重要視している企業が増えているのです。
参考:JAPAN SDGs Action Platform(外務省)
障害者割引が適用される主な対象者
障害者には、健常者と同等の生活を送るために最低限必要な支援を受けやすくするための証明書があります。
障害者割引が適用される対象者は、主に以下の手帳や受給証をもっている人です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の規定に基づき身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付される障害者手帳です。
自治体や世代によっては「赤い手帳」と呼ばれることもあります。
身体障害者手帳については、別記事で詳しく紹介します。
療育手帳
療育手帳は、療育手帳制度に基づき知的障害(知的発達症)であると判定された人に交付される障害者手帳です。
原則18歳未満の人に交付され、「愛の手帳」「緑の手帳」と呼ばれることもあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)は、精神障害があると認定された人に交付される障害者手帳です。
精神障害には発達障害やてんかんを含み、2年ごとに更新が必要と定められています。
特定疾患医療受給者証
特定疾患医療受給者証は、原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち長期にわたり高額な医療費が必要となることから厚生労働省が指定する特定疾患をもつ人に交付される受給証明書です。
長期にわたり高額な医療費が必要となるため、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1ヶ月1万円までとなります。
特定疾患登録者証
特定疾患登録者証は、国が指定する難病に罹患し指定難病の診断基準を満たしている人に対して交付される登録証明書です。
特定医療費(指定難病)受給者証
特定医療費(指定難病)受給者証は、国が指定する難病に罹患している人に対して医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成する制度です。
上記は、あくまで障害があることを示す基本的な対象です。
施設やサービスによっては一部が割引対象外となることがありますので、各施設やサービスの公式サイトなどで確認してください。
また、被爆者健康手帳や戦場傷病者手帳をもっている人も割引対象としている施設やサービスもあります。
身近な障害者割引の一例
私たちが普段の生活で利用する施設やサービスには、障害者向けの割引を適用していることがあります。
障害者割引が適用される代表的なサービスとしては、以下のようなジャンルです。
電車やバスなどの公共交通機関・道路
JRをはじめとする鉄道会社では、障害者の対象条件を満たせば普通乗車券が半額で利用可能です。
電車や新幹線のほかにもバスやタクシー、飛行機、フェリーなどの交通機関でも運賃の割引があります。
他に高速道路など有料道路の料金、公営駐車場、レンタカーの割引などもありますが、ETCを利用する場合は市区町村の福祉窓口への申請が必要です。
交通・道路に関する障害者割引については、下記記事をご参考ください。
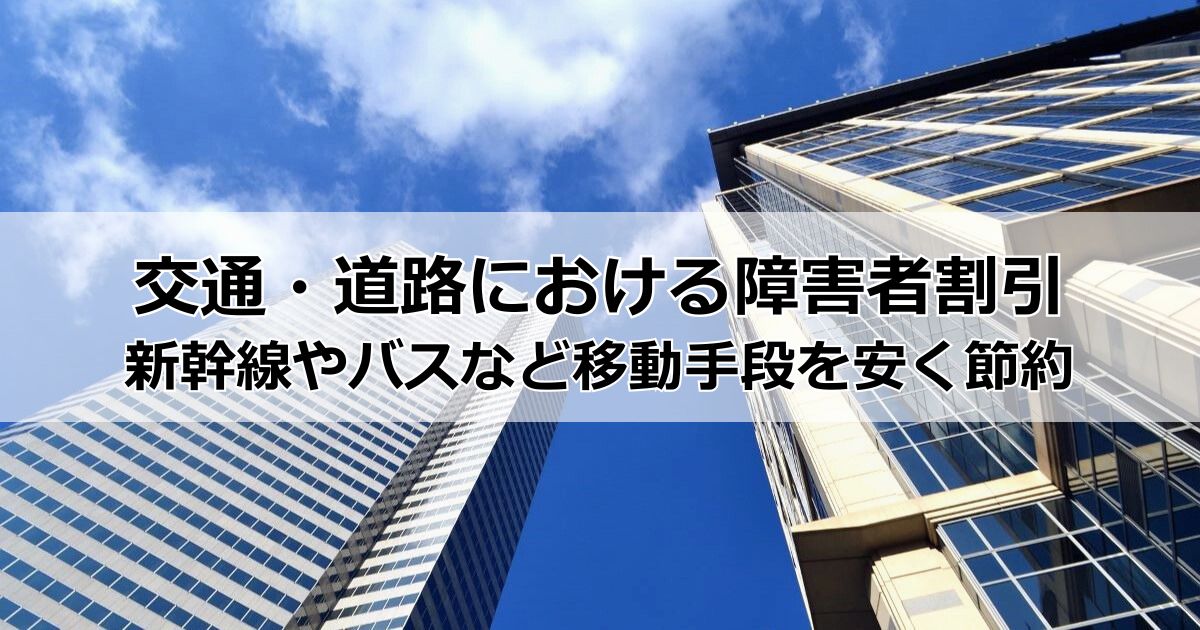
携帯やスマートフォンの通話・通信
IT技術の進歩により、近年では携帯電話よりもスマートフォンを利用する人も増えています。
一部の料金プランで割引が適用されたり通話料が無料になったりするなど携帯・通信会社によって対応はさまざまです。
携帯電話・ネットワーク通信に関する障害者割引については、下記記事をご参考ください。

遊園地やテーマパークの娯楽・レジャー施設
遊園地やテーマパークなどの娯楽・レジャー施設でも障害者割引があります。
東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど、人気のテーマパークでは入園料が年々値上がりしている中で約20~50%の割引で利用可能です。
他にカラオケボックスやボウリングといったアクティブなスポーツレジャー施設でも割引を導入していることがあります。
娯楽・レジャー施設に関する障害者割引については、下記記事をご参考ください。

動植物園や映画などの芸術・文化、自然、エンタメ
動物園や植物園、美術館といった芸術・文化や自然における施設では、障害者向けの割引料金が設定されており多くが半額または無料です。
他に映画館では1,000円で観賞できたりスポーツ観戦でも安く入場できたりするなど、エンターテインメントでも割引が実施されています。
芸術・文化、自然、エンターテインメントにおける障害者割引については、下記記事をご参考ください。

旅行や宿泊、観光・アウトドア
温泉やホテルなどの宿泊、観光スポットなど旅行にまつわる施設やサービスでも障害者割引を設定しているところがあります。
登山鉄道や登山バス、ケーブルカーなどアウトドアに関する交通サービスでも障害者割引が適用されることも多いです。
旅行・観光に関する障害者割引については、下記記事をご参考ください。

障害者が生活する上で負担を軽減する割引まとめ
厚生労働省の資料によると、日本における障害者数は2023年(令和5年)時点で1160.2万人おり人口の約9.2%です。
障害者の割合は年々増加傾向にあり、それに比例して障害福祉サービスの予算額も拡充されています。
障害のある人も地域の一員としてともに生きる社会づくりを目指して、厚生労働省をはじめ多くの組織・団体が自立や社会参加を支援する制度を採用し、障害者の受け入れ態勢を強化しているわけです。
普通の生活を送る上で治療をはじめ補装具やバリアフリー装置が必要な障害者は、健常者よりも費用がかかります。
各種手帳や受給者証の交付を受けている人は、あらゆる障害者割引・優遇制度を有効に活用して経済的な負担を和らげることが可能です。
施設やサービスによっては付き添いの同行者も割引になりますので、趣味や娯楽、旅行など外出の機会を増やして遊びや学びを充実させていきましょう。
そして健常者も、障害者が経済面や機会の不平等にならないように国や自治体、民間企業が導入した障害者割引について理解を深めていただけたら幸甚です。
以下の記事では、社会に参加する上で生じる4種類のバリアと心のバリアフリーの重要性について解説していますので併せてお読みください。
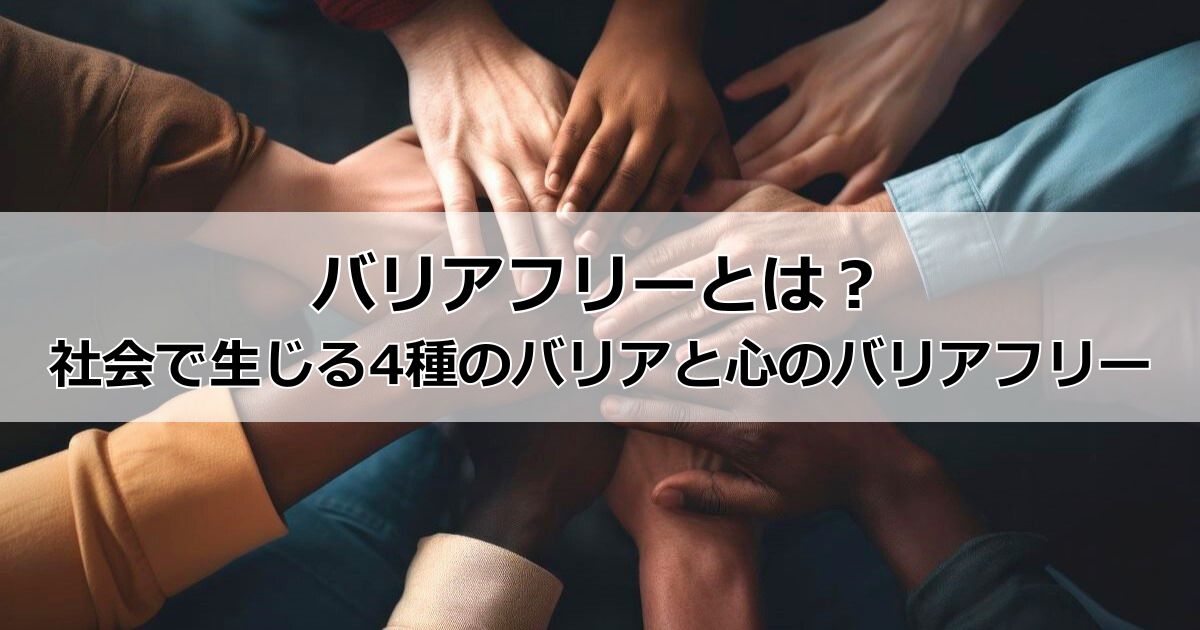






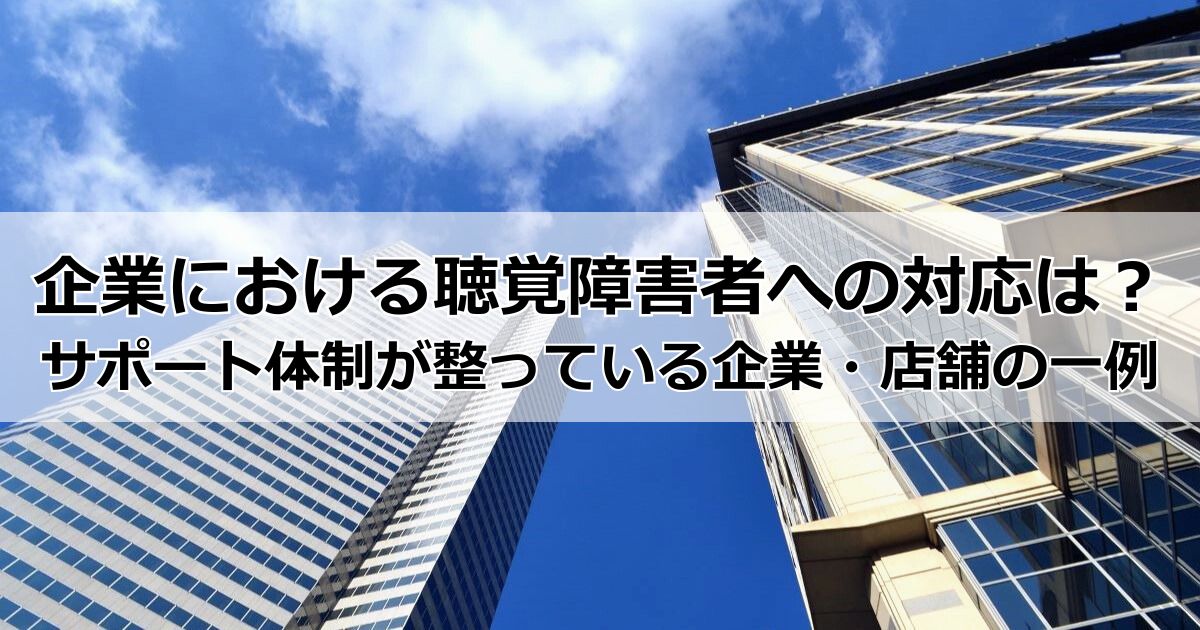
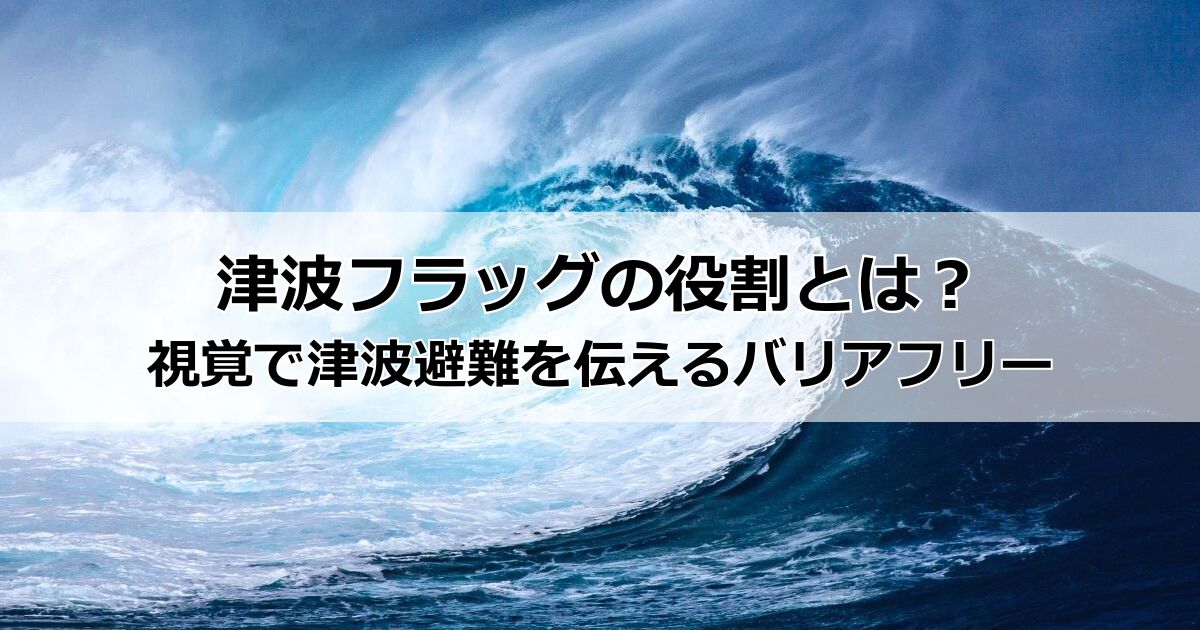
コメント