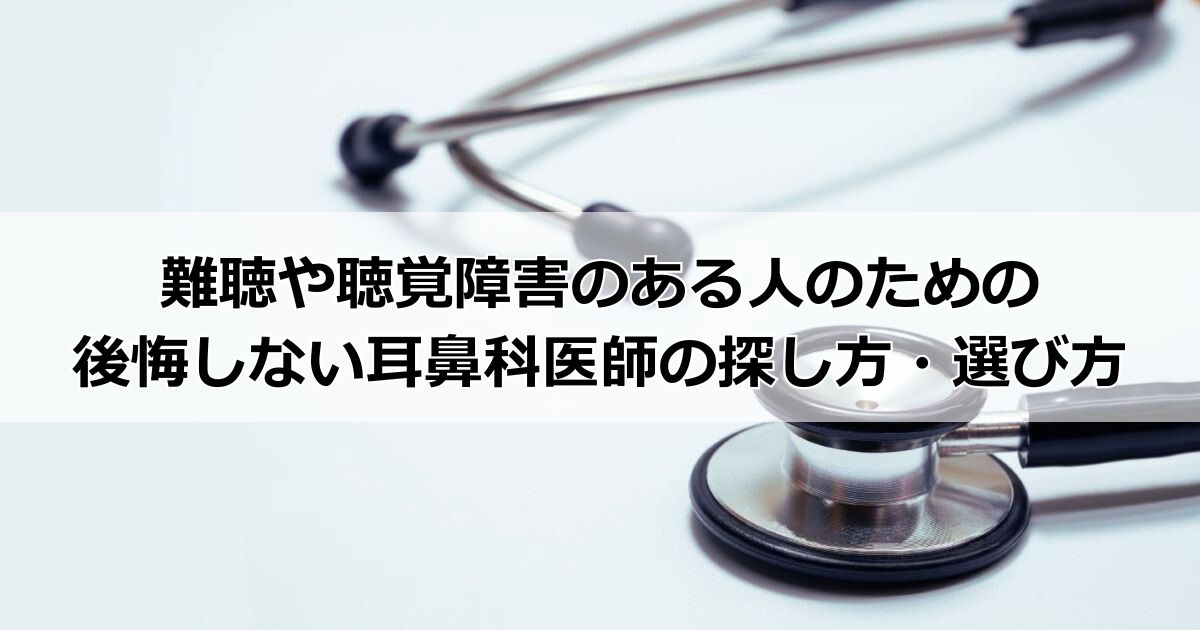
難聴や聴力の低下を感じ始めた時、まず耳鼻咽喉科の病院やクリニックを受診することになります。
しかしどういった医療機関を選んだほうがいいのか、どの医師に診察してもらったほうが安心なのか悩む人も多いでしょう。
通院のしやすさは当然優先したいところですが、途中で病院を変えることは避けたいですし後々後悔することのないように病院や医師を選びたいものです。
難聴や聴覚障害を専門にする医師を見つけるためには、指定医・補聴器相談医・補聴器適合判定医の資格をもっていることが目安になります。
この記事では、筆者の経験から耳鼻科医を受診する際の探し方や選び方をポイント解説しますので参考にしてください。
耳鼻科と耳鼻咽喉科について
耳鼻科というと耳と鼻を専門とする医療機関だと思われがちですが、正式には耳鼻咽喉科・頭頸部外科という名称です。
多くの病院やクリニックでは簡略化して耳鼻咽喉科と設定していますが、主に耳・鼻・口・喉や食道の一部を専門としています。
耳鼻咽喉科の医師による診療内容は、主に以下の通りです。
| 部位 | 主な症状 |
|---|---|
| 耳の症状 | 中耳炎や外耳炎、耳鳴り、難聴、めまいなど |
| 鼻の症状 | 鼻水や鼻づまり、花粉症、アレルギー性鼻炎など |
| 喉の症状 | 喉の痛みや喉の違和感、扁桃炎、気管支炎など |
また目を除く顔面、頸椎以外の首の病気、めまいやいびきなど鎖骨から上にあたる診療も行っています。
医師の専門分野や院内の医療設備によっては、以下のように細部にまで診察することが可能です。
- 聴覚・嗅覚・味覚・平衡感覚を扱う感覚器
- 摂食嚥下や発声・音声機能などの障害
- 鼻副鼻腔腫瘍や甲状腺腫瘍など頭頸部腫瘍の診療
耳鼻咽喉科の基本的な探し方ポイント
耳鼻咽喉科の医療機関を受診する時の基本的な探し方ポイントは、以下の通りです。
- 通院のしやすさ
- 待ち時間と予約システム
- 医療設備の充実さ
通院のしやすさ
耳・鼻・喉の痛みや違和感などの症状が生じた場合に、誰もが優先的に考えるのが通院のしやすさでしょう。
中耳炎や外耳炎といった外傷、耳鳴りやめまいといった耳内部の問題などは症状が治まるまでに時間がかかるため定期的な通院が必要です。
そのため自宅から近いか、駅から徒歩圏内か、通学・通勤路で寄り道できるかなど個々によって違いはあるものの通院のしやすさは病院選びの重要なポイントになります。
まずは、お住まいの近くにある耳鼻咽喉科の病院やクリニックを探してみてください。
気になる医療機関を見つけたら、公式サイトなどで専門とする部位や診察内容、医療設備の有無など必要な条件に応じて選ぶことが大切です。
待ち時間と予約システム
病院で受付をしてから診察までの待ち時間が長いほど評判が高い表れですが、目安として30分を超えてしまうと待ち時間が長い病院というイメージがついてしまいます。
待ち時間があまりにも長いと病院では対策を考える必要があるため、一部では予約システムを導入している病院も多いです。
耳鼻咽喉科ではありませんが、筆者が利用する内科のクリニックではインターネットによるオンライン受付が導入されているため受付番号を取得できるようになっています。
インターネット上では診察中の受付番号と診察待ちの受付番号、そして待機人数がリアルタイムで更新されるため自分の受付番号が近くなったら来院しています。
また次回診療の予約に時間指定がある医療機関は、時間帯に対する人数調整を行っているということですので待ち時間も比較的少なめで安心です。
筆者が定期通院している耳鼻咽喉科の病院でも、次回の来院予約で診療日と診療時間が設定されているため待ち時間が比較的少なくて助かっています。
医療設備の充実さ
例えば難聴や聴力低下に関わる症状の場合は聴力検査を受けることがあるため、聴力検査ができる医療設備が整っている病院やクリニックを探したほうがいいです。
聴力における診察にはオージオメーターやインピーダンスオージオメーター、耳音響放射検査装置などがあり、それぞれの聴力検査機器については後述します。
お住まいの近くに耳鼻咽喉科の病院やクリニックがある場合は、公式サイトなどで難聴の症状にも診察の対応をしているか聴力検査ができる医療設備が整っているかを確認しましょう。
近くになければ、通学・通勤ルートや近隣の駅など範囲を広げてみてください。
筆者は耳内の炎症や違和感がある時は近くのクリニックを利用していますが、難聴をはじめ聴力・聴覚障害、補聴器に関する検査には都心にある大学病院と連携しているクリニックを受診しています。
難聴の診察に必要な聴力検査装置
難聴や聴力の低下を感じた場合、受診する予定の病院やクリニックに聴力検査ができる装置が設備されているかを確認することも病院選びの判断材料になります。
聴力・聴覚に関する聴力検査装置は、主に以下の通りです。
- オージオメーター
- インピーダンスオージオメーター
- 耳音響放射検査装置
オージオメーター
オージオメーターは、電気的に発生した検査音を与え受診者自身の認知や応答によって聴覚機能を検査する装置です。
聴力・聴覚の測定に必要な検査音を出す本体とその検査音を受診者に提示するヘッドホンに似た受話器があり、受診者の聴力状態を確認するための応答用押しボタンスイッチを備えています。
受診者の耳内に検査音を提示し、それに対する応答を確認することにより受診者の聴覚機能を測定するわけです。
検査音にはいくつかの種類があり、筆者は通常の音や雑音が入った音を聞き分ける検査とあいうえおといった母音を読解する検査をしています。
インピーダンスオージオメーター
インピーダンスオージオメーターは、外耳道や中耳の音響インピーダンスを測定することで伝音機構の機能を検査する装置です。
インピーダンスとは交流回路での電気抵抗を表す指標で、外耳から与えて跳ね返ってきた音を測ることでどれだけの音が鼓膜や中耳を通っていったかを測定できます。
インピーダンスオージオメーターには、大きく分けてチンパノメトリーとレフレックスという2つの検査機能があります。
チンパノメトリー検査は鼓膜・耳小骨の振動(動き具合)といった中耳の状態を、レフレックス検査は顔面神経の障害がどこで発生したかなどを調べることができ、両方の測定を連続して行うことが可能です。
耳音響放射検査装置
耳音響放射検査装置(OAE検査装置)は、耳奥の神経細胞から発生するかすかな音を測定して内耳の機能を検査する装置です。
難聴の人や小児の聴覚、高齢の人に多い加齢性難聴の検査などに用いられます。
他にも耳鼻咽喉科では平衡障害やめまいなどの症状で平衡機能を測定する重心動揺計などがありますが、この記事では聴力・聴覚を中心としているため省略します。
難聴に関する耳鼻咽喉科の選び方ポイント
難聴や聴力の低下を感じた時の受診は、基本的に前述通り通院のしやすさや医療設備の充実さなどを考慮して探すのがおすすめです。
しかし難聴の症状が進行して、例えば行政機関による判定や補助を受けるための申請・手続きが必要になった時には耳鼻咽喉科医の中でも専門医としての資格をもつ医療機関を受診することが重要になります。
耳鼻咽喉科の医師における専門医の種類は、以下の通りです。
- 指定医
- 補聴器相談医
- 補聴器適合判定医
指定医であること
指定医にはさまざまな種類があり、難聴や補聴器など聴覚に関わる医師の場合は身体障害者福祉法第15条の指定医を指します。
詳しくは別記事で説明しますが、指定医は身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書や意見書を作成する医師のことです。
難聴や聴力低下の症状が進行した場合に、身体障害者に該当すると診断されることがあります。
その身体障害者を証明する手帳の交付申請に必要な診断書や意見書を記入してもらうためには、受診している耳鼻咽喉科の医師が指定医であると手続きがよりスムーズです。
また高額な補聴器を購入するにあたって補装具費の支給を受ける場合、申請するのに必要な診断書や意見書も指定医に記入してもらうことになります。
身体障害者手帳の交付や補装具費の支給に関する申請・流れについては、別記事で紹介します。
補聴器相談医であること
補聴器相談医は、聴力レベルや補聴器の必要可否などを診断し適正な補聴器を利用できるように指導を行う医師です。
2018年より、医療機器でもある補聴器の購入費用も医療費控除の対象となりました。
しかし補聴器を購入したからといって、全ての人が医療費控除の対象になるわけではありません。
また補聴器を購入した際に補聴器販売店から受け取った領収書だけでは医療費控除の申告はできません。
補聴器の購入費用を医療費控除で申告できるためには、補聴器相談医に診療情報提供書を発行してもらう必要があります。
もし耳鼻咽喉科の医師に補聴器の装用を勧められた人は、その医師も補聴器相談医である可能性が大きいため問題ないと考えられますが、念のため確認しておくことをおすすめします。
補聴器の購入費用を医療費控除で申告する条件や手順などについては、別記事で紹介します。
補聴器適合判定医であること
補聴器適合判定医は補聴器相談医の上位互換にあたるため、必ずしも選ぶ必要がありませんが補聴器適合検査が実施できる医師です。
補聴器を使っている人が補聴器を適切に使用しているか、調整が適切であるかなどを確認します。
各種申請・手続きの対応一覧表
各種申請・手続きにあたって対応する専門医を一覧表にしましたので、下記表を参考にしてください。
| 申請・手続きの種別 | 対応する専門医 |
|---|---|
| 身体障害者手帳の交付 | 指定医 |
| 補装具費支給の申請 | 指定医 |
| 補聴器購入費用の医療費控除 | 補聴器相談医 |
| 補聴器選びの相談 | 補聴器相談医 |
| 補聴器適合検査 | 補聴器適合判定医 |
補聴器を購入する際の販売店や資格者については、別記事で紹介します。
筆者が利用している病院・クリニックについて
筆者の現在の担当医は、かつて勤務していた会社の診療所に派遣されていた医師です。
大学病院の耳鼻咽喉科医であり、元勤務先を退職する時に大学病院への紹介状を書いてくれました。
担当医は耳鼻咽喉科医というだけでなく、同時に指定医でもあります。
そのため障害等級が上がるという診断とともに身体障害者手帳を更新していただいたり、補聴器購入費用の支給における必要書類を記入していただいたりするなど一連の申請・手続きが1人の担当医で行うことが可能です。
また補聴器相談医でもあったことから補聴器メーカーの特徴や性能も熟知しており、別のメーカーに変更することになった時も紹介状を書いてもらうことになっています。
ただし都心にある病院までいくのもたいへんなため、耳内の炎症や違和感があった場合は自宅近くの耳鼻咽喉科を利用しています。
ちなみに筆者が難聴であることと身体障害者手帳の交付を教えていただいた最初の担当医は、故郷の厚生連病院に在籍していた言語聴覚士でした。
このように難聴や聴力の低下を感じ始めた時に受診する医療機関には、前述で紹介した専門医の資格をもつ耳鼻科の医師を選ぶようにしてください。
耳鼻咽喉科医の選び方まとめ
耳・鼻・喉の違和感や症状で耳鼻咽喉科のかかりつけ医を見つけることは、そんなに難しいことではありません。
しかし難聴の人や聴覚障害者に相当することになったら、万が一のことを考えた時に必要な申請や諸手続きはできるだけスムーズに行いたいものです。
もし、難聴や聴力の低下を感じ始めたら。
将来的に難聴の進行や悪化することを想定して、身体障害者手帳の交付や補装具費の支給など諸手続きがしやすい専門医のいる医療機関を決めておくなど日常生活を安心して過ごせるように準備していきましょう。


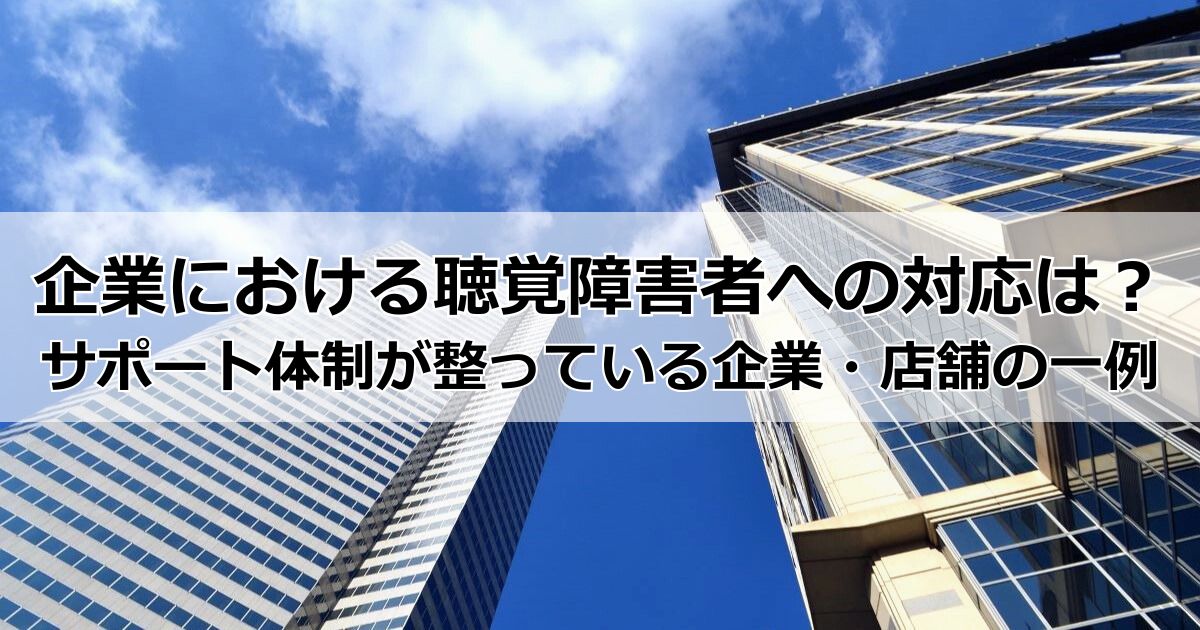
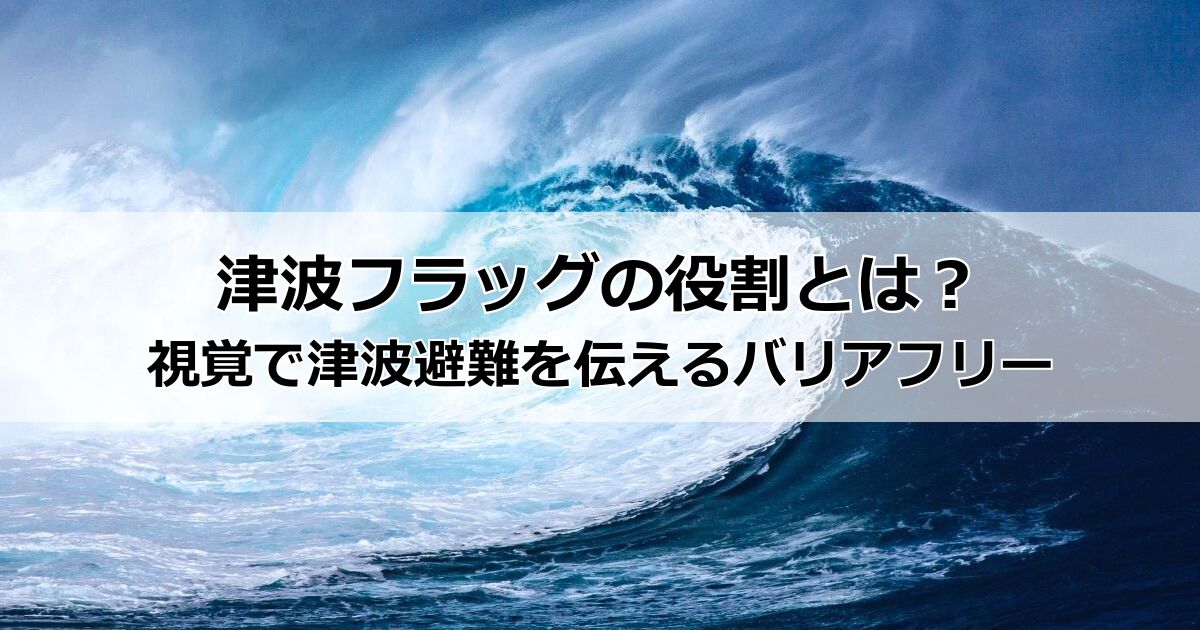

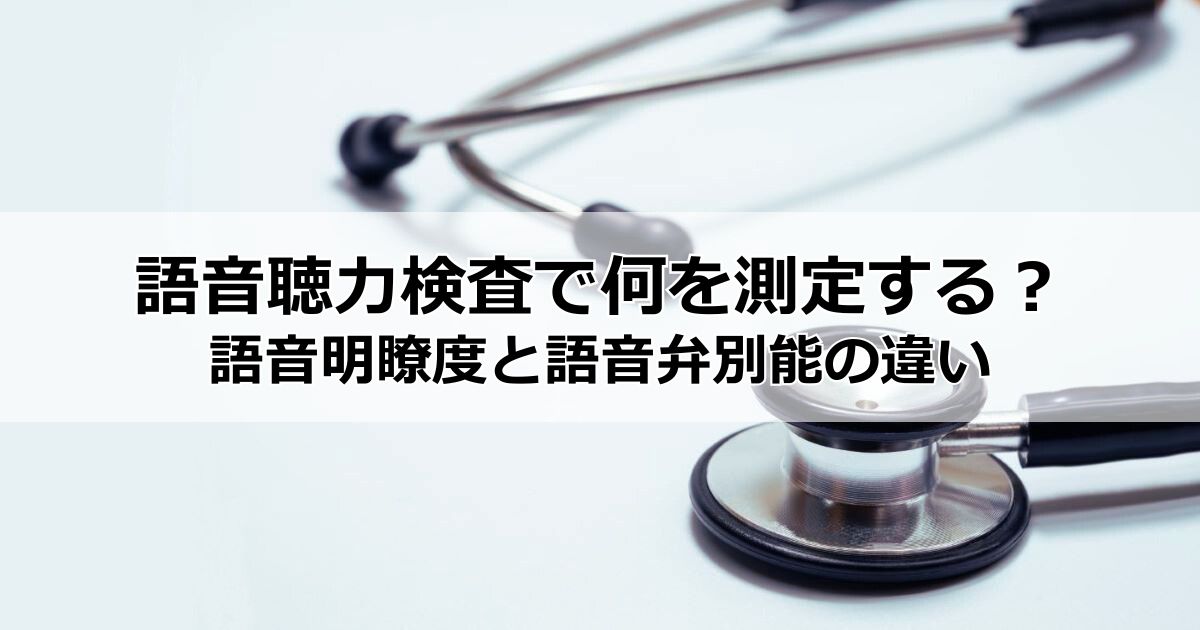
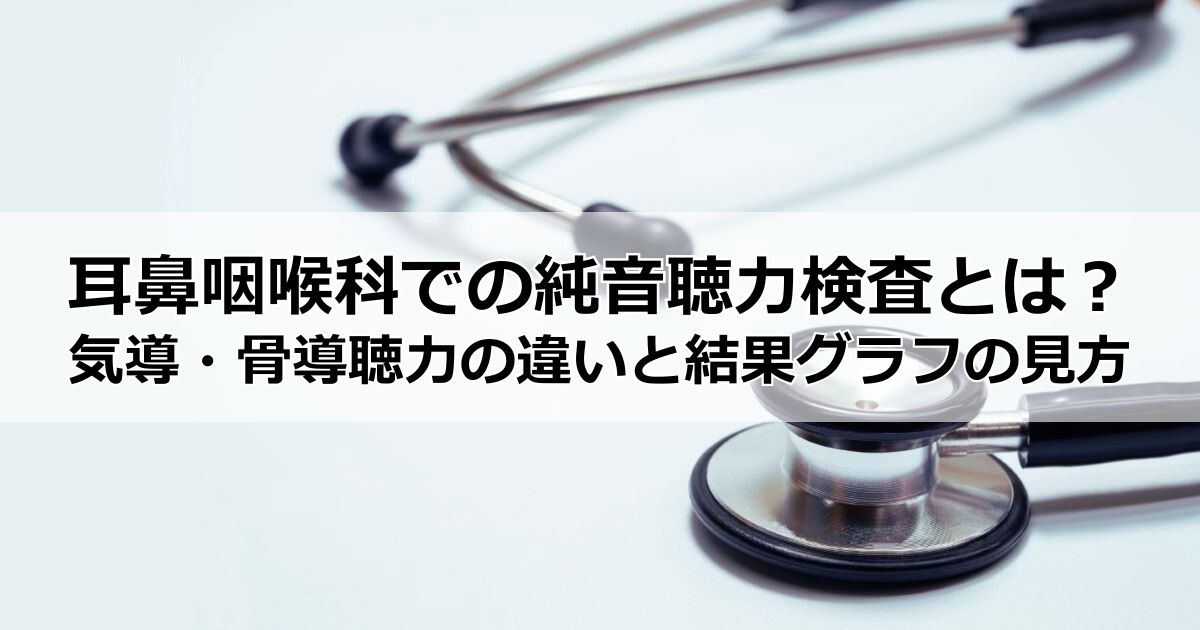
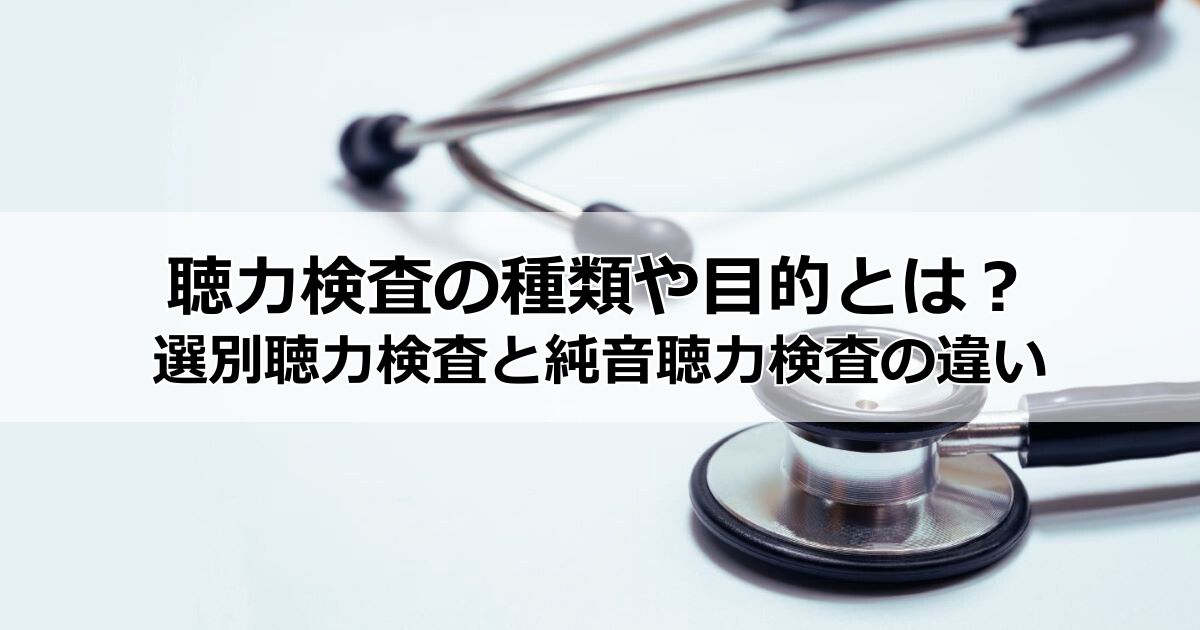
コメント