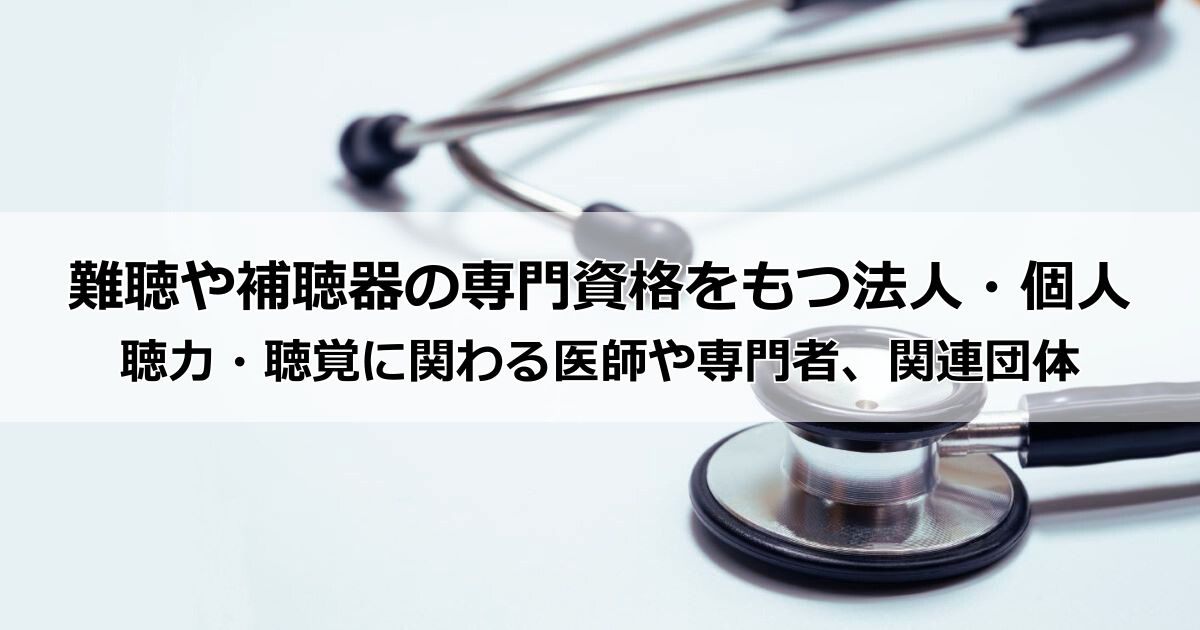
難聴や聴力低下を感じ始めたり、補聴器の利用が必要なのかわからなかったりした時。
聴力・聴覚を専門とする医師をはじめ、医療機器である補聴器を取り扱うことのできる資格をもつ法人・個人をご存知でしょうか。
また専門医や技能士を認定したり難聴に関する認知を広めたり、補聴器の補助制度を設定したりする法人や団体もあります。
聴力・聴覚を専門にする医師はどういう役割があるのか、難聴や補聴器に精通していることを示す資格とはどんなものなのか。
難聴や聴力・聴覚に特化した医師から、補聴器を専門に取り扱う資格所持者や関連団体を紹介します。
聴力・聴覚を専門とする資格所持者や法人・団体一覧
難聴や補聴器など聴力・聴覚を専門に活動する資格所持者や関連法人・団体は、以下の通りです。
難聴や補聴器に関する医師
- 耳鼻咽喉科医
- 補聴器相談医
- 補聴器適合判定医
- 指定医(15条指定医)
難聴や補聴器の専門資格をもつ法人・個人
- 認定補聴器専門店
- 認定補聴器技能者
- 言語聴覚士
難聴や補聴器に関する関連団体(法人)
- 公益財団法人テクノエイド協会
- 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会
- 一般社団法人日本聴覚医学会
- 一般社団法人日本補聴器工業会
- 一般社団法人日本補聴器販売店協会
- 特定非営利活動法人日本補聴器技能者協会
次項からは、聴力・聴覚専門の資格所持者や法人・団体それぞれの特徴や役割を説明します。
耳鼻咽喉科医(耳鼻科医)
耳鼻咽喉科医は、めまいや耳鳴り、アレルギーなどの内科的な治療と副鼻腔や耳の内部、扁桃などの外科的な治療の両面で診療を行う医師です。
幅広い知識や技術が求められる専門医として聴こえの相談はできますが、補聴器を購入するまでの指導は医師によって異なります。
詳しくは後述しますが、難聴や補聴器を用いた専門的な医療に関われるのは日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会から委嘱された補聴器相談医です。
耳鼻咽喉科医と補聴器相談医の違い
耳鼻咽喉科の医師は、中耳炎や鼻炎、のどの感染症など耳・鼻・喉に関連する幅広い専門知識をもってる医師です。
一方で補聴器相談医は、難聴の状態を判断し補聴器を必要とする人により専門的なサポートを提供する役割があります。
そのため難聴や聴力の低下により補聴器が必要なのか疑問に感じ始めたら、補聴器相談医としても認定されている耳鼻咽喉科医への相談がおすすめです。
補聴器相談医
補聴器相談医は、聴力レベルや補聴器の必要可否などを診断し難聴や聴力の悪い人が適正な補聴器を利用できるように指導を行う医師です。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(日本耳鼻咽喉科学会)により認定された医師を指し、当学会が規定する講習・実習カリキュラムのすべてを履修した日本耳鼻咽喉科学会専門医に対して学会理事長が委嘱を行っています。
また6年ごとに決められた講習を受講し、資格を更新する必要があります。
補聴器相談医は、難聴や聴力低下を感じている人に耳の状態を診察したり聴力検査を行ったりして難聴の種類やレベルを判断します。
治療できない難聴については補聴器の必要性や認定補聴器専門店の紹介をするほか、補聴器購入後も聴力の経過観察や補聴器の調整が適正に行われているかなど通常の耳鼻咽喉科の診察に加えて補聴器の相談が可能です。
補聴器相談医は、2024年12月時点で約5,000名が認定されています。
日本耳鼻咽喉科学会の公式サイトで、補聴器相談医の名簿を公開していますので参考にしてください。
参考:補聴器相談医の名簿公開について(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)
補聴器適合判定医
前述の補聴器相談医とは別に、補聴器適合判定医という医師もいます。
補聴器適合判定医は、厚生労働省が指定する補聴器適合判定医講習会を修了した耳鼻咽喉科医です。
簡潔にいうと補聴器相談医の上位互換にあたり、補聴器適合判定医が一定の施設基準を満たすと補聴器適合検査が実施できます。
すでに補聴器を使っている人が補聴器を適切に使用しているか調整が適切であるか、補聴器装用後の効果・改善度を評価したり補聴器の調整状態を確認したりします。
指定医(15条指定医)
指定医とはいってもさまざまな種類がありますが、難聴や聴力低下、補聴器の装用など聴覚に関わる医師を表す場合は身体障害者福祉法第15条の指定医を指します。
身体障害者福祉法第15条の指定医とは、身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。
医療機関が所在する都道府県知事(指定都市長、中核市長)が、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会、その他の合議制の機関の意見を聞いた上で行われます。
身体障害者福祉法第15条の指定医要件
指定医は、病院または診療所において各障害区分(申請しようとする障害区分)ごとに関係のある診療科で診療に従事し、原則として5年以上の臨床経験(平成16年4月から必修化された新医師臨床研修制度の2年間の研修を除く)を有する者で、身体障害者の福祉に理解を有する者であることが必要です。
例えば、聴覚障害の場合は以下の診療科に関わる要件があります。
- 耳鼻咽喉科
- 小児耳鼻咽喉科
- 気管食道・耳鼻咽喉科
- 脳神経外科
- 神経内科
認定補聴器専門店
認定補聴器専門店は、厚生労働省の関連団体である公益財団法人テクノエイド協会に認定された補聴器専門店です。
補聴器の選定や調整などに必要な機器や設備について当協会の審査基準をクリアした店だけに与えられる資格で、認定補聴器専門店であることを示す認定証書や認定プレートが交付されます。
また、5年ごとに認定時と同様の厳正な更新審査を受けることが義務づけられています。
認定補聴器技能者の在籍が必須
認定補聴器専門店には、人的要件として認定補聴器技能者が常駐していることが必須です。
店舗の構造・設備
認定補聴器専門店には利用者の相談対応や必要な測定、調整などを行うのに適切な構造・設備が整っていることが求められます。
設備・器具の整備
認定補聴器専門店には、以下の通り性能を十分に発揮できる設備・器具を整備していることが要件です。
- 補聴器を調整するための測定ができる設備
- 補聴器の特性を測定できる設備
- 補聴器を装用することによる効果測定のための設備
- 補聴器の故障や修理に対応できるための設備・器具
- イヤモールドやシェルの補修や修正のための加工設備・器具
- 補聴器を消毒するための設備
業務を実施する上での留意事項
認定補聴器専門店は、以下の通り業務を実施する上で留意すべき事項が定められています。
(1)補聴器技能者の指導・監督のもとで行われていることや店舗や業務運営について適切な衛生管理を行っていること
(2)補聴器の購入を検討している人への難聴の症状、使用目的、使用環境などに対応できる各種の補聴器を揃えておくこと
(3)認定補聴器技能者が常駐していることにより補聴器に関する相談への対応をはじめ、種類や機種の選定、調整するための測定などを行うこと
(4)補聴器の購入者ごとに販売・修理した機種や実施した調整などに関する記録を作成すること
(5)販売した補聴器に必要な調整や苦情などアフターケアを適切に対応すること
(6)補聴器の修理を行う場合は、医薬品医療機器等法(略称)に基づく補聴器修理業の許可を得ていることと責任技術者が常勤していること
(7)日本耳鼻咽喉科学会が認定する補聴器相談医と連携して事業を行うことを原則としています。
他にも誇大広告や通信販売など不適切な販売活動、社会的信頼を損なう行為を行わないことが必須で、利用者が安心し信頼して相談できる店が求められています。
全国の認定補聴器専門店について
認定補聴器専門店は、国内に977店舗あります(2024年4月時点)
全国各地の認定補聴器専門店については、下記サイトで調べることが可能ですので参考にしてください。
認定補聴器技能者
認定補聴器技能者は、補聴器に関する一定の知識・技能をもち調整や販売を適切に実施できると認められた人に与えられる専門資格です。
公益財団法人テクノエイド協会が行う認定補聴器技能者試験に合格する必要があり、資格を取得すれば永続的に有効ではなく5年ごとに更新審査を受けることが義務づけられています。
補聴器の取扱いを専門とする唯一の資格制度であり、資格を保有しているということは補聴器の専門家であることを意味します。
認定補聴器技能者は、4,835人が登録されており公共財団法人テクノエイド協会が認定しています(2024年12月時点)
認定補聴器技能者の役割
認定補聴器技能者は補聴器に特化した資格をもつ専門家のため、聴こえや補聴器に関する専門的な知識・技能が備わっています。
最新の機種も含め補聴器に関する知識も豊富なため、使う人に合った補聴器を的確に提案してもらえる点が大きなメリットです。
また、耳鼻咽喉科の医師と連携して対応できる点もメリットの1つです。
認定補聴器技能者が対応できる内容は、以下の通りです。
- 補聴器を1人ひとりの聴力状態に合わせて調整し、より快適な聴こえを追求する
- テレビや電話、会話が聞きづらい時の相談
- 難聴や聴力低下に悩む人の聴こえや補聴器購入に関する相談
- 公的支援のアドバイスや情報提供
- 耳鼻科医師と連携した対応
認定補聴器技能者の合格者
認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が行う認定補聴器技能者試験に合格した人です。
| 年度 | 養成課程講習会修了者(第Ⅰ期) | 認定補聴器技能者試験結果(合格率) |
|---|---|---|
| 2019年度 | 649名 | 83.1% |
| 2020年度 | 605名 | 82.0% |
| 2021年度 | 588名 | 84.2% |
試験の合格率は、近年約82~85%で推移しており比較的高い合格率ですが、だからこそ油断はできないことを表します。
認定補聴器技能者になることができれば販売者としてのキャリアアップ、会社・店舗における地位、耳鼻科医・消費者・ユーザーからの信頼度が確実に向上します。
認定補聴器技能者は5年間の有効資格が認められ、補聴器の安全で効果的な補聴器販売業務に従事します。
その5年間の資格有効期間内にその知識と技能の向上、業務運営の改善を目的とするために講習会を受講することが必須です。
言語聴覚士
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事に問題がある人を支援する目的で、1997年に制定された言語聴覚士法という法令で定められる国家資格です。
言葉によるコミュニケーションには失語症や聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害など多岐にわたります。
専門領域は聴覚のほか言語・音声・呼吸・認知・発達・摂食・嚥下など広範囲にわたり、病気や交通事故、発達上の問題などで機能が損なわれることもあります。
医療・介護・福祉・保健・教育など幅広い領域で活動する言語聴覚士は、対処法を見出すために検査・評価を実施し必要に応じて訓練や指導、助言、その他の援助を行う専門職です。
コミュニケーションの面から自分らしい豊かな生活を構築できるように、言葉や聴こえの問題をもつ人と家族を支援します。
公益財団法人テクノエイド協会
公益財団法人テクノエイド協会は、義肢装具士国家試験などを実施する公益法人です。
福祉用具に関する調査研究や開発、福祉用具情報の収集・提供、福祉用具の臨床的評価事業、ISO(国際標準化機構)に関する国内審議団体としての事業、JIS(日本工業規格)の原案作成団体としての事業などを行っています。
福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士にかかわる試験事務なども実施しており、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者および障害者の福祉の増進に寄与することが目的です。
以前は厚生労働省の所管でしたが、公益法人制度改革に伴い2011年に公益財団法人へ移行しました。
認定補聴器専門店の認定
補聴器専門の販売店として適しているのか、認定補聴器専門店を認定しているのもテクノエイド協会です。
当協会では認定補聴器専門店を認定するために、認定補聴器技能者が常駐しているか、補聴器を購入するために必要な設備が完備しているか、利用者が安心し信頼して相談できるかなどの条件を満たしているか審査します。
認定補聴器技能者の認定
テクノエイド協会が実施する認定補聴器技能者の資格は、医師や看護師などのような国家資格ではなく民間資格です。
補聴器相談医の診断・指導に基づき、適切な補聴器販売をするために必要な補聴器に関する知識および技能を修得したと認定して付与する資格で取得するまでには最短でも4年かかるとされています。
公式サイト:公益財団法人テクノエイド協会
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会
日本耳鼻咽喉科学会は、正式名称が日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会で、耳鼻咽喉科医師で構成された団体です。
耳鼻咽喉科専門医や補聴器相談医の育成、補聴器キーパーソン制度など耳鼻咽喉科学に関する学術文化の発展・普及を目的として1893年に設立されました。
耳鼻咽喉科は耳、鼻、口腔・咽頭、喉頭、気管、食道、頭頸部と広範囲にわたって新生児から老人まで多彩な疾患の診療・研究を行っており、学問・研究の推進および新しい診断・治療法の確立に努め国民の健康と医療の将来に貢献しています。
公式サイト:一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会
一般社団法人日本聴覚医学会
日本聴覚医学会は、聴覚およびその障害に関する研究の進歩と発展を図る目的で、1951年に発足した団体です。
当初は難聴研究会として設立された後、1956年に日本オージオロギー学会、1959年に日本オージオロジー学会、1988年に現在の日本聴覚医学会と改称しました。
耳鼻咽喉科の医師と聴覚医学分野の研究に従事する人で構成され、補聴器適合検査の指針など聴覚と聴覚障害に関する研究の進歩と発展のために活動しています。
毎年3月3日を耳の日に設定したのも、日本聴覚医学会です。
会員数は、2024年5月時点で約2,600人が登録しています。
公式サイト:一般社団法人日本聴覚医学会
一般社団法人日本補聴器工業会
日本補聴器工業会は、国内における補聴器の適正な供給や普及促進を目指しさまざまな問題の解決や関連する事業の推進を中心に活動することを目的に、1988年に設立された団体です。
補聴器の製造メーカーで構成され、補聴器の普及・啓発や難聴者のニーズに合った良質な補聴器の供給体制を確立し、難聴者の社会参加を支援しています。
数年に1度、難聴や補聴器における実態調査「JapanTrak(ジャパントラック)」を実施しています。
日本補聴器工業会の加盟メーカー
日本補聴器工業会は、日本国内で補聴器を製造・輸入・販売している団体を指します。
国内における補聴器の流通と促進を目指して活動しており、国内で補聴器として製造・販売できるのは日本補聴器工業会に加盟していることが基準です。
現在、日本補聴器工業会に加盟しているメーカーは11社あり、そのうち外国製は7社、日本製は4社になります。
| ブランド名 | メーカー名=経営会社 | 拠点 |
|---|---|---|
| フォナック | (ソノヴァ) | スイス |
| シグニア | (WSオーディオロジー) | ドイツ・シンガポール |
| オーティコン | (デマント) | デンマーク |
| ワイデックス | (WSオーディオロジー) | デンマーク |
| リサウンド | (GNヒアリング) | デンマーク |
| スターキー | アメリカ | |
| ニュージャパンヒヤリングエイド | アメリカ | |
| コルチトーン | 日本 | |
| リオネット | (リオン) | 日本 |
| パナソニック | 日本 | |
| マキチエ(旧:キコエ) | 日本 |
一方で、日本補聴器工業会に加盟していないメーカーは7社です。
日本補聴器工業会の加盟・非加盟メーカーについては、別記事で紹介します。
JapanTrak(ジャパントラック)について
JapanTrak(ジャパントラック)は、日本補聴器工業会が公益財団法人テクノエイド協会の後援と欧州補聴器工業会(EHIMA)の協力を得て、日本国内の約15,000人を対象に聴こえの不自由さや補聴器の使用状況など実態調査を実施している市場データです。
欧州各国や中韓など世界16ヵ国が進めている国際調査「ユーロトラック」の日本版ともいわれ、2012年・2015年・2018年・2022年に行われました。
最新で実施されたJapanTrak 2022の目的は、国内における聴こえと補聴器を取り巻く現在の諸問題を抽出し、欧米諸国の一部データとの比較も行いながら全難聴者の生活の質(QOL)が向上できるよう対策を検討し提案することでした。
公式サイト:一般社団法人日本補聴器工業会
一般社団法人日本補聴器販売店協会
日本補聴器販売店協会は、全国の補聴器販売店で構成された団体です。
47都道府県部会9支部で組織化された補聴器販売事業者は、関連団体との連携のもとに補聴器の適正な供給と普及を通して聴こえで困っている難聴者に対する福祉への寄与を目的に活動しています。
また認定補聴器技能者による対面販売と資格者在籍の義務化の実現など、経営品質の維持・向上を目指しています。
公式サイト:一般社団法人日本補聴器販売店協会
特定非営利活動法人日本補聴器技能者協会
日本補聴器技能者協会は、公益財団法人テクノエイド協会の補聴器技能者育成事業への協力活動を行う団体です。
認定補聴器技能者で構成され、難聴者に対し適切な補聴器適合技術が駆使されるように専門知識と技能をもつ補聴器技能者を育成するために、関係する職域・組織の方々との協力・連携を緊密に保ちながら活動しています。
一般消費者への補聴器に対する知識の普及活動として、合理的な補聴器の選択・供給のための活動も行っています。
公式サイト:特定非営利活動法人日本補聴器技能者協会
聴力・聴覚に精通した専門資格者まとめ
聴力・聴覚において必要な専門知識や技術をもつ法人や個人。
1人ひとりの難聴の程度や聴こえの状態を改善できるように多くの資格所持者や専門店、関連団体が存在しています。
補聴器が必要か疑問に感じた時は、耳鼻咽喉科の中でも補聴器に特化した補聴器相談医を訪ねるのが効率的です。
また補聴器が必要となった時、高価な医療機器を安心して購入するために公的に認定された技能者が在籍している認定補聴器専門店を利用したほうがスムーズで確実な機種を使うことができます。
難聴や聴力低下を感じている人や補聴器の装用に悩んでいる人も含め、上記で紹介した専門資格所持者や団体を意識して利用してください。


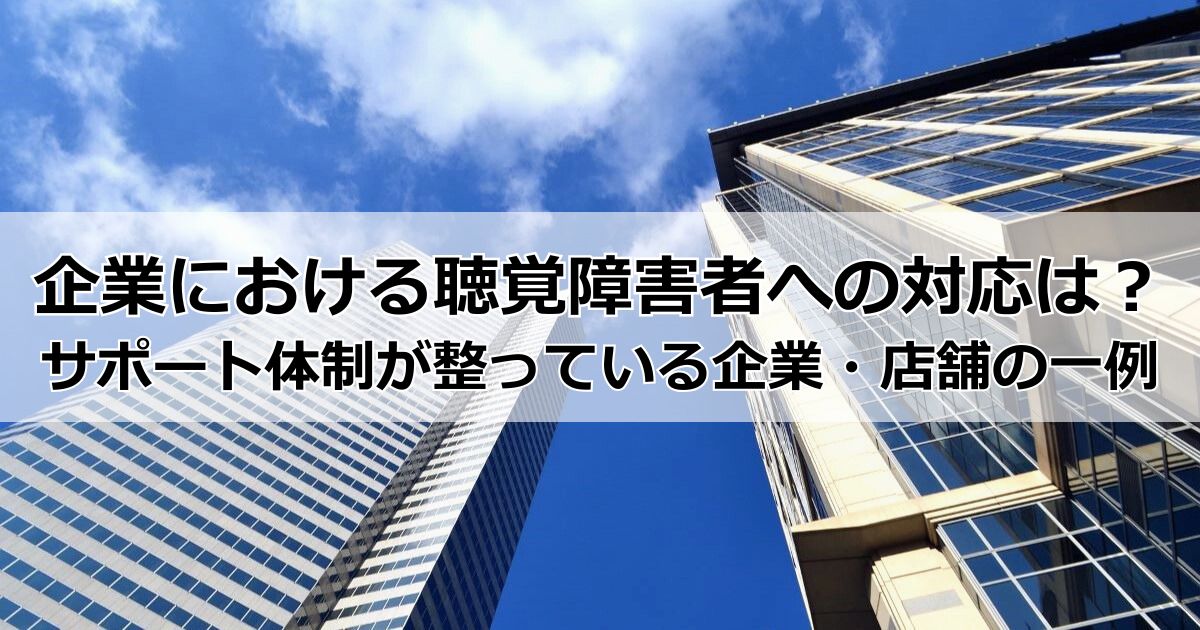
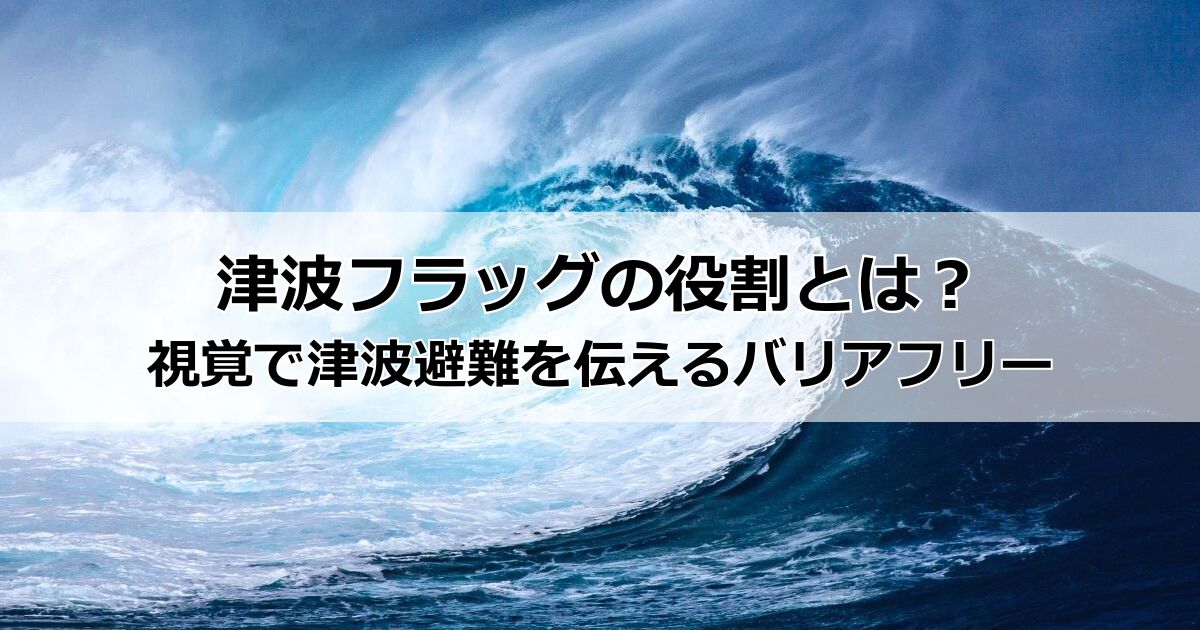

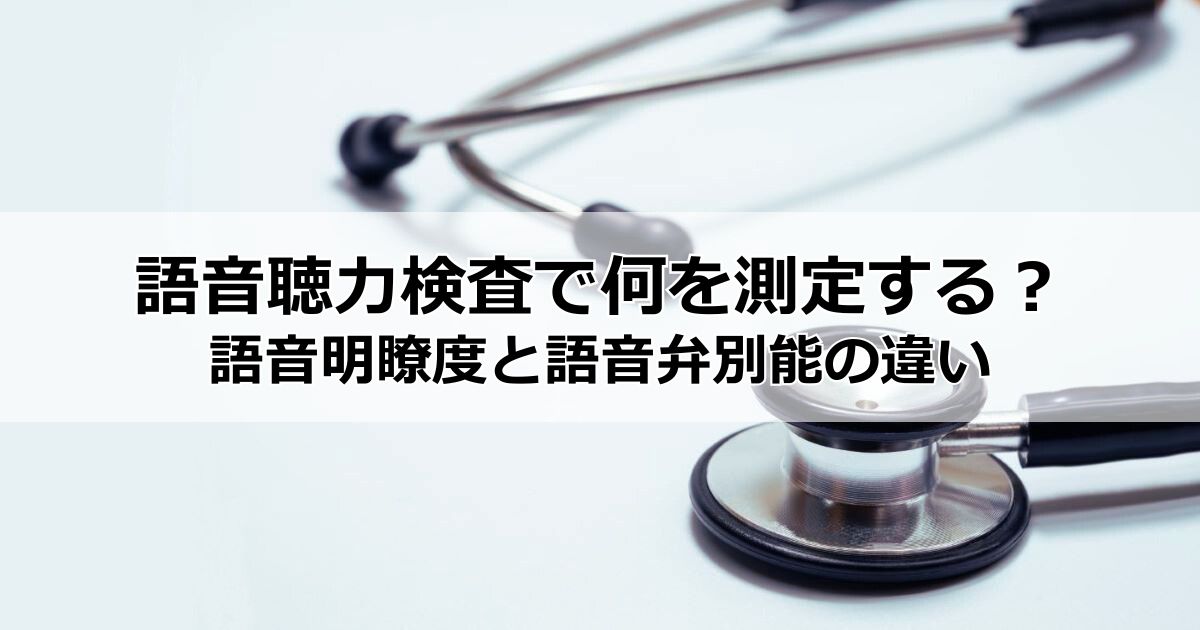
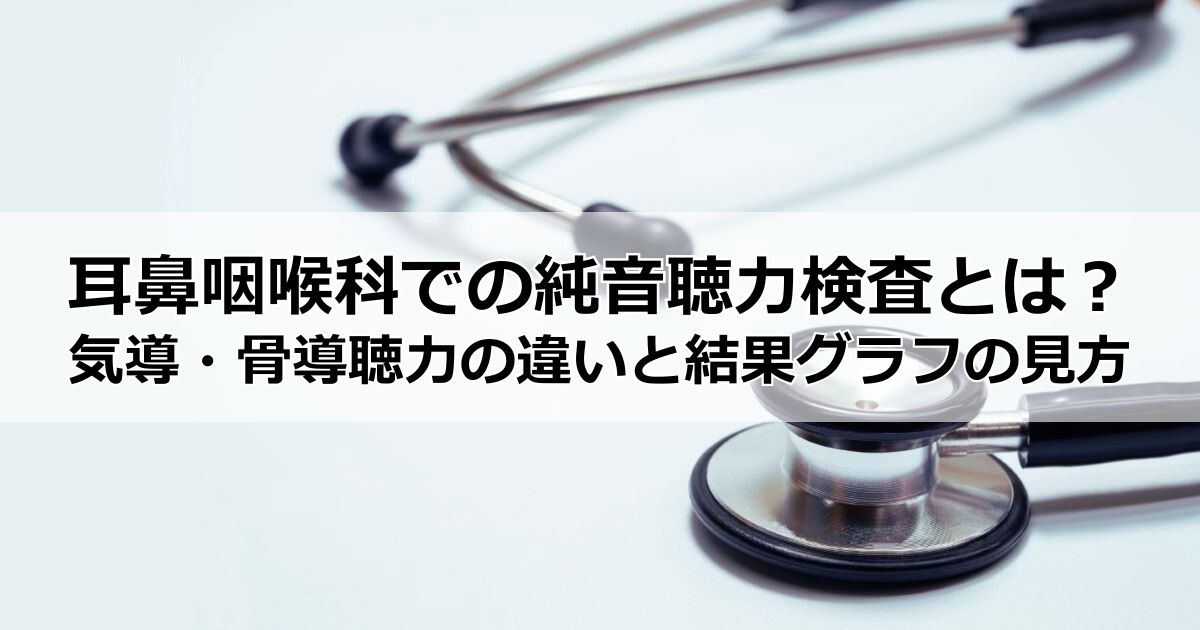
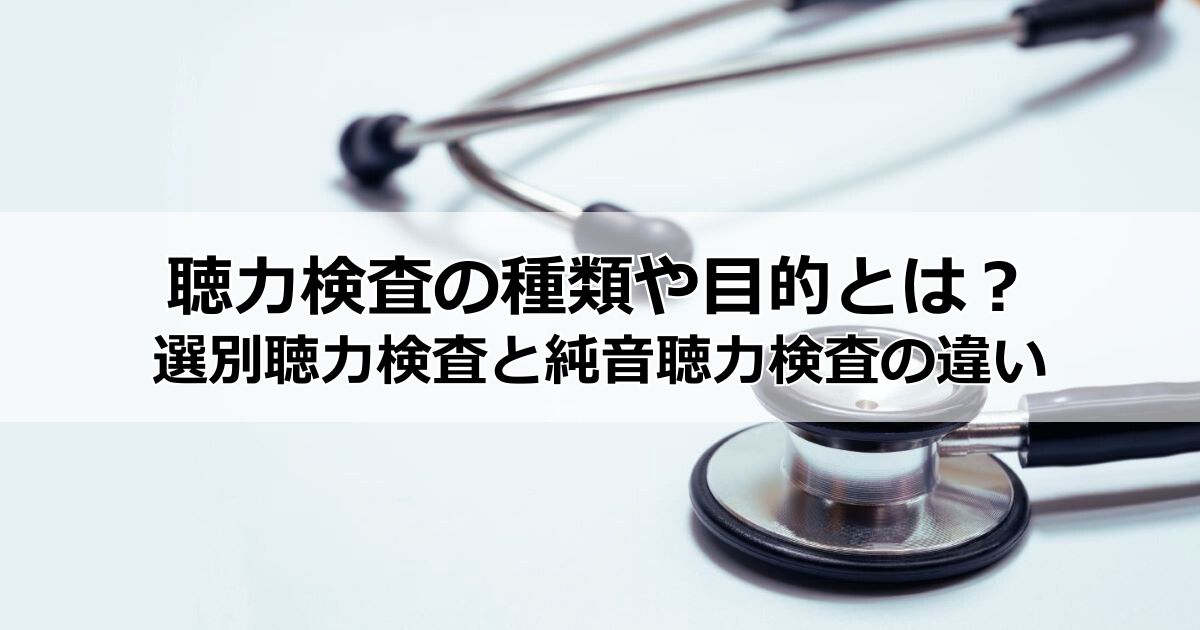
コメント