
普通に話せるから聞こえていると誤解されがちな難聴の人や中途失聴の人。
聞こえる人の感覚で見ると話せることは=聞こえるのだと判断されがちですが、すでに日本語を習得できている場合は聞こえなくなっても話せる人がほとんどです。
しかし生まれつき難聴だった人は、耳に入ってくるはずの音や声から言葉を身につけることができないため発話が遅れ語彙数が足りず話せないこともあります。
では難聴と失聴とはどのような意味や症状なのか、難聴者・中途失聴者・聾者の違いや共通点とは何か?
この記事では、難聴と失聴の定義や症状から難聴者・中途失聴者の違いを解説します。
難聴や失聴の傾向と似ているろう者(聾者)についても紹介しますので、それぞれの特徴を知るご参考になれば幸いです。
難聴とは、もっとも多い症名・症状
難聴の程度は、全く聞こえないものから少し聞こえにくい程度までさまざまです。
聴力低下による難聴のほか、生まれながらにして難聴だったり若いうちから難聴になったりする病状もあります。
ここでは、難聴の中でもっとも多い症名・症状を紹介します。
- 先天性難聴
- 後天性難聴
- 老年性難聴
- 若年性難聴
- 突発性難聴
- 機能性難聴
- メニエール病
先天性難聴
先天性難聴は、生まれつき難聴である状態のことです。
新生児の1000人に1~2人の割合で両耳の難聴があるといわれており、片耳の難聴については明確にはわかっていませんがさらに多いと考えられています。
先天性難聴の原因はさまざまですが、遺伝子の異常が多いほか妊娠中にウイルスや風疹などの感染症にかかったり出産時に早産や胎盤の異常などによるトラブルがあったりする場合もあります。
また外耳や内耳における発育不全も難聴になる場合もあり、先天性難聴である筆者も内耳形成異常によるものでした。
後天性難聴
後天性難聴は、生まれてから耳が聞こえなくなった状態のことです。
年齢を重ねるにつれ人数は増えており、加齢によって難聴になった人の多くは内耳の細胞が失われることによって両側の耳が同じように難聴となっていきます。
後天性難聴の主な原因としては、ウイルスによる感染症や髄膜炎、中耳炎、薬の副作用などが挙げられます。
老年性難聴
老年性難聴は、加齢によって聞こえにくくなっている状態のことです。
加齢性難聴ともいわれ、聴覚に関わる細胞の減少や老化により通常は50歳を超えると聴力が急激に低下し60歳以上になると会話の面で不便になり始める傾向があります。
しかし進行状況には個人差があるため、40代で補聴器が必要になる人もいれば80代を超えてもほとんど聴力が低下しない人もいます。
若年性難聴
若年性難聴は、40歳未満で発症し両耳ともに難聴が進行する状態のことです。
原因不明の感音難聴のうち両耳に難聴があらわれる疾患を「特発性両側性感音難聴」といいますが、老人性難聴と見分けるために年齢の要件が加えられました。
遺伝子による病気の原因が多く、一般的には軽度の難聴から発症しその後徐々に進行していく傾向があります。
突発性難聴
突発性難聴は、ある日突然聞こえなくなる状態のことです。
通常は片方の耳に生ずる感音難聴の1つで、症状は40代から60代に多いですが近年では10代の若年層や70代以上の高齢者にも見られます。
突発性難聴の原因は、ウイルス感染や血流不良などの諸説がありますが、はっきりとした要因はわかっていなく急激に発症する感音難聴のうち、原因不明のものを突発性難聴と呼んでいます。
機能性難聴
機能性難聴は、聴力に関わる器官に問題や障害がないにもかかわらず聴力検査で片側もしくは両側の耳が難聴にある状態です。
突然聞こえなくなったり聞こえ方が変わったりするのが特徴で環境の変化によるストレスが多い幼児期から思春期に現れやすいとされますが、子どもから高齢の人まで起こりうるといわれています。
メニエール病(内リンパ水腫)
メニエール病は、典型的な例として難聴、耳鳴り、めまいの3つの症状を繰り返す状態のことです。
初診での難聴やめまいではメニエール病の診断はされず、突発性難聴との区別が難しい場合もあります。
軽い症状では耳の閉塞感を自覚する程度ですが、重度になると回転性のめまいを伴い、1日のうちでも症状の変動があり症状を繰り返されることが特徴です。
他にも音響外傷など難聴に関する症名がありますが、多くは上記のように感音難聴のうち一般的に多く見られる症状として知っておくとよいでしょう。
感音難聴については、別記事で紹介します。
失聴とは
失聴は、病気や事故により聴力を失うこと、耳が聞こえなくなることです。
もともと耳が聞こえづらかったり、前述の突発性難聴や老人性難聴から進行したりすることもあります。
中途失聴の特徴
中途失聴は、人生の途中で聴力を失った状態のことです。
言葉を覚えた後に聴力を失っているため、聞こえなくても話せる(発話できる)ことが一般的で元健聴者であったことを明確にしています。
幼少時から聞こえづらい人やさまざまな病状の難聴に加え、鼓膜や聴神経などの障害や事故、騒音などの原因により耳が不自由になることもあります。
中途失聴の主な原因
中途失聴の主な原因は、事故や病気、騒音、ストレスなどさまざまです。
失聴や難聴を含めた聴覚障害には、耳のどの機能に損傷や障害があるかで伝音性難聴・感音性難聴・混合性難聴で分類されます。
中途失聴は遺伝も関係するといわれており、耳の中で動くタンパク質を作る細胞の遺伝子に変異が起こることで発症すると考えられています。
伝音性難聴・感音性難聴・混合性難聴については、別記事で解説します。
難聴者と中途失聴者の違い
難聴者と失聴者の大きな違いは、聴力が残っているか残っていないかです。
中途失聴でも難聴を含めて難聴者とすることもありますが、中途失聴者は聴力を失っているのに対し難聴者は若干の聴力が残っている状態を指します。
難聴者のメリット・デメリット
聴力の程度によって違いはありますが、難聴者の中には補聴器や人工内耳を使用すれば音を聞き取れる人もいます。
音は判別できても言葉は聞き取りにくい、自分の声も聞き取れないなど聴こえの程度には個人差があります。
例えば生まれつき聴力の低い先天性難聴は手話を使って言葉を覚えることが多いですが、手話を使える人が限られることからコミュニケーションの幅が狭くなりがちです。
また言葉を身につけることを目的に言語訓練を受けるため、語彙数が少ないことがあります。
その一方で症状が発覚してから聞こえない状態で生活してきた中で身についた知恵があるため、中途失聴に比べると順応性は高いです。
人生の途中から聴力が低下した後天性難聴は、すでに言語を身につけている状態のため手話を覚えることは少なく筆談などでコミュニケーションを図れます。
中途失聴者のメリット・デメリット
中途失聴者は、言語を習得できていて音声でのやりとりができる状態で聴力を失った状態のため話すことには問題がありません。
それまでの聞こえていた生活の中で身についた発声ができることから、基本的に手話は使わず普通に話せる人が多いです。
しかし実際は早口や複数人でのやりとり、暗いところなどでは会話の内容を理解することは困難であることが多く、口話は周囲が想像する以上に集中力を必要とします。
難聴者と中途失聴者の比較
難聴者と中途失聴者の違いを比較表にしましたので、参考にしてください。
| 項目 | 先天性難聴 | 後天性難聴 | 中途失聴 |
|---|---|---|---|
| 対応力 | 臨機応変に対応できる | 臨機応変に対応できる | 戸惑うことが多い |
| 言語 | 言語訓練を要する | 言語にほぼ問題ない | 理解するのに時間がかかる |
| 手話 | 手話を使う人が多い | 手話ができる人が限られる | 手話ができない人が多い |
難聴や失聴となったタイミングにもよりますが、生まれつき聴力が低い先天性難聴は周りからの音や声から言葉を得ることが難しいため手話もしくは言語訓練を受けることでコミュニケーションがとれるようになります。
また後天性難聴も含めこれまでの生活で培ってきた知識や知恵があるため、物事に対する順応力もあります。
失聴者もまた聴こえていた頃の生活で身についた知恵を活かすことが可能ですが、会話などのコミュニケーションでしばらく戸惑うことも多いです。
難聴者と中途失聴者の共通点・留意事項
難聴者と中途失聴者、そして聴覚障害者にも共通点があります。
実際はさまざまな事情で難聴・失聴になり、どちらも必ずある特徴的な共通点というものはなく人それぞれです。
ここでは難聴・失聴の人においていくつか共通点を紹介しますが、固定的な捉え方をしないようにあくまで参考としてください。
話せる=聞こえると思われる
難聴・中途失聴や聴覚に障害がある人は、多くは見た目に特徴があるわけではなく他人から見てその障害がわかりません。
例えば職場や学校に向かう通勤・通学路で、1日に何人の難聴者や聴覚障害者とすれ違っているか把握できている人はほとんどいないはずです。
髪の短い男性やショートカットヘアの女性など耳に補聴器を装用していることが見える状態の人はいますが、基本的に見た目からは聞こえる・聞こえない、聴覚に障害がある・ないは判断ができないといえます。
中途失聴者は社会生活において何らかの社会の障害に出会うことで初めて困難や障害が生まれ、その困りごとが周囲には伝わらないことが多いかもしれません。
手話を必ず使えるとは限らない
発話で情報伝達をせずに手話を使う人もいますが、難聴・失聴者全員が必ずしも手話を使うわけではありません。
難聴・失聴を含む聴覚障害者と接したことがない人、聴覚障害者を扱ったドラマやマンガなどでしか関わる機会がなかった人にとっては、難聴・失聴者や聴覚障害者は手話が使えるという固定観念を抱きがちです。
とくに発話ができていて手話が使えない中途失聴者に対して、本当に聴覚障害者なのかと疑問をもたれることもあります。
難聴者でも手話を使う人は多いですが、必ずしも手話を使えるとは限らず筆者も言語を覚えることが優先にあったため手話を覚えさせられる環境ではありませんでした。
また逆に、健聴者の立場から見た時に手話が使えないとコミュニケーションがとれないと誤解されることもあります。
補聴器装用による誤解
難聴・中途失聴や聴覚に障害がある人は、誰でも補聴器を装用していると思われがちです。
しかし難聴の程度によっては実際に補聴器を使わなくてもいい人もいれば、中途失聴の人は補聴器を使っても聞こえることはないといえます。
そのため、補聴器をつけていないからといって正常に聞こえるとは限りません。
また近年ではワイヤレスイヤホンが注目されていることから、道路交通法の違反とされている自転車でのイヤホン装着が補聴器と間違えられやすく指導を受けることも少なくないようです。
ろう者(聾者)について
難聴者や失聴者とは別に、ろう者(聾者)という言葉をご存知でしょうか。
ろう者は音声言語を身につける前に聴力を失っており、主に手話をコミュニケーション手段とする人のことです。
難聴・中途失聴者との違い
難聴・中途失聴との大きな違いは、手話をコミュニケーションの基本としていることです。
補聴器などを使用しても音声が判別できない・耳が聞こえない状態の人がろう者で、聴力がある程度残っていて聞き取れる状態の人が難聴者といわれることがあります。
手話を主なコミュニケーション手段とする人をろう者、音声での言語を中心に手話をあまり使わない人を難聴者と呼ばれることもあります。
中途失聴者はもともと聴者だったのが途中で聴力を失った人を指すため、音声言語を身につける前に聴力を失ったろう者とははっきり区別できます。
ろう者の定義
ろう者の中にも聴力が残っている人もいて補聴器を利用している人もいますが、その多くは手話を使用していることが大きな特徴です。
しかし、ろう者にあたるかというのは残っている聴力の程度や手話言語使用の有無ではなく、その人自身が自分をどのように認識しているかというアイデンティティにも関わるため一概に定義することはできません。
その中で、ろう者と難聴者の区別については耳が完全に聞こえないかどうかで分けるのが一般的です。
難聴者と中途失聴者、ろう者の違いまとめ
難聴者と中途失聴者でも聞こえ方やコミュニケーションのとり方はさまざまです。
人は生まれた時から、母親の発する言葉や周囲の声など耳から入ってくる音や声で言葉を理解します。
例えば先天性難聴の人は言語発達が遅れるため語彙数があまりありませんが、言語訓練を行うことで必要最低限の言葉を身につけることが可能です。
また若いうちから難聴になる人もいれば、加齢によって聴力が低下する人もいます。
それに対して人生の途中から聞こえなくなった中途失聴者は、発話はできても聞こえなくなったことでコミュニケーションがとりづらくなります。
今まで聞こえていた世界から急に音のない閉ざされた世界に引き込まれるため、苦悩は計り知れないものだと察します。
難聴者と中途失聴者には環境や状況が異なることで見た目からはわかりづらいのが一番悩ましいところですが、健聴者を含む周りの人はその変化に躊躇することなくその人に適したコミュニケーションを心がけてあげてください。


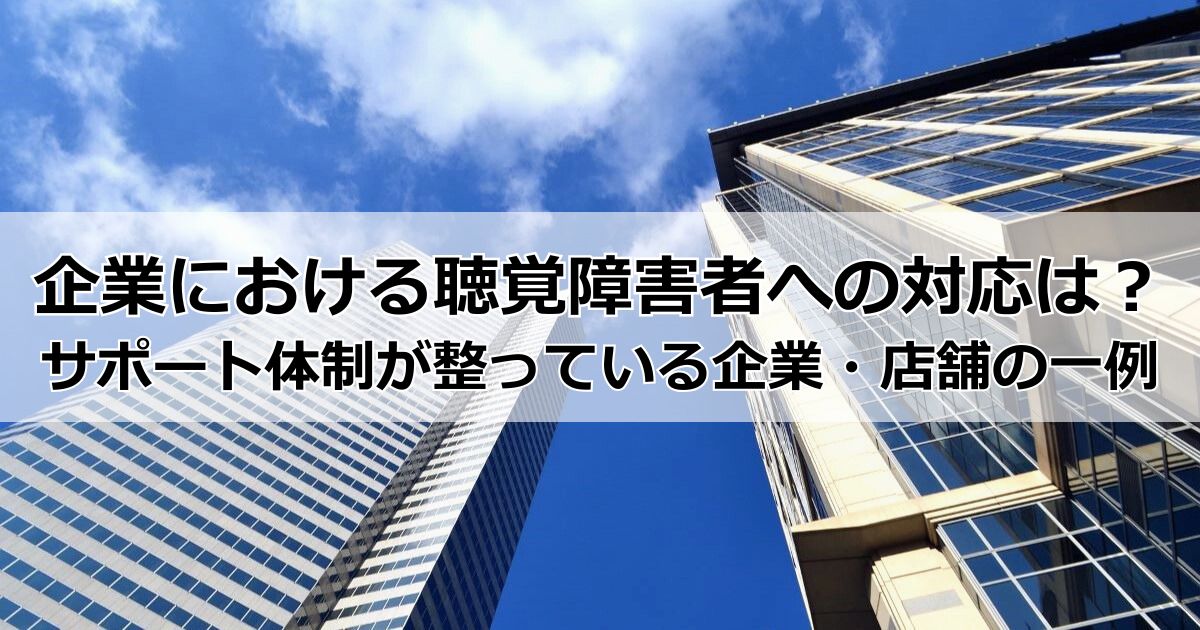
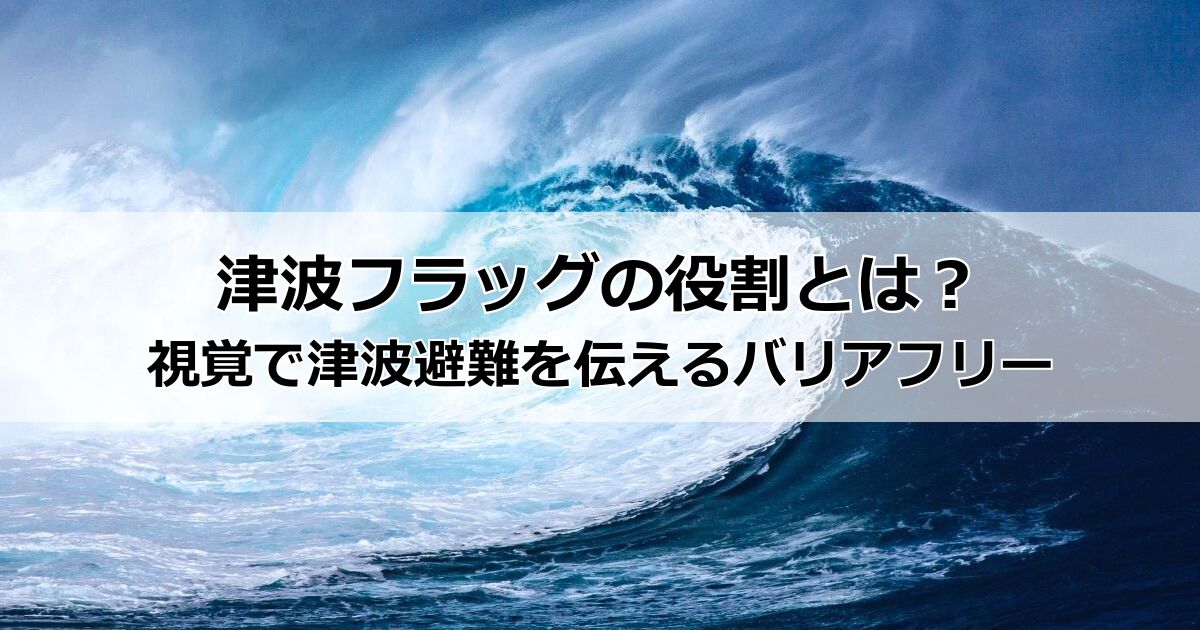

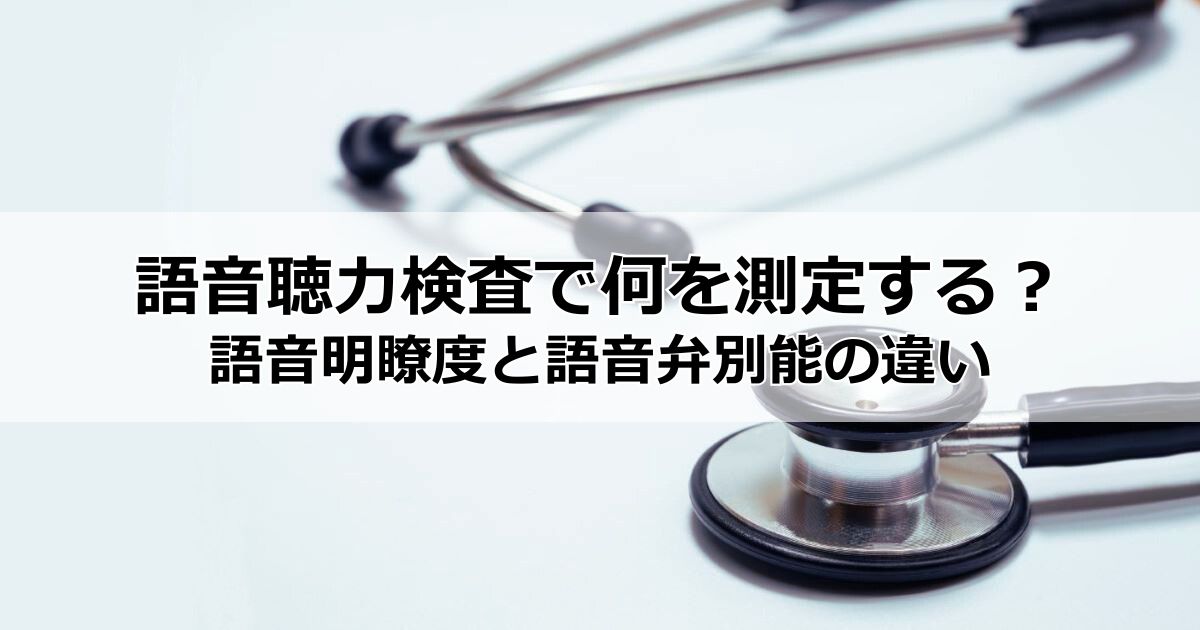
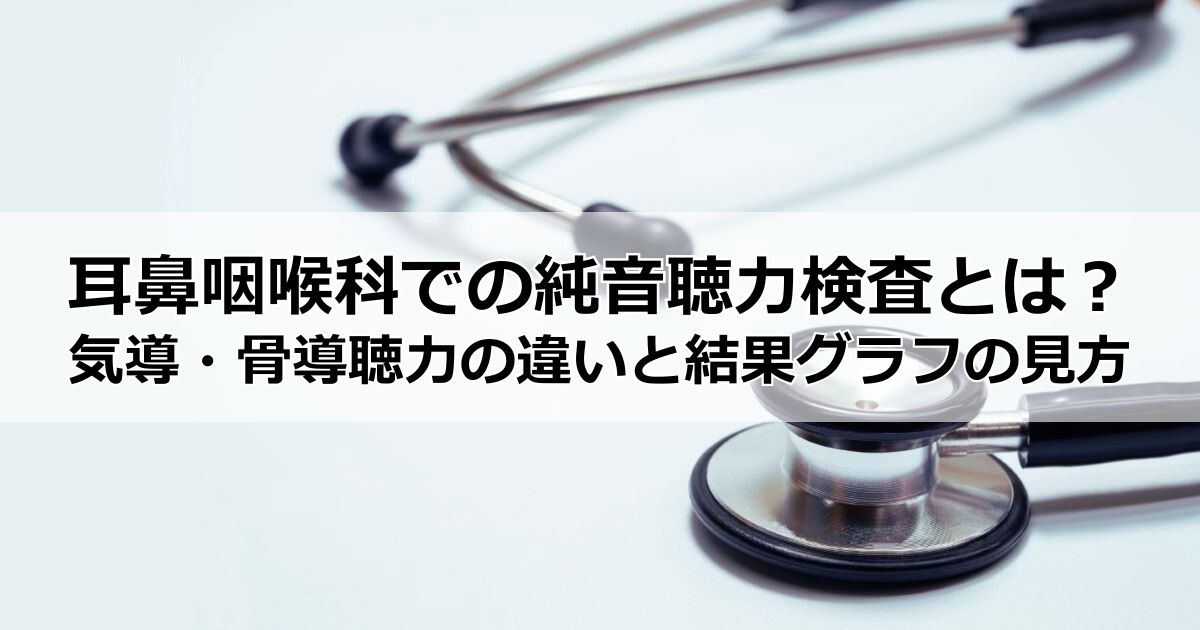
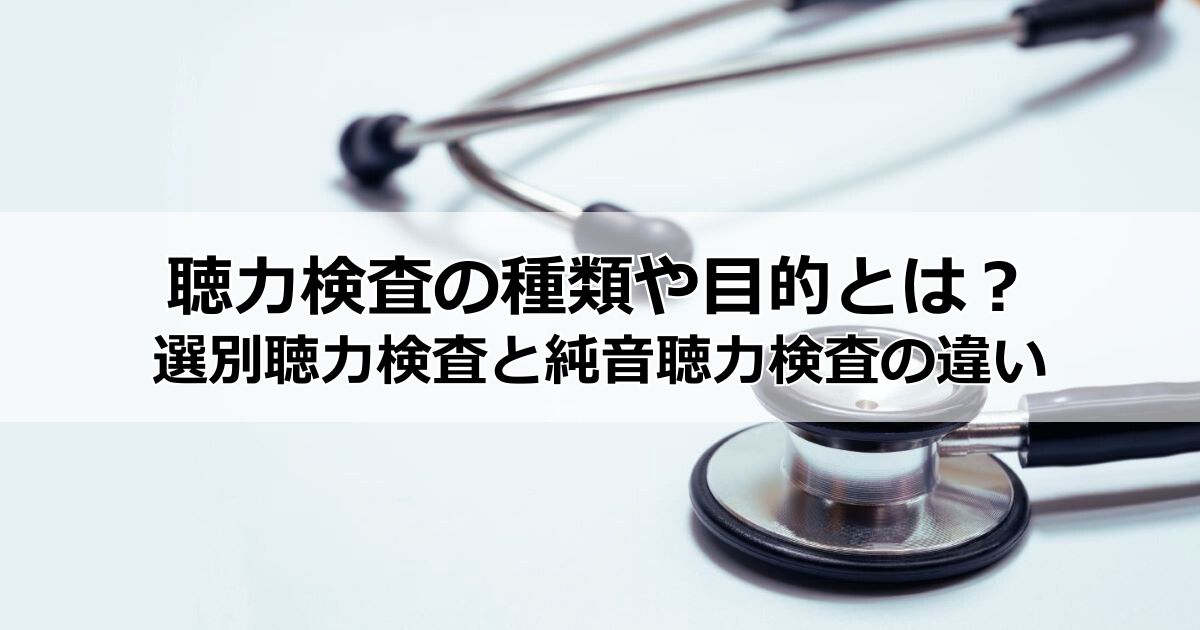
コメント