
街中に響き渡る車・バイクの音や人の話し声など。
耳が聞こえにくい人や聞こえない人にとって聴力を補うために、どんな工夫をして日常を過ごしているのでしょうか。
補聴器の装用で発話できる人もいれば手話を使って会話する人もいますが、中には聴こえをカバーできるアイテムを必要とする人もいます。
しかし聴力を補うアイテムにはどんなものがあるのか、どういう時に役立つのか具体的に知らない人も多いでしょう。
この記事では、難聴の人や聴覚障害者など耳の不自由な人が利用している医療機器、難聴の助けになる便利アイテムを説明します。
難聴である本人だけでなく、周囲の人がどのようなツールやアイテムを使って難聴の人のサポートができるのかを知るご参考になれば幸いです。
耳が不自由な人が利用する医療機器
難聴や聴覚障害をもつ人の中で、聴力の程度や難聴のレベルによって医療機器を装用していることがあります。
補聴器
補聴器は、病気や加齢などで聴力が低下した人や聴覚障害者の聴こえを補助する補装具です。
内蔵されているマイクで集めた周囲の音を増幅し、アンプやスピーカーなどにより聞きやすい音質と音量にして耳の中に伝えます。
補聴器には耳の上に引っかける耳かけ型、耳の穴に装着する耳あな型、本体につながったイヤホンを装着するポケット型という3つの種類があります。
従来はアナログ形式の補聴器でしたが、近年では聞こえ方によって細かい調整が可能なデジタル方式の補聴器が主流です。
補聴器の特徴や種類などについては、別記事で紹介します。
人工内耳
人工内耳は、世界で最も普及している人工臓器の1つで補聴器での装用効果が不十分である人に対する聴覚獲得法です。
蝸牛の代わりにつけた装置により音の情報を電気信号に変え、聴神経を直接刺激し脳へ電気信号を送ることで脳で環境音や音声、言葉を感じることができます。
耳の奥に埋め込む部分とマイクで拾った音を耳内に埋め込んだ部分へ送る体外部の2つで構成され、音は外耳も中耳も通らないため手術が必要です。
人工内耳には個人差があり、手術直後からすぐに音が聞こえるわけではありません。
最初は機械的に合成されたような音が聞こえますが、人工内耳の効果を十分に発揮するためには積極的なリハビリが重要です。
筆者も担当医から人工内耳の手術を勧められたことがありますが、当時は成功率がわずか15%と低かったことと自然の流れに委ねることを重視していたため人工内耳にしませんでした。
人工内耳の手術が始まってから20年が経過しており、現在では比較的安全な手術となっていますが有効性には個人差があります。
そのため当サイトでは人工内耳とは何かという概要説明だけに留めていますので、詳しくは人工内耳を専門とする病院に問い合わせてください。
集音器(助聴器・拡張器)
医療機器ではありませんが、見た目が補聴器と似ている集音器というのがあります。
集音器は、内蔵のマイクで音を大きくして耳に届ける音響機器です。
助聴器や拡張器とも呼ばれ、家電製品の分類になるため販売や管理に許可が必要なく、オンライン通販や家電量販店でも購入できます。
集音器のほうが価格も安価で手軽に購入できるため、使用目的によっては難聴者でも使える人もいます。
しかしもともとは難聴者を対象とした製品ではないため、満足な効果を得られず聴こえを改善できない場合が多いです。
どちらかというと、補聴器を装用するほどではない軽度の難聴に向けたオーディオ製品として利用することをおすすめします。
難聴の助けになる便利アイテム
難聴の人や聴覚障害をもつ人が、日常を過ごす上で役に立つアイテムやグッズがあるのをご存知でしょうか。
ここでは難聴の助けになる便利アイテムを紹介しますので、本人だけでなく家族や周囲の人も参考にしてください。
スマートウォッチ
スマートウォッチは、一般的にタッチスクリーンとCPUが搭載された腕時計型のウェアラブル端末です。
腕時計型のコンピュータとして健聴者も活用するほど人気ですが、聴覚障害をもつ人にとっても便利なアイテムです。
スマートフォンと連動させて電話の着信やメール受信などをアラームを光や振動で知らせてくれるだけでなく、簡単なメッセージや緊急連絡メールの送信もできます。
インターホンと接続できるタイプもあり、来客も知ることが可能です。
音声翻訳ツール(文字変換アプリ)
近年のデジタル端末には、音声を文字に変換してくれる音声翻訳ツールや文字変換アプリがあります。
新型コロナウイルス禍以降、オンラインでの会議や打ち合わせが増えたことにより何を話しているかまでは画面上ではわからないことも多かったため、ZoomやTeamsなど字幕機能をつけたツールも増えました。
しかし精度も速度も向上してはいるものの口話の文字への自動変換には誤字がまだ多いため、聴覚障害者への情報伝達には課題が残っています。
口話や筆談を交えつつ音声翻訳ツールや文字変換アプリも活用することで、それぞれの欠点を補いながらコミュニケーションをとることが望ましいです。
職場や自社サービスでも提供する情報が視覚・聴覚情報のどちらかだけになっていないか確認し、情報のバリアをなくしていくことが難聴者を含めた多様な人とのコミュニケーションのとりやすさにつながります。
屋内信号装置
屋内信号装置は、難聴の人や聴覚障害者、ろう者など音が聞こえづらく日常生活の不自由さを解消するために生活音を振動や光、大きな音に変えて知らせてくれる機器です。
電話やインターホンをはじめ、目覚ましや火災警報、赤ちゃんの泣き声など家庭内やオフィスでの生活をより快適に過ごせるようにあらゆる音の情報を視覚的または振動で通知してくれます。
福祉機器の1つとして国からの支援があり、聴覚障害の程度が2級以上であれば給付制度も利用できますので詳しくは厚生労働省サイトをご参考ください。
振動式目覚まし時計
振動式目覚まし時計は、目覚まし時計のアラーム音が聞こえない難聴・聴覚障害者に振動で時間を知らせてくれる時計です。
シェイカーがついているため、枕の下などに入れて寝ることでアラーム音の代わりに振動で起こしてくれます。
振動の強弱が設定できるものや振動と音を組み合わせられるものなど種類も豊富です。
筆者は学生時代に、腕時計型の振動ウォッチを利用していたことがあります。
現在では窓から射し込む太陽光や体内時計で起きることが可能ですが、当時はあと何時間後に振動で知らせるかという設定で使い勝手がよくなかったです。
寝ている間に手首が痛くなり外していたことも多かったため、置時計型が登場したのは便利で助かりますね。
ベルマンアラームクロック
ベルマンアラームクロックは、聴覚障害者向けに考案された振動式目覚まし時計です。
正確な時間だけでなく、電話やFAXの着信も光や振動で知らせてくれます。
強力な振動が起こるため、難聴の人だけでなく朝が弱い人や目覚めの悪い人、自力で起きられない人でも使用できます。
ベルマンアラームクロックは、日常生活用具給付の対象の1つです。
振動式腕時計
振動式腕時計は、日常使いしながら振動でアラームを知らせてくれる腕時計です。
目覚ましのアラームだけでなく、予定や約束の時間を知らせてくれたり電車の乗り過ごしを防いだりするなどあらゆる場面で活用できます。
近年では、前述のスマートウォッチが登場したことで多くのことができるようになりました。
目覚ましアラームのほか電話の着信やメール受信、来客時には光や振動で知らせてくれるため、スマートウォッチ1つがあれば十分でしょう。
筆談ボード・ノート
難聴の人は口話では理解できない言語や相手の発する音質によって聞き取れない場合もあるため、筆談ボードやノートを持ち歩いている人も多いです。
筆談ボードは、ペンや鉛筆を使用しなくても磁気で文字が書けるボードです。
書き消しが簡単で繰り返し使用できるため、1台あればさまざまな場面での使用が可能です。
ちょっとした会話での聞こえない部分をカバーできたりスムーズな会話につながったりするほか、災害などの緊急時や病院など静かな場所でも重宝します。
筆談ボードは書き消しが可能なため、会話の記録を残したい時には紙のノートが便利です。
振動体温計
振動体温計は、検温が終了したことをバイブレーションで知らせてくれる体温計です。
検温が終わったタイミングを把握できるため、もう測定は終わったかな?というちょっとした負担を減らすことができます。
筆者は、振動体温計があることを最近まで知りませんでした。
現在15~30秒で検温が終了する体温計を使用していますが、破損したら振動体温計に買い替えるつもりです。
透明マスク
難聴・中途失聴者や聴覚障害者は、口元の動きを読み取って聞き取れない・聞こえない分をカバーすることが少なくありません。
マスクを要する場面で、難聴の人や聴覚障害をもつ人と会話する時は透明マスクを使用するといいでしょう。
透明マスクは口元の部分が透明なプラスチック製になっており、顔に接する部分は不織布などの布製になっています。
呼吸がしやすく曇りにくいものも増えているため、マスクが必要な場では透明マスクにするだけでコミュニケーションがとりやすいでしょう。
福祉機器として支援が受けられる制度
上記で紹介した難聴の助けになる補助アイテムの中には、福祉機器の1つとしてお住まいの市区町村による支援が受けられる場合があります。
厚生労働省によると福祉の増進に寄与することを目的に、市町村が行う地域生活支援事業の1つとして日常生活用具の給付が規定されています。
例えば、玄関のインターホンや電話の着信などがあった場合に音を光や振動に変えて知らせる屋内信号装置、音声の代わりに文字などで通信が可能な通信機器などです。
聴覚の障害に関係なく介護・訓練支援用具や自立支援用具、在宅療養などの支援用具といった分類で日常生活用具も給付が受けられる場合もあります。
ただし聴覚障害者が給付を受けられる日常生活用具は、市区町村によって対象となる機器や難聴の程度など条件がありますので各市区町村サイトをご参考ください。
聴こえを補う便利アイテムまとめ
耳が不自由な人は補聴器や人工内耳といった医療機器だけではなく、聴こえをカバーしてくれるさまざまなアイテムやツールを活用しながら生活しています。
難聴の助けになる便利アイテムをあらかじめ知っておくことで、難聴や聴力の低下を感じた時にすぐ準備もできます。
難聴や聴覚障害のある本人だけでなく、本人に関わる家族や友人など周囲の人もサポートできるアイテムを知っておくことでいざという時に動きやすくなるでしょう。


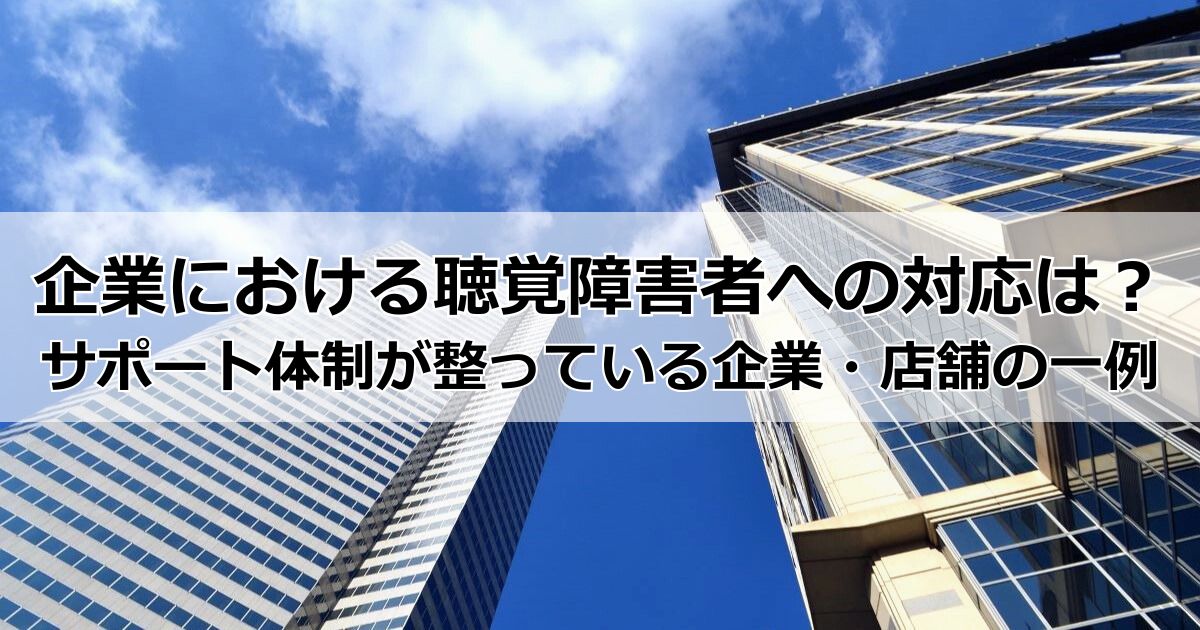
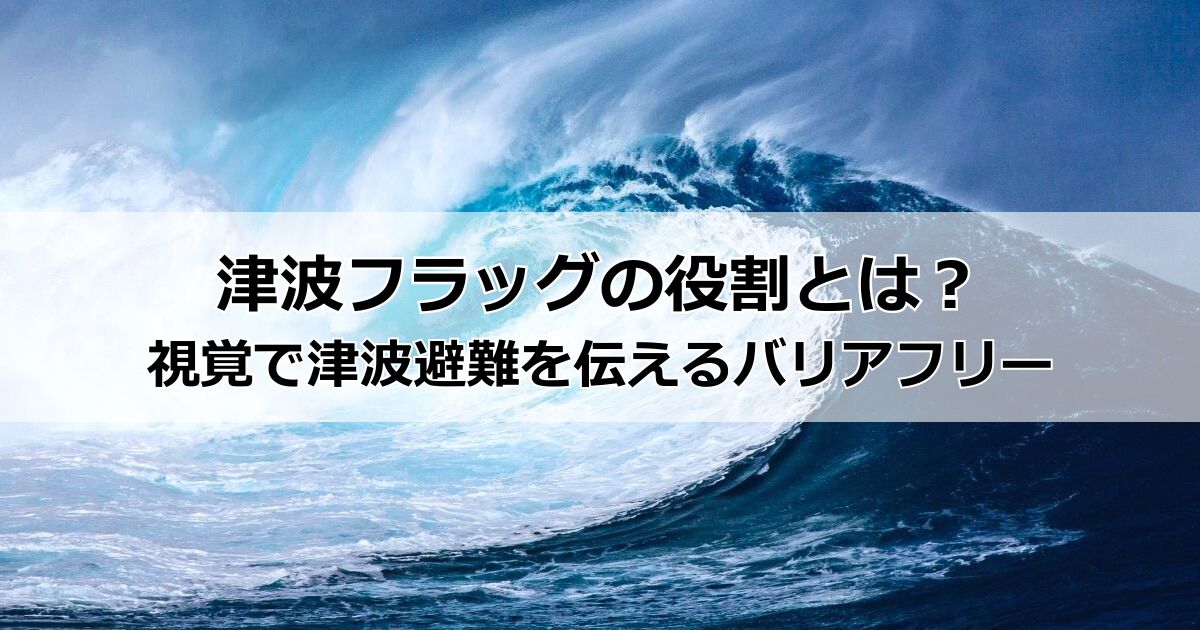

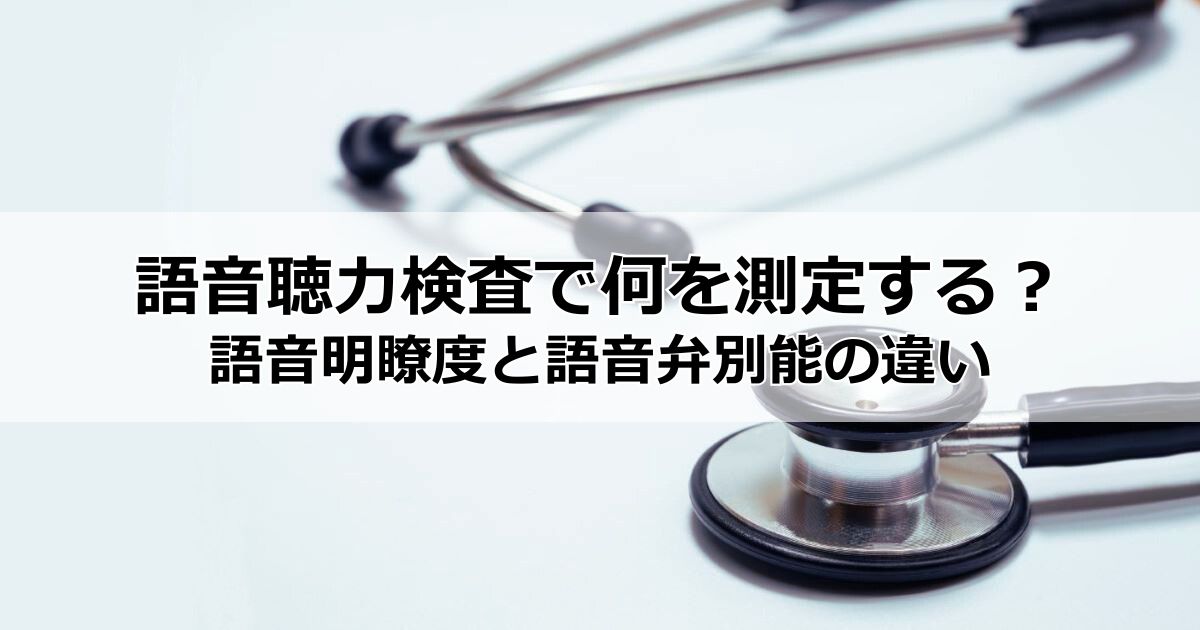
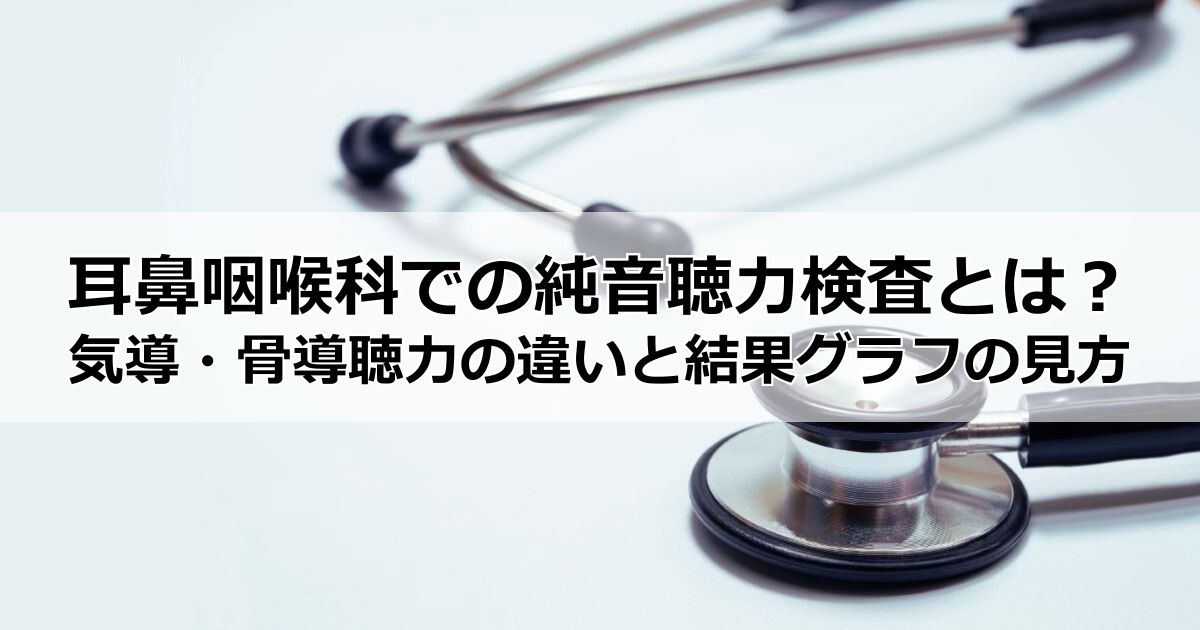
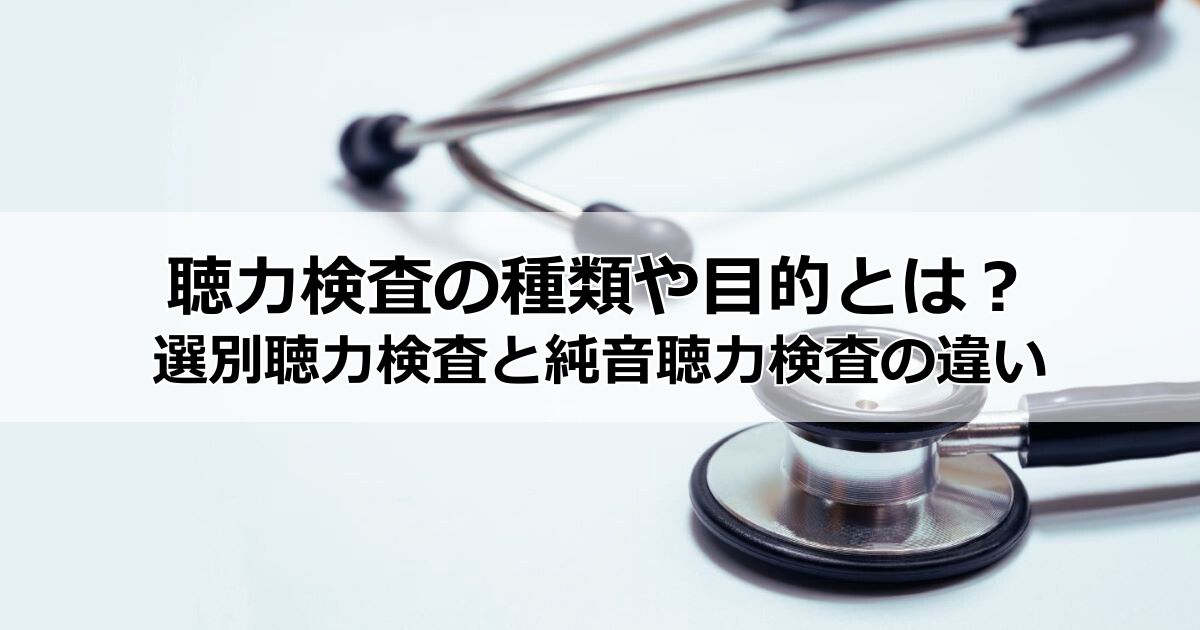
コメント