
外見からは見えにくいとされる難聴の人や聴覚障害者。
メガネをかけている視力の弱い人や杖をもっている人に比べると、耳の不自由な人は他人から見て症状や障害があることに気づきにくいです。
そのため、あらゆる物事に対して周囲の人に手間や面倒をかけないように先回りする傾向があります。
この記事では難聴の人や聴覚障害がある人のよくある行動・心がけていることといった特徴あるあるを紹介します。
当事者は共感していただけると思いますが、難聴の人が普段から気をつけていることを知るきっかけになれば幸いです。
難聴や聴覚障害がある人の特徴
難聴の人や聴覚障害がある人には、どんな特徴があるのでしょうか。
見た目の特徴
難聴の人や聴覚障害者の多くは、見た目に特徴があるわけではなく他人から見てその障害がわかりません。
目の悪い人はメガネを装着し足腰が弱い人は歩き方の癖や杖でわかるのに比べ、耳の不自由な聴覚障害者は周囲の人から見えにくい障害です。
例えば通学・通勤路や外出先、旅先での道中など、1日に何人の難聴者や聴覚障害者とすれ違っているか把握できる人はほとんどいないはずです。
男性やショートカットヘアの女性など耳に補聴器を装用していることが見える人はいますが、基本的に見た目からは聞こえる・聞こえない、聴覚に障害がある・ないは判断ができないでしょう。
聞こえの特徴
難聴の人や聴覚障害がある人を見分けるには、コミュニケーションをとったり行動を共にしたりすることでわかります。
難聴の人や聴覚障害者であることがわかるポイントは、主に以下の通りです。
- 会話で聞き返すことが多い
- 騒がしい環境での会話が困難
- 人によっては発音が特徴的
- 後ろからくる自転車や車に気づかない
- 細い通路や階段でふらつく
難聴の人は相手の話すボリュームに問題がなくても音程や音質などによって聞き取れる度合いが異なるため、聞き取れなかった部分を聞き返すことが多いです。
また、音楽や周囲の騒ぐ声が響く飲食店での会話も困難なことがあります。
重度の難聴になってくると、後ろからやってくる自転車や車の音に気づかず細い通路や階段ではふらつくこともあります。
聞こえ方による特徴の違い
また難聴の人の聞こえ方による特徴の違いも説明しますので、以下を参考にしてください。
- 雑音がある中での会話が聞き取りにくい
- 高音域(あるいは低音域)の音が聞こえにくい
- 響く音は割れて不快に聞こえる
- 音質によっては歪んだように聞こえる
- 補聴器をつけても聞き取れないことがある
難聴の程度は人によってさまざまで、電話ができる軽度難聴から周囲の音がほとんど聞こえない重度難聴までのレベルがあります。
程度による難聴の種類と聴力レベルについては、別記事で紹介します。
難聴の人がとる行動・あるある
難聴の人がとる、あるいは無意識にとってしまう行動があります。
当事者はおそらく共感できると思いますが、あくまで一例として難聴の人や聴覚障害がある人が後のことを考えた上でとる行動がわかります。
苦手な音声には消極的
難聴の人や聴覚障害のある人は、基本的に好き嫌いはありません。
しかし聞き取りやすい話し声の人には、積極的に話しかける傾向があります。
逆に聞き取りにくい相手にはあまり近寄らないかもしれませんが、決して嫌いだからというわけではないことに留意してください。
何度も聞き返すことが重なると、不便をかけて申し訳ない気持ちが先にあるためです。
また、筆談でのやりとりに面倒をかけることを避けがちです。
複数人の会話には加わらない
難聴の人は、多数の人が集まる会話の流れについていけないことが多いです。
例えば、歓送会といった飲みの場や職場での会議などが該当します。
とくに補聴器を使っている難聴の人は、複数人の声の聞き分けが困難です。
普通の健聴者や軽度の難聴者であれば、飲み会など周囲が騒がしい環境でも相手の話は聞き取れるという人が多いでしょう。
これは音を処理して必要な情報だけを受け取るという、耳内にある処理能力が働いているためです。
しかし一方でボイスレコーダーで録音した音声を聞くと、周囲の音まで全部混ざってしまい聞き取りづらいことがあります。
補聴器を使っている聴覚障害者が複数人の話が聞き取れないのも、同じような原理によるものだといえば理解できるでしょうか。
さらに聴覚障害者は話す相手の口元を見て内容を類推するため、発話が終わるまで口元の動きを見つめる必要があります。
そのため複数人が一斉に話すと、次に誰が話すのか誰を見たらよいのかわからなくなりコミュニケーションがとりにくくなってしまうのです。
先を読もうとする癖
前述の類推に通じますが、難聴の人は相手が話す内容が聞き取れない可能性を踏まえて先を読もうとする癖があります。
何度も聞き返す手間を省きたい、面倒をかけることを避けたいという心理が働くためです。
そこでいくつかの言葉が読み取れると、内容の意図を想定して相手が用件を話し終える前に確認してしまうことがあります。
耳からの情報が得られない分、もし○○○だったらという可能性を予見して行動することが多いです。
難聴の人が心がけていること・あるある
難聴の人は、相手の手間や面倒をかけないように先に回って行動することがあります。
これは聴覚障害にかかわらず、他の障害をもつ人も別のケースで同様かもしれません。
ここでは筆者の経験をもとに、あらゆる物事がスムーズにいくように難聴の人が心がけている一例を紹介します。
レストランで飲食をする時
例えばレストランやカフェで料理と一緒に飲み物をセットで注文した時に、オーダーをとりにきた店員から以下のような質問が返ってくることがあります。
- 飲み物を食前か食後にもってくるか
- コーヒーや紅茶の場合はアイスかホットか
- 紅茶を注文した時にストレートかレモンか
- ステーキ肉の焼き加減(レア・ミディアム・ウェルダン)
- パスタ麺の茹で加減(アルデンテ・ベンコッティ)
レストランやカフェなどの飲食店で飲み物を一緒にオーダーした時、食前か食後かもってくるタイミングを聞いてくることがあります。
コーヒーや紅茶をオーダーした場合はアイスかホットか、ミルクが必要か不要かも聞かれるでしょう。
またベーシックな紅茶の場合に、ストレートかレモンかを聞かれる点にも注意です。
お店の対応によりますが、他にもステーキなどの肉には焼き加減、パスタをオーダーした時は麺の茹で加減(硬さ)も聞いてくる場合があります。
友人や家族など同行者がいる時は代わりに聞いてくれますが、1人で飲食したい時に聞き取れないことは不便です。
しかし1度利用した飲食店で支障なくオーダーができたら、次回以降も利用しやすいでしょう。
カフェで飲み物を購入する時
スターバックスやドトールなどのカフェドリンク店で、コーヒーなどの飲み物を購入する時に以下のような質問がくることがあります。
- テイクアウト(持ち帰り)かイートイン(店内飲食)か
- シュガーまたはシロップの必要可否
- クリームの必要可否
テイクアウトとイートインでの共通として、シュガーまたはシロップ、クリームの必要可否も聞かれるので注意が必要です。
そのため、オーダーする時にテイアウトかイートインか、テイクアウトなら袋の必要可否を伝えています。
また砂糖やクリームの必要可否も聞き取れない場合を想定して、オーダー時に伝えることが多いです。
スーパーやコンビニなどで買い物をする時
スーパーやコンビニなどの物販店で買い物をする時に、レジの店員から以下のように質問されることがあります。
- レジ袋が必要か
- 割り箸やスプーンなどが必要か
- 弁当やお惣菜、スープなどは温めるか
最近ではセルフレジの導入も相まって、多くのスーパーでは有人レジでもレジに入る前にサイズの異なるレジ袋をとる仕組みが多くなり、レジ袋の必要可否を伝える必要がなくなりました。
しかしコンビニや業務スーパーなど、ショップによってはレジ袋の必要可否を聞くことがあります。
他にも割り箸やスプーン・ストローといったカトラリー、食品によってはレンジで温めるかどうかも聞かれるでしょう。
筆者も最初は何を聞かれているかわからずレジ袋が必要か聞かれたのだと思い「はい」と答えてしまったことがあり、その後にスープをレンジに入れ出したので慌てました。
そのため、レジに商品を預けた時に聞かれるであろう質問の内容をあらかじめ全部伝えることにしています。
名前の呼び出しがある時
病院や公共・民間施設などの順番待ちでは、名前での呼び出しが多いです。
そのため受付をする時に、名前を呼んでも反応がなかったら合図していただけると助かることを伝えておきましょう。
筆者が通院するかかりつけの病院では、すでに顔なじみになっていることもあって呼び出されたかなと思い受付の人を見ると診察室へ促すしぐさをしてくれるので安心です。
ただし一部の病院や銀行などの公共・民間施設では受付番号で管理をしているところも多く、順番がくると電光ボードに番号が表示されるところもあります。
こういった視覚的な情報のバリアフリーがもっと増えてくれたら嬉しいですね。
バリアフリーについては、別記事で紹介します。
上記はあくまで一例であり、筆者が経験していないだけで他にも困難にぶち当たる対応があります。
難聴や聴力低下を感じ始めた人は、こういうケースもあるという準備や心がけとして参考にしてください。
商業施設や交通機関での緊急アナウンス
ショッピングモールや百貨店などの商業施設、電車やバスといった交通機関などでは音声によるアナウンスが多いです。
通常は店内情報や迷子情報、次の停車駅といった基本情報のためあまり気に留めることはありませんが、緊急アラームが聞こえたり周辺の雰囲気がいつもと違ったりしたら注意しましょう。
近年では、文字や画像を流すデジタルサイネージを設置するところも増えました。
駅ホームでは時刻表の下に文字が流れることがありますが、細かい情報までは伝えきれない面もあります。
もし大地震や緊急事態による音声案内が流れた時は、エントランスやサービスカウンターなどで直接聞きにいくことをおすすめします。
また人身事故などといった緊急停車や運転見合わせが発生してもどう動いていいかわからないことがあるため、駅員のいる窓口に聞くようにしましょう。
周囲の人は聴覚障害に関わらず、視力の悪い人や足腰の弱い人など困っている様子を見かけたら声をかけてあげてほしいです。
赤いヘルプマークをつけている人も障害をもっている目印でもあります。
ヘルプマークについては、別記事で紹介します。
筆者がとった行動
筆者も朝の出社時に電車内で、信号故障による緊急停車で運転見合わせになったことがあります。
その時に運転再開の見込みや時間が音声アナウンスで流れますが、当然聞き取ることが困難です。
緊急停車した駅からの移動が可能なのかもわからないため、改札口付近にいる駅員に聞きました。
その時に耳が不自由なため筆談でお願いしたいことを伝えて、現在の状況や予定を知ることができたおかげでその後の行動を決めることができました。
万が一の事態が起きた時、同じ公共・民間施設や交通機関内にいる一般客に聞くのは勇気が要ることです。
しかし、商業施設や交通機関で働く係員は防災教育を受けています。
またバリアフリー設備が整っているということは、身体障害者への対応も視野に入れているはずです。
そのため緊急事態の時には、公共・民間施設や交通機関の係員や関係者に直接聞くようにしましょう。
難聴の人や聴覚障害者の特徴まとめ
難聴の人や聴覚障害がある人は、「聞こえない」ことだけではありません。
コミュニケーションがとりにくい・音声による情報が伝わらない・聞こえないことが外見からわかりにくいなどの特徴や不便さがあります。
先回りして行動することはもちろん大切ですが、相手によけいな手間や面倒をかけたくない気持ちが強いです。
しかし、自分の力だけでは解決できないことも当然ながらあります。
とくに音声による情報が伝わらないことは、災害が起きた時には深刻です。
緊急事態を感じた時には、勇気をもって公共・民間施設の係員や交通機関の駅員がいる場所まで聞きにいくことを心がけましょう。
また健聴者あるいは健常者は、耳が不自由な人だけでなく他の障害をもつ人や妊婦の人、ヘルプマークをつけている人など困っていそうな人を見かけたら声をかけてあげていただけると嬉しいです。


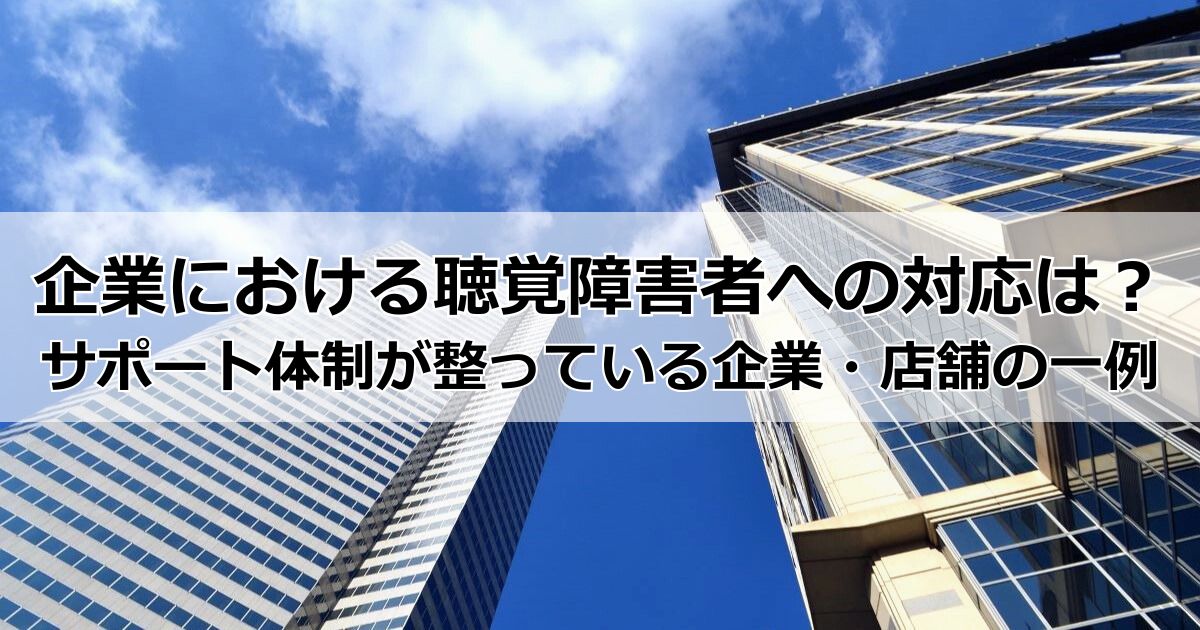
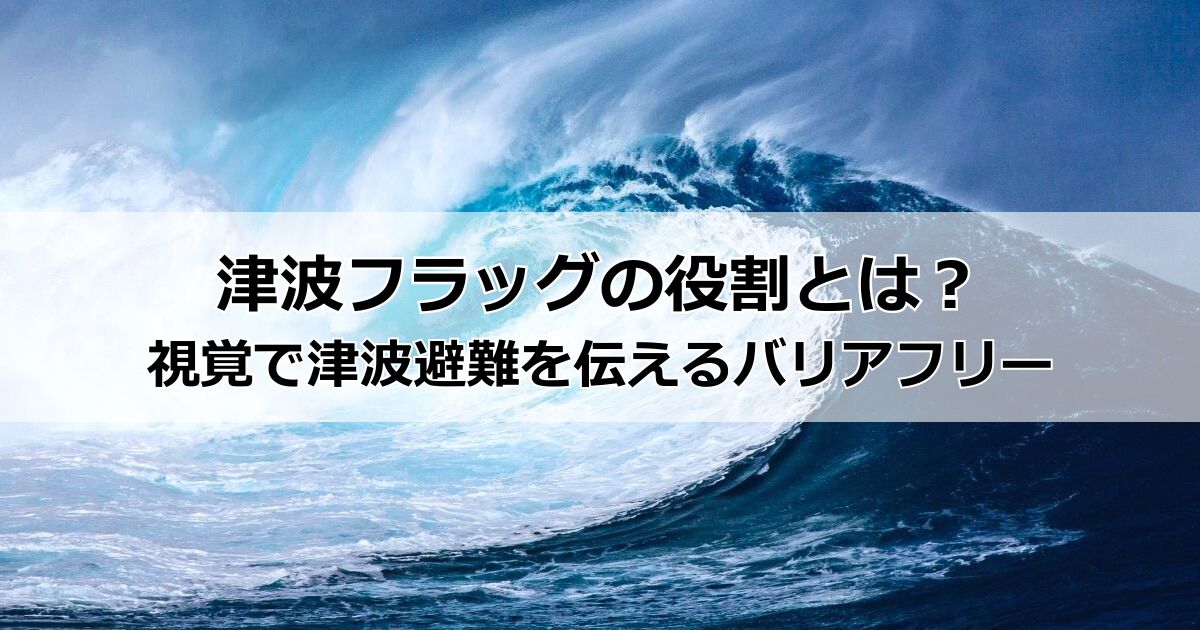

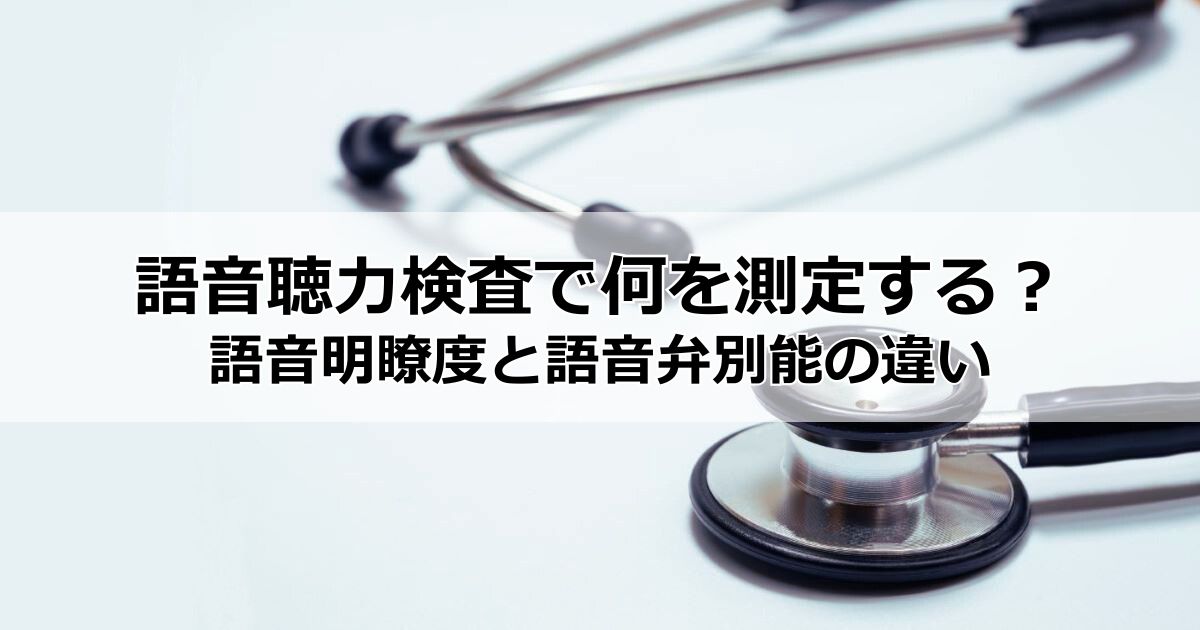
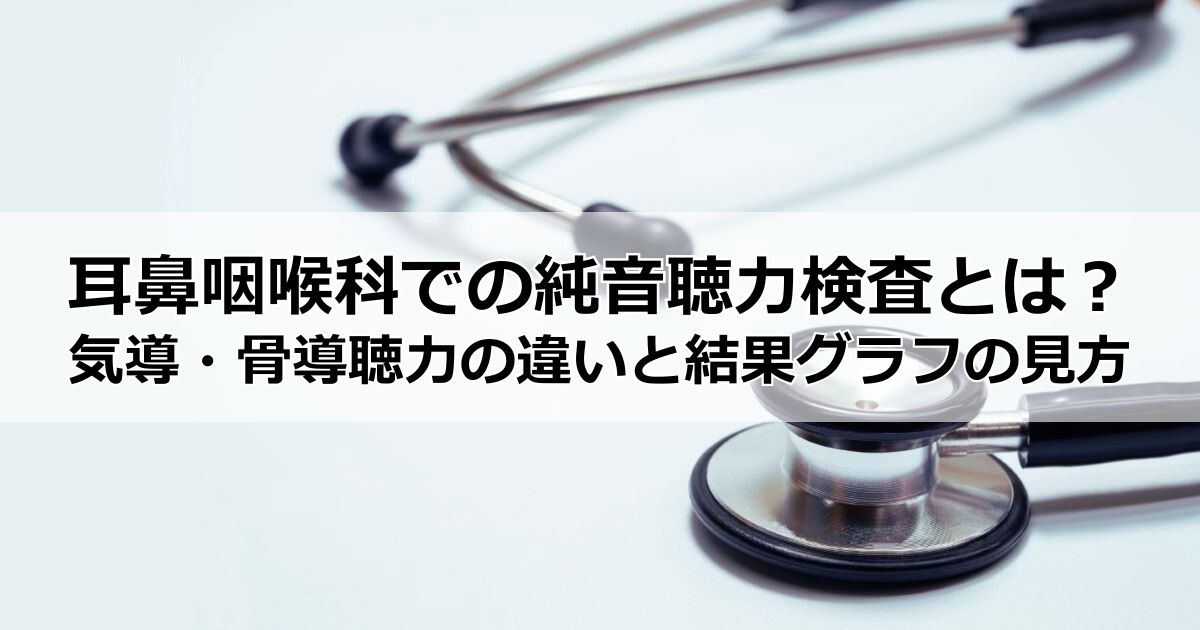
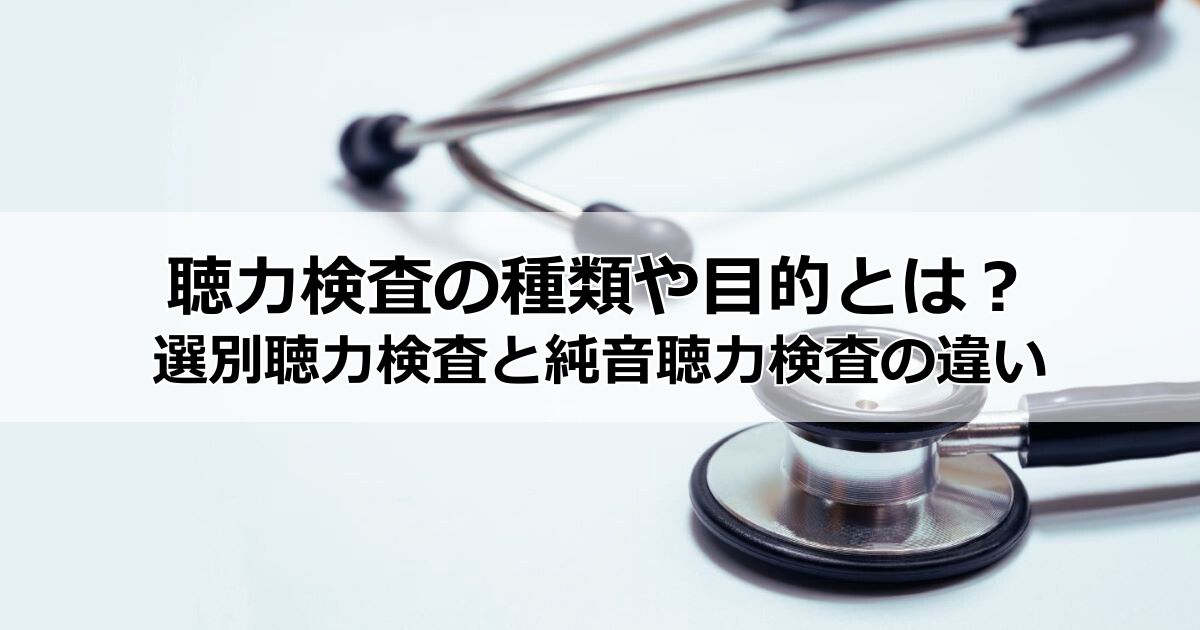
コメント