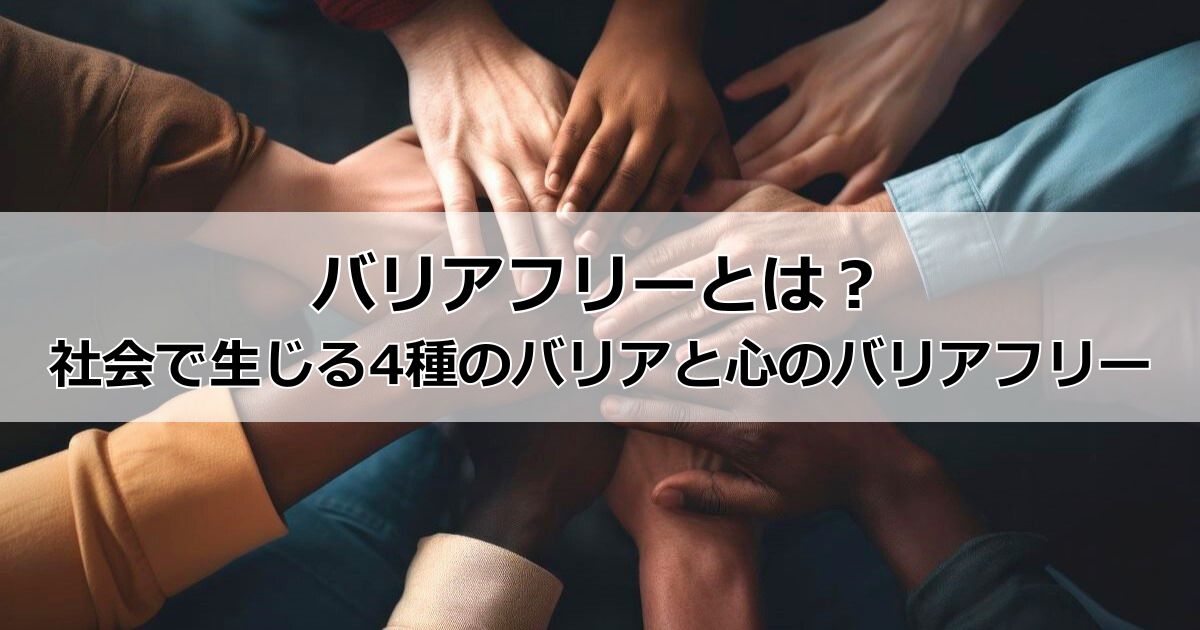
バリアフリーという言葉を聞いて、あなたなら何を思い浮かべるでしょうか。
バリアフリーとは、年齢や性別・仕事・教育・環境など異なる多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすことです。
多様な人たちのことが考慮されていない社会は、障害がある人などにとって多くのバリアを生み出しています。
例えば盲導犬を同伴しての入店を断られたり、点状ブロックの上に自転車が置かれていて通路を妨げられたりするなどです。
障害の有無にかかわらず高齢の人でも妊娠中の人でも、どんな立場でも安心して生活をする上でバリアフリーは重要となります。
この記事ではバリアフリーとは何か、4種類あるバリアそれぞれの意味や例、最も重要とされる心のバリアフリーについて解説します。
筆者が直面した聴覚障害におけるバリアも紹介しますので、1人ひとりが多様な人のことを思いやれる心のバリアフリーを広げる機会になれば幸いです。
バリアフリーとは
バリアフリーの「バリア(barrier)」は、英語で「障壁(しょうへき)」という意味の単語です。
バリアフリーとは、生活を送る中で不便を感じることや社会において活動をしようとする時に壁になっているバリアを取り除く(フリーにする)ことを指します。
バリアフリーの概念、本来の意味
バリアフリーという言葉は、もともとは建築用語として道路や建築物の段差などを除去するという意味で使われていました。
近年では障害のある人や高齢者をはじめ、多様な人たちの社会参加を困難にしているすべての分野においてバリア(障壁)を取り除く意味で用いられています。
私たちが暮らす社会には外見や性格、能力も人それぞれ異なり、年齢や性別、国籍、仕事、受けてきた教育や育った環境などもさまざまです。
そんな多様な人がいるにもかかわらず多数を占める人に合わせて社会がつくられたために、多数の人が不便に感じないことでも少数の人たちにとっては不便さや困難さを生むバリアとなっています。
障害者の状況とバリア
内閣府の障害者白書(令和6年版)によると、日本国内で身体障害・知的障害・精神障害のある人は国民のおよそ9.2%です。
| 身体障害者 | 436万人 |
| 知的障害者 | 109万4000人 |
| 精神障害者 | 614万8000人 |
障害のない人に合わせた社会は、障害のある人にとっては生活しにくい環境があり困難や不便なことを生むバリアとなっています。
障害のある人もない人も含めた全ての人たちが参加しやすい社会にしていくためには、どのようなことがバリアになっているのか、それを解消するために何ができるのかを考えていく必要があるのです。
4つに分類されるバリア
社会にあるさまざまなバリアは、大きく4種類に分けられます。
| バリアの分類 | 概要 |
|---|---|
| 物理的なバリア | 公共交通機関や建物などで困難をもたらす障壁 |
| 制度的なバリア | 本来もつ力を出せず健常者と同じ行動の機会を奪われる障壁 |
| 文化・情報面のバリア | 伝達が不十分なために必要な情報が平等に得られない障壁 |
| 意識上のバリア | 偏見や差別など障害のある人や高齢者を受け入れない障壁 |
次項では、上記4つのバリアそれぞれにどういった障壁があるのかを説明しながら一例を紹介します。
筆者が直面した障壁も一部紹介しますので、聴覚障害をもつ人が抱くバリアの例としても参考にしてください。
(1)物理的なバリア
物理的なバリアは、公共交通機関、道路、建物などにおいて利用者が移動するのに困難をもたらす障壁のことです。
主に車いすの人や足の不自由な人が建物の入口や歩道に段差があって通れない、スペースの狭い駐車場で車いすを使用している人は車の乗り降りが困難などがあります。
物理的なバリアの一例
物理的なバリアとして挙げられる主な例としては、以下の通りです。
- 狭い通路や急こう配の通路
- 建物や道路など移動時の段差や滑りやすい床
- 駅のホームと電車の隙間や段差
- 駅の狭い改札口やホームまでの階段
- 乗降口に段差のあるバスなどの公共交通機関
- 車いすの人が利用できないトイレ
- 車いすの人や子どもには届かない設置物
- 路上の放置自転車 など
筆者が直面した物理的なバリア
物理的なバリアは、移動面における困難や不便に見られるため、特に車いすの人や視覚に障害がある人に起こるケースが多いです。
筆者が直面した聴覚障害における物理的なバリアは、あまりありません。
ただ聴力が低下するほど平衡感覚も劣ってくるため、段差には気をつける必要があります。
とくに階段の時は、視界に入ってくる周辺の動きに惑わされることがあるため踏み外すことも多いです。
(2)制度的なバリア
制度的なバリアは、社会の制度やルールによって障害のある人が本来のもっている力を出せず普通の人と同じ行動の機会を奪われている障壁のことです。
主に障害によって資格や免許取得などの付与が制限される、補助犬を連れての入店を断られるなどがあります。
制度的なバリアの一例
制度的なバリアとして挙げられる主な例としては、以下の通りです。
- 盲導犬同伴で利用できないレストランやホテル
- 障害によって制限される資格・免許取得の付与
- 障害の有無で制限される入試や就職、資格・免許試験
- 点字や音声による受験を認めてくれない各種試験
- 幼児を連れての入店を断る店 など
補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)に対する理解が不十分なために入店を断られたり電車内で非難されたりするケースが多いですが、2003年(平成15年)の身体障害者補助犬法により盲導犬などの同伴を断れないことになっています。
身体障害者補助犬法については、別記事で紹介します。
筆者が直面した制度的なバリア
筆者が直面した聴覚障害における制度的なバリアは、資格・免許試験の時に音声によるアナウンスのみで行われることでした。
近年ではオンラインによる受験も増えていますが、試験会場によっては液晶モニターを置いていない場合もあるため事前に確認することをおすすめします。
他にも語学に関する試験にはヒアリングがあり、資格の種類によっては質疑応答という形の面接・口述試験があります。
筆者もある資格の1級を取得しようと思ったものの、筆記試験とは別に口述試験もあったため2級に留まっています。
(3)文化・情報面でのバリア
文化・情報面でのバリアは、情報の伝え方や伝達手段が不十分なために必要な情報が平等に得られない障壁のことです。
主に聴覚に障害のある人が車内アナウンスだけで情報が得られない、テレビの内容がわからないなどがあります。
文化・情報面でのバリア一例
文化・情報面でのバリアとして挙げられる主な例としては、以下の通りです。
- 車内や館内のアナウンスやテレビなどの音声情報
- 点字や手話通訳のない講演会などのイベント
- タッチパネル式のみの操作盤を使った各種手続きや注文
- 文字が読めない、信号がわからないといった視覚情報
- 障害によって制限される文化活動の機会
筆者が直面した文化・情報面でのバリア
筆者が直面した聴覚障害における文化・情報面でのバリアは、まず病院や役所、民間施設での呼び出しです。
大きい病院や一部の商業施設では受付番号での案内表示がありますが、音声アナウンスによる呼び出しとなる場合は受付の人に相談することをおすすめします。
また講習やセミナーでは講師の口頭による講演が多いことから、できるだけ字幕やテロップが入っているオンライン講習に絞って選択する必要があります。
(4)意識上のバリア
意識上のバリアは、偏見や差別、無理解など障害のある人や高齢者を受け入れない障壁のことです。
主に精神障害のある人は何をするかわからない、外見からわかる障害にかわいそうに思うなどがあります。
意識上のバリア一例
意識上のバリアとして挙げられる主な例としては、以下の通りです。
- 点状ブロックの上に自転車などの物が置かれていること
- 見た目でわかる障害を奇異な目で見ること
- 障害のある人をかわいそう・気の毒だと思うこと
- 通学路や駅前、車いす用駐車スペースでの迷惑駐車
点状ブロックがある理由や意味に無関心な場合、その上に自転車や物を置いたり無意識に立ったりすることで視覚障害のある人のバリアをつくってしまいます。
筆者が直面した意識上のバリア
筆者が直面した聴覚障害における意識上のバリアは、見た目からはわかりにくいことによる偏見や差別です。
筆者は生まれた時から聴力がないため言葉を自然に覚えることができず、幼児時代のうちに言語訓練を受けたことによって発話ができています。
ただ完全な訓練を受けることは難しいため、発音が普通と違うことにより奇異な目で見られることもあります。
場合によっては、外国人に見られることも少なくありません。
聴覚だけに限りませんが、目に見えない障害は解決が難しいのが現状です。
意識上のバリアは心のバリア
障害者を支援しなければいけないという考え方も障害者を理解しているように見えますが、障害がない自分のほうが上だという思いからきていることもあります。
障害をもつ人は、好き好んでなったわけではありません。
バリアフリーに対する健常者の認識不足などにより障害のある人や高齢者などへの無理解や偏見などが生じることは、いわゆる心のバリアともいえるのです。
後にも解説しますが、心のバリアを解消するためには共に行動する機会を増やすなど偏見や差別をなくしていくことが大切です。
障害のある人にとってのバリア
前述ではバリアの一例を種類別に紹介しましたが、障害があるとひと口にいっても障害にはその種類や程度によってさまざまです。
障害があることが外見からはわからない人もいるため、困っていることや不便なことがそれぞれ違います。
ここでは、障害の種類によってバリアとなる主な内容を説明します。
聴覚に障害のある人
聴覚に障害のある人は耳が全く聞こえない聾者(ろう者)、聞こえにくい難聴者など聴力のレベルや聞こえ方に個人差があります。
耳(聴覚)からの情報収集が困難なため、文字情報や視覚による情報などで伝えることが必要です。
また言語の障害により声を出して話すことが難しい人は、一般的に音による情報収集が難しいため筆談や手話、文字情報などで伝える必要があります。
視覚に障害のある人
視覚に障害のある人は全く見えない全盲の人、見えないけど光が感じられる光覚の人、眼鏡などで矯正しても視力が弱い弱視の人、見える範囲が狭い人(視野狭さく)、色の見え方が異なる色覚異常の人などさまざまです。
目(視覚)からの情報収集が困難なため、音声による情報や触覚情報などで伝えることが必要です。
また弱視や色覚異常の人には、文字を大きくしたり色の対比を明確にしたりして伝える必要があります。
肢体に障害のある人
肢体に障害のある人は、麻痺などで手や足など身体のどこかが動かない・動かしにくいなど人によって状態はさまざまです。
日常生活を送るために義肢などの補装具や車いす、杖などを使う必要があります。
身体の内部に障害のある人
身体の内部に障害のある人は、病気などで心臓や腎臓、呼吸器、胃腸、肝臓、免疫機能など状態によってさまざまです。
外見からはわかりにくいのが特徴ですが、疲れやすかったり長時間立っているのが難しかったりするほか頻繁にトイレへいく必要がある人もいます。
知的障害・発達障害・精神障害がある人
ここまでは身体における障害について解説しましたが、他にも知的障害・発達障害・精神障害というのがあり個人差が大きいため人によって状態は異なります。
読み書きや計算が苦手だったり社会生活や日常生活を送りづらかったりする点では、身体に障害をもつ人と同じです。
何よりも大切な心のバリアフリー
多様な人にとって暮らしやすい社会をつくるためには、バリアの種類で4つ目に紹介した意識上のバリアをなくすことが重要です。
意識上のバリアをなくすためには、1人ひとりによる「心のバリアフリー」が求められます。
心のバリアフリーというのは、バリアを感じている人の立場や身になって考え、バリアをなくすための行動を起こすことです。
まず家庭や職場、学校、地域の集まりなどで自分の周りにはどのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみてください。
以下のようにさまざまなバリアに気づいたら、障害のある人などが必要な物事を利用しやすいように配慮したいものです。
- 店の前や道路の段差で車いすの人が入りづらそうだったら
- 街中で白い杖をもって歩いている人が目的の方向に迷っていたら
- 優先席の前にペースメーカーや杖をもった高齢者が立っていたら
- 電車内でマタニティマークをつけている人が近くにいたら
- 列に並んでいる時に後ろでベビーカー利用者が待っていたら
バリアに気づいた時には、○○しましょうか?などと声をかけてみましょう。
困っていそうではあるけど何に困っているのかわからない、またどんなことをすべきかわからないこともあります。
そんな時には、何かお困りでしょうか?・できることはありますか?などと聞いてみてください。
もちろん、中には自分でできる人や助けが要らない人もいるため声をかけても断られるケースもあります。
しかし誰もが受け入れられる社会をつくっていくためには、ひと声が無駄だったとしても1人ひとりがバリアに対する意識をもって行動を起こしていくことが大切です。
障壁を取り除くバリアフリーまとめ
障害のある人をはじめ、多様な人が社会に参加する上で生じる障壁を取り除くバリアフリー。
駅や公共交通、商業施設など街中で見られるバリアフリーを目にして、どんな意味がありどういった目的や助けになるのか意識を傾けてみてください。
障害のある人それぞれの特性を理解して、その人の目線になってみると何がバリアになっているのかが見えてくるのではないでしょうか。
もちろん障害がある人だけでなく高齢の人や妊娠中の人、ベビーカーを引き連れている人もいます。
どんな立場の人でも、もし人の手を借りる必要がありそうな現場に遭遇したら。
あなたの中にある心のバリアフリーを、少しでも分けてあげてください。
以下の記事では、駅や交通機関、商業施設など街中にあふれるバリアフリーの設備や装置について紹介していますので併せてお読みください。
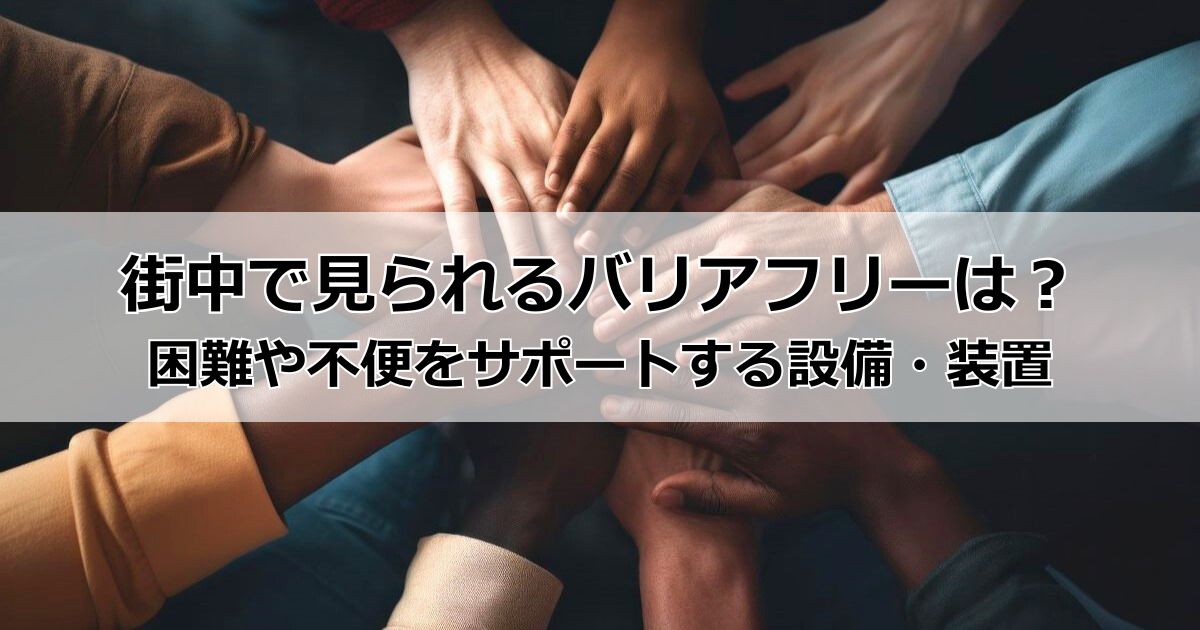




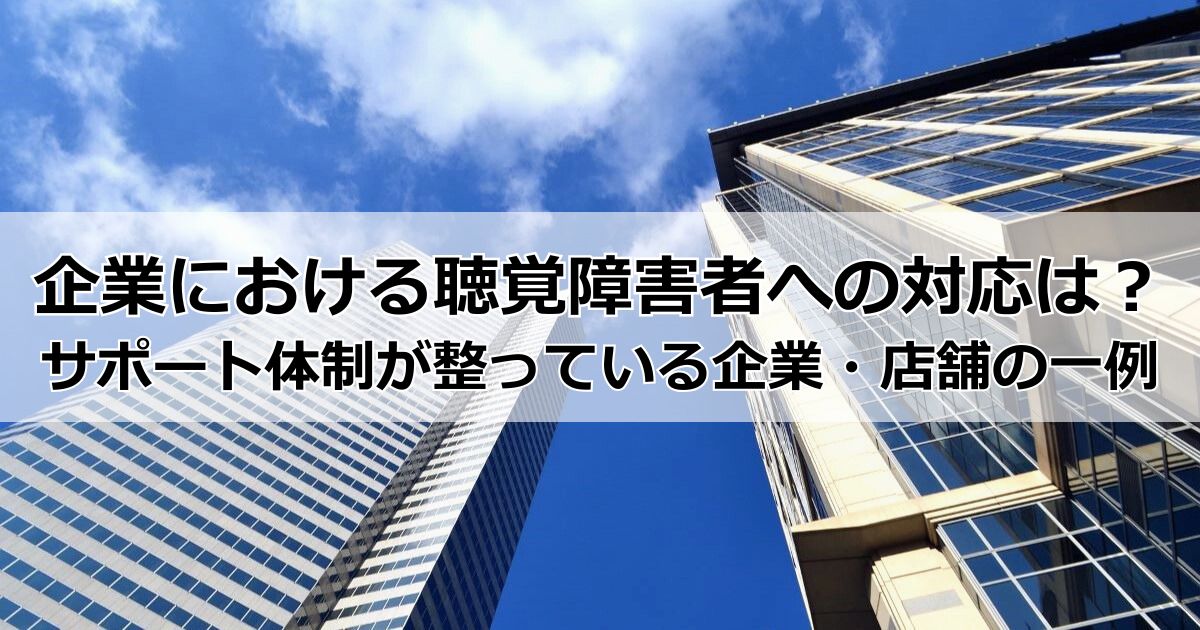
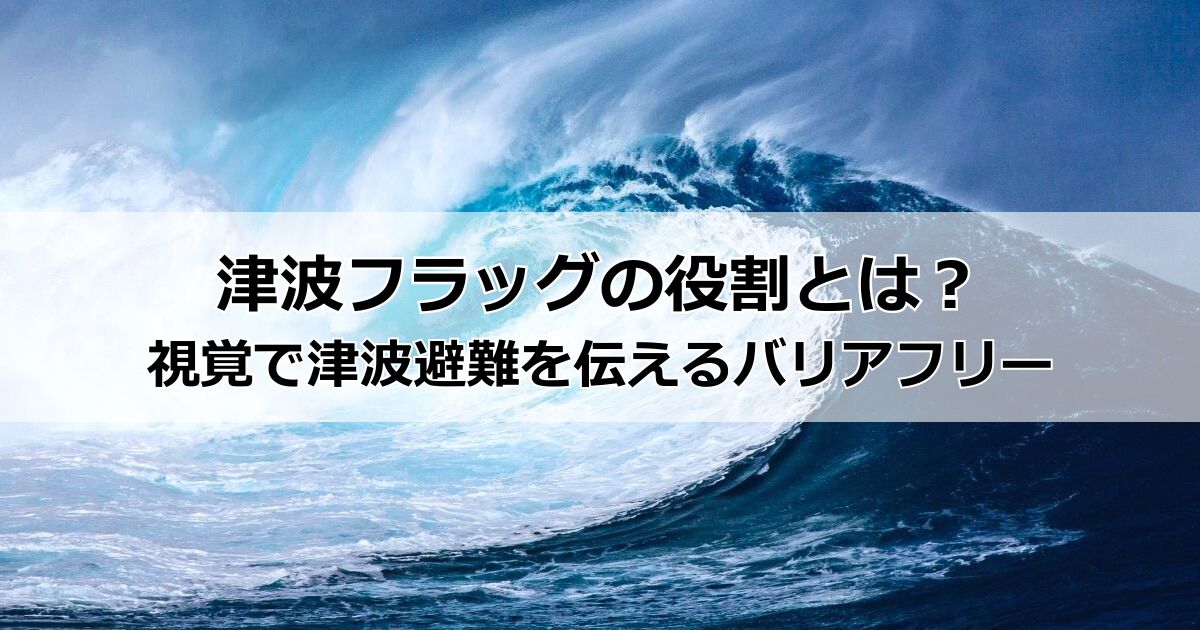
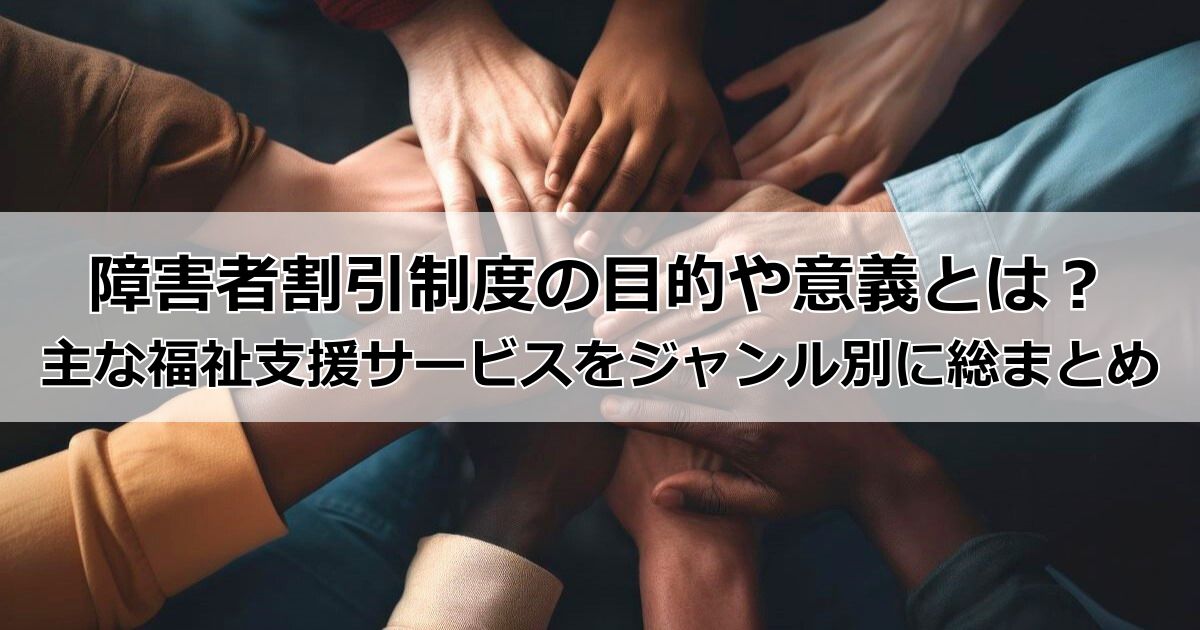

コメント