
難聴の人や聴覚に障害のある人は、補聴器をつけたり手話を使ったりしてコミュニケーションを図っています。
耳が不自由な人には聴力の程度や症状など、1人ひとりの困りごとや悩みもさまざまです。
コミュニケーションのとり方や聞こえ方がそれぞれ異なるために、手話を使えば誰でも会話が成り立つ・電話のベルが聞こえるなら内容も聞き取れるといった誤解が多くあります。
この記事では難聴の人や聴覚障害者に対してどんな誤解があるのか、その一例を紹介します。
誤解を受けがちな事例を知ることでどうやったらスムーズなやりとりができるのか、コミュニケーション方法についても解説しますので参考にしてください。
難聴の人や聴覚障害者に対する誤解
難聴の人や聴覚障害者に共通するのは、聞き取れない・聞こえないことです。
中には聴力が低下し始めた段階であるなど、軽度の難聴であれば聞き取ることに問題のない人もいます。
実際にはさまざまな事情で難聴・失聴になり、コミュニケーション方法は聴力の程度や症状、聞こえ方などで異なり人それぞれです。
そんな難聴の人や聴覚障害者とのやりとりにおいて誤解されやすいことは、主に以下の通りです。
補聴器を使って聞き取れるor聞き取れない
医療機器である補聴器を使用している難聴の人や聴覚障害者は、基本的に周りの音や相手の声を聞き取れることが大半です。
しかし補聴器を装用しているからといって、全ての音声を聞き取れるわけではありません。
相手の発する会話の声量ではよく聞こえても、高い声・低い声といった音程や歯切れがよい・悪いといった音質などによっては聞き取れないこともあります。
補聴器のボリュームを上げて大きくしても周りの音も入ってくるため、相手の話し声が必ずしも明瞭に聞こえているとは限らないのです。
手話を使えるor使えない
難聴の人や聴覚障害者の中には、手話を使ってコミュニケーションをとる人もいます。
しかし耳の不自由な人が全員、手話を使うわけではありません。
とくに途中で聴力を失った中途失聴者はもともと聞こえていた聴者であり、手話を必要とせず発話ができているためです。
なお、音声言語を身につける前に聴力を失っている聾者(ろう者)は、主に手話をコミュニケーション方法としています。
読唇術を使えるor使えない
難聴の人や聴覚障害者は、読唇術という唇の動きを読んで相手の発する会話の内容を理解しやりとりすることが可能です。
しかし難聴になった事情や症状、コミュニケーション方法によっては読唇術を使えない人もいます。
また基本的に読唇術を使ってやりとりをする難聴の人でも、話す相手がマスクをしていたり唇の動きが小さかったりすると相手の話す内容を読み取ることが難しいです。
逆のパターンによる誤解もある
上記とは逆のパターンによる誤解も、実はあります。
例えば健聴者の立場から見た時に、難聴者であることが事前にわかっていても手話が使えないことはコミュニケーションがとれないと誤解されることもあります。
手話を使わない難聴の人や聴覚障害のある人は、基本的に発話が可能だと考えてよいでしょう。
補聴器を使っていない人でも会話ができないと思われがちですが、軽度の難聴であれば健聴者とほぼ同じようにやりとりが可能です。
手話をコミュニケーション方法とする聾者(ろう者)は声を発しないというイメージがありますが、難聴や聴覚障害のある人の中には声を出して話せる人もいます。
誤解が多いことは個人差がある表れ
前述の通り難聴や聴覚障害がある人は、1人ひとりの聴力レベルや症状などによって聞こえ方が異なります。
さまざまな誤解があることは聞こえ方がそれぞれに異なる、つまり個人差による違いが大きいことの表れです。
他にもある誤解の一例
他にもよくある誤解として以下のようことがありますので、あくまで一例として参考にしてください。
- 会話ができるなら電話もできるだろう
- 雑談はできるから仕事の話もできるだろう
- 発音がきれいだから聞こえているだろう
- 電話のベルが聞こえるから内容も聞き取れるだろう
- 音声案内のチャイムが聞こえるから内容も聞き取れるだろう
- 1対1での会話ができるから複数人での会話もできるだろう
健聴者(聴者)から見て、難聴の人や聴覚障害者と直接対話ができるからといって電話ができるわけではありません。
とくに口元の動きを読む読唇術を使って相手の発話内容を理解してやりとりしている場合は、電話をはじめ公共・民間施設内の音声アナウンスも聞き取れません。
また読唇術を使って雑談ができているからといって、全員が仕事の話ができるとは限りません。
雑談は基本的に相手が1人であることが多くその人の口元に集中できますが、数人で仕事の話をする時はそれぞれの発する内容が追いつかないことが多くあります。
発音がきれいだからといって聞こえていると思われがちですが、例えば途中で難聴や失聴になった人はすでに音声言語を身につけている元健聴者であるため、これまでの発話を変えずに話すことが可能です。
電話のベルが鳴っているのが聞こえたとしても、電話での会話内容が聞き取れるわけではありません。
音量の違いもありますが、単純な通知音と相手の話す複雑な内容が同じではないためです。
公共・民間施設内や交通機関の音声案内も同様で、案内開始のチャイムが聞こえたとしても案内の詳細までは聞き取りが不可能なことが多いです。
また近年で注目されているワイヤレスイヤホンですが、道路交通法の違反とされている自転車でのイヤホン装着が補聴器と間違えられやすく指導を受けることも少なくないようです。
個人差による違い
前述の通り補聴器や手話、読唇術が使えるからといって、難聴の人全員が同じように聞き取れるわけではありません。
耳の不自由な人への誤解は、難聴の程度や障害の種類、育った環境などの個人差が大きいです。
全員に共通しているのは、文字や図・イラストなどといった視覚的な情報が非常に重要な情報源である点です。
そのため、街中にはピクトグラムを用いた視覚で伝わる情報のバリアフリーがあふれています。
バリアフリーについては、別記事で紹介します。
筆者の例:補聴器+読唇術(手話不可)
筆者は生まれつき聴覚障害があり、補聴器を装用しています。
しかし補聴器をつけているからといって、全ての会話を聞き取れている可能性はありません。
声量の大きさは補聴器でも調節が可能ですが、相手の声質が高い・低いだけで聞こえ具合が違います。
事実をいってしまえば低い音や声は聞き取りやすく、高い音や声は割れて聞こえるという状況です。
またはっきりと明確な口調で話す人は聞き取れても、発音が繋がっているような滑舌や癖のある話し声は聞き取れないことが多いものです。
そのため補聴器にプラスアルファする形で、長年訓練してきた読唇術に頼って相手の発する言葉を読み取っています。
また生まれつき難聴の人でも手話を使う人は多いですが、必ずしも手話を使えるとは限らず筆者も手話ができません。
人は生まれた時から耳に入ってくる周りの音や声で言葉を理解しますが、生まれつき耳が聞こえない筆者は言語の発達が遅れました。
語彙数がないことによりまず言語を覚えることが優先にあったため、手話を覚えさせられることはありませんでした。
これは健聴者の多くに手話が使えないことを理解していた、母による判断が大きいです。
当時は看護婦だった母は専門外ではあったものの、筆者に対して普通の人と同じ生活ができることを望んでいました。
小学校で特別学級への入学を勧められたものの断ったくらいです。
そこで小学校に上がるまでに手話による対話ではなく口話による対話ができるように、看護婦を辞めて筆者が言語を取得するための訓練を優先しました。
快適なコミュニケーション方法
前述の通り難聴の人や聴覚障害者に対する誤解が多く出てきたところで、どうしたら支障なくやりとりができるのでしょうか。
ここでは、難聴の人や聴覚障害者とのコミュニケーション方法について会話方法別に紹介します。
- 補聴器を装用している人には
- 読唇術を使っている人には
- 音声翻訳ツール・字幕アプリ
- 確実なのは…筆談
補聴器を装用している人には
補聴器を装用している難聴の人との対話は、話す時の声量を大きくすれば聞き取れるわけではないことに留意してください。
補聴器には、音量の大小を調節する機能がついています。
しかし高い声・低い声といった音程、明瞭な話し方や滑舌といった音質を調節することは不可能なため、聞き取りにくい声質の人の話し声は聞き取りづらい傾向が多いです。
補聴器の影響だけでなく、もともとの聴力により高い声が聞き取れなかったり低い声が入りづらかったりすることも当然あります。
読唇術を使っている人には
読唇術を使っている人との対話には、口元をできるだけ動かしながら話すことがポイントです。
ただし一文字一文字で伝えるよりも、文節ごとに区切って話すほうがより伝わりやすいです。
一文字一文字だと例えば「あ」と「か」、「み」と「び」では口元の形がほぼ同じに見えます。
母音のあ行・い行・う行・え行・お行の並びははっきり区別しやすいですが、子音の「あかさたなはまやらわ」など基本的に同じ口元の形になるため、文節ごとに分けて伝えたほうが理解しやすいです。
筆者も基本的に読唇術に頼って対話をしており、一文字一文字での話し方では内容が読めません。
そのため単語あるいは文節ごとに区切って伝えてもらったほうが、その先の言葉つまり内容の続きが想像できて理解しやすくなります。
なお読唇術は慣れや訓練が必要な場合があり、全ての難聴者が理解できるわけではありません。
またマスクなどで口元が見えない環境では、コミュニケーションをとることが困難ですので注意しましょう。
音声翻訳ツール・字幕アプリ
スマートフォンの流通により、近年のデジタル端末には音声を文字に変換してくれるツールやアプリが増えてきました。
精度も速度も向上してきているため、難聴者向けのコミュニケーションとしても利用することが可能です。
しかし口話の文字への自動変換には誤字がまだ多いため、難聴や聴覚障害者への情報伝達は課題が残っています。
それでも会話や仕事など内容の意図が伝わるため、1つのコミュニケーションツールとして活用してもいいでしょう。
音声翻訳ツール・字幕アプリについては、別記事で紹介します。
確実なのは…筆談
難聴の人や聴覚障害者とのやりとりで、確実に伝えられる方法として筆談があります。
メモ帳やノートなど用紙タイプでもいいですが、毎回要件ごとに紙を捨てることになるため環境エコを考えると繰り返し使える筆談ボードが効率的です。
筆者もコンパクトな筆談ボードとして携帯しており、書いてはきれいに消してを繰り返すことができて何度も使い回せます。
用紙に書くやりとりでは、対話が終わった後に捨てることになります。
せっかく書いてくれた人の厚意を無下にする気がして申し訳ない気持ちにもなるため、キングジムのブギーボード(booogie board)を筆談ツールとして持ち歩いています。
キングジムのブギーボード(booogie board)は、軽くてコンパクトなだけでなく書き心地もよくしっかり消去できるのでおすすめです。
難聴の人や聴覚障害者への誤解まとめ
コミュニケーションのとり方や聞こえ方で誤解されがちな、難聴の人や聴覚障害者。
例えば手話を使えば誰でも話が通じる、補聴器をつけているから聞こえているはず、全く音のない沈黙の世界にいる、などです。
1人ひとりにおける聴力の程度や症状などが異なるために、難聴をひとくくりにしてしまうと対応を誤ります。
もし、目の前にいる難聴の人や聴覚障害者と接することになったら。
どういった会話方法が適しているのか、やりとりで困難なことは何かを少しずつ見極めながらコミュニケーションをとっていってください。


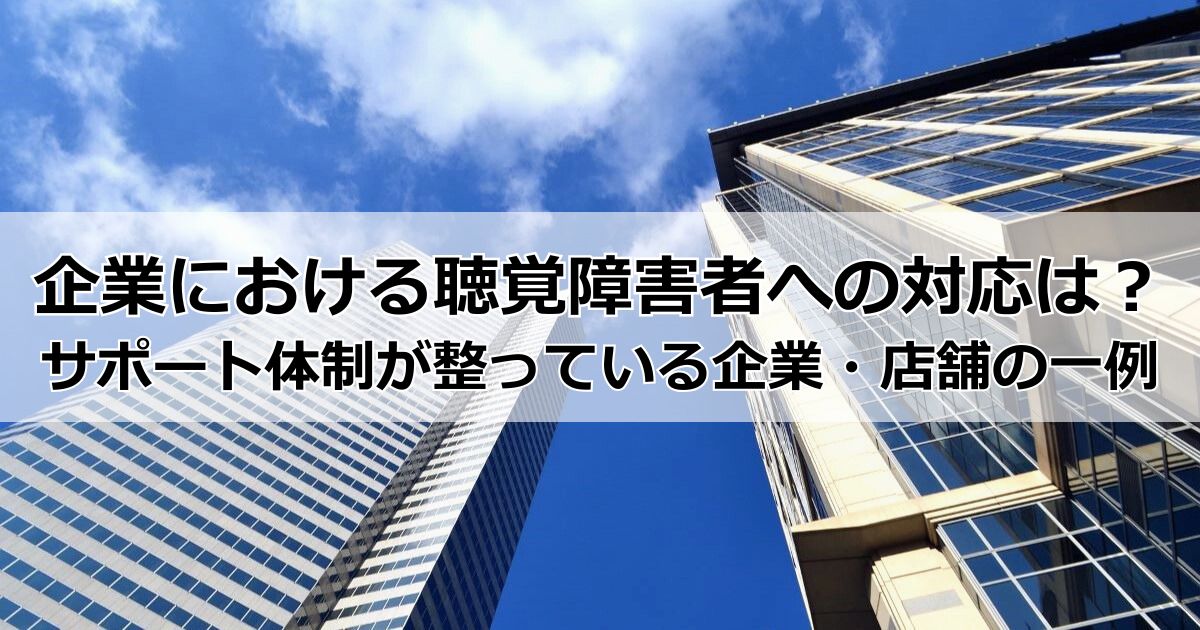
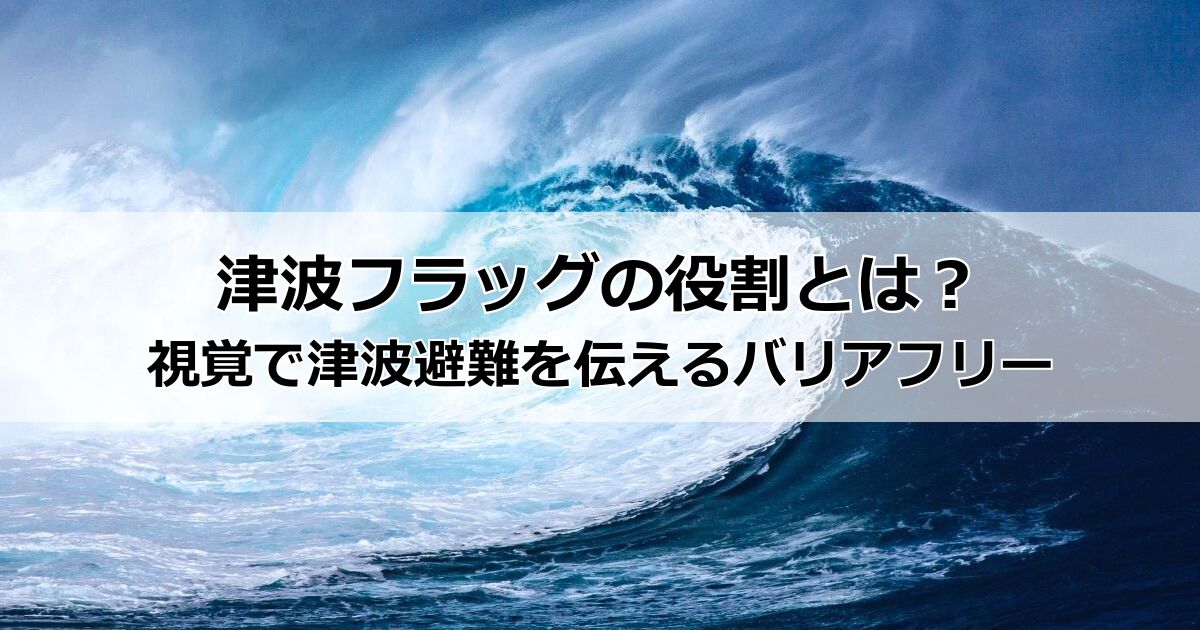

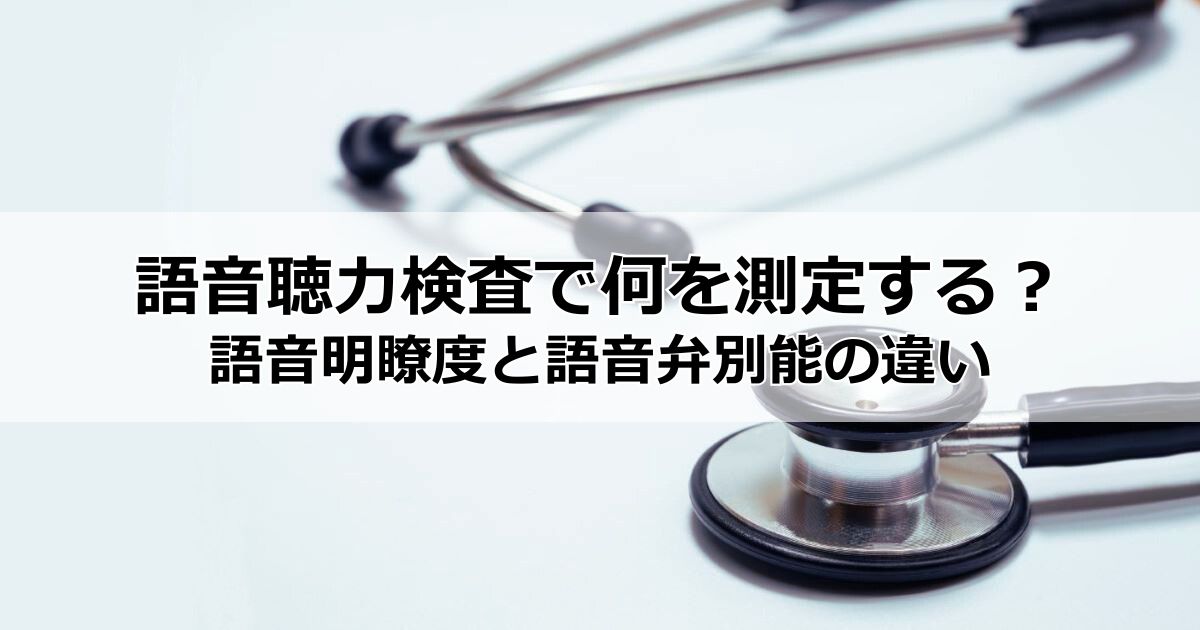
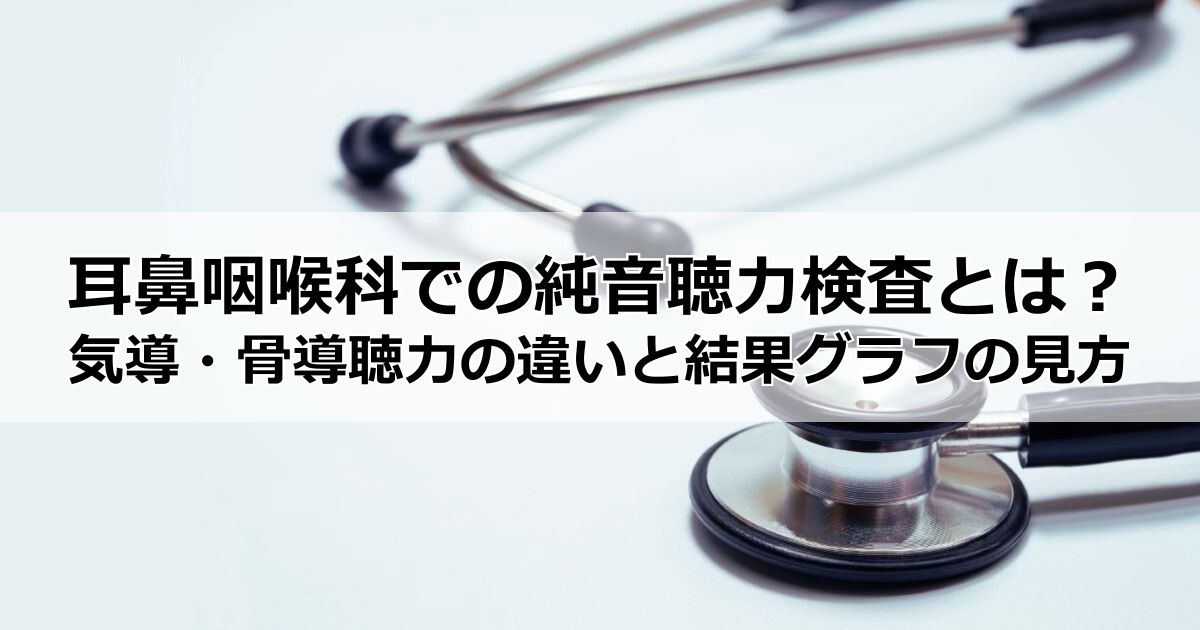
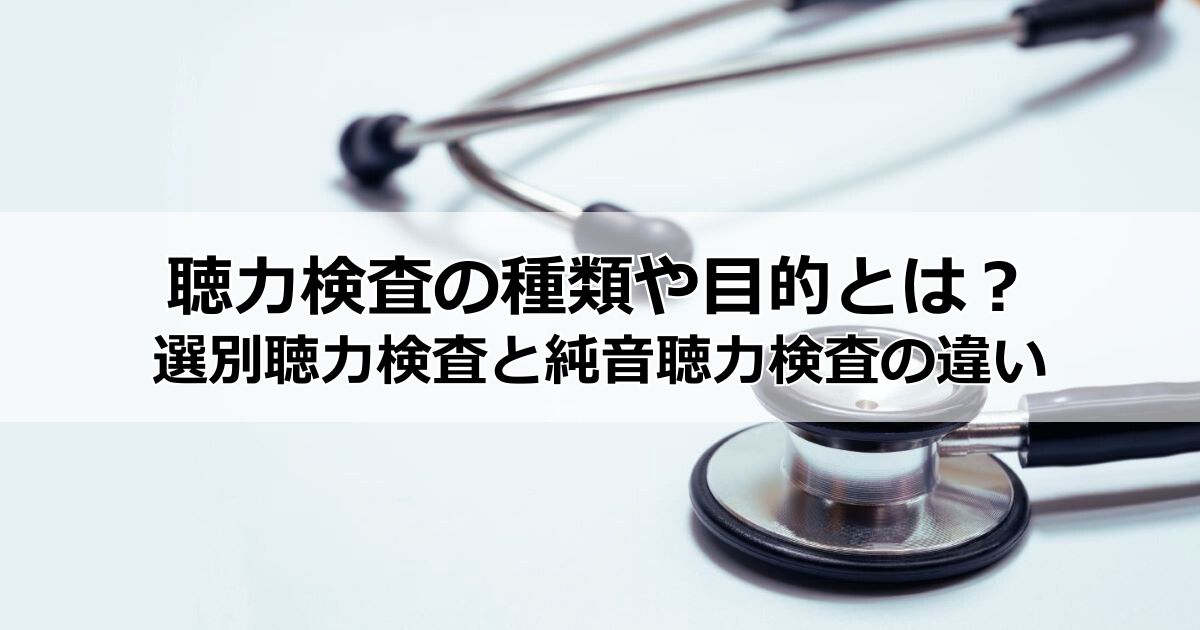
コメント